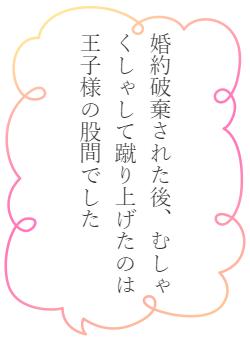幽閉王子は花嫁を逃がさない
「み……見たな……?」
「え、ええ……」
というか、現在進行形で見ている。ナタリアが目を瞬かせて頷くと、カーティスが呻いた。
「恐ろしくはないのか」
「恐ろしくは……特には」
というか、むしろかわいい。触らせてほしい。もしかしたら、尻尾もあるのだろうか。確認したいが、軍のものらしき長い外套に身を包んでいるカーティスの背後を確かめることはできなかった。
そんなナタリアの姿に、カーティスは呆然としていたが――やがて、はは、と乾いた笑い声を漏らした。
「そうだ、きみはそういうやつだったよ……」
「そういうやつ、ってなんですか」
ナタリアが呟くと、カーティスはその彼女の頭をぽんと撫でた。
「もっと早くに、打ち明けていればよかった。俺は――いわゆる先祖返り、というやつでね」
遠い昔、まだ神々が地上にいた頃。王家の祖先は神に銀の狼を伴侶として与えられた。神の力により人の姿を与えられたその狼と交わって、力を得たのだという。
それから幾世代にもわたり、その力は王家を繁栄させてきた。しかし、何代かに一人、カーティスのように力の強すぎる子どもが生まれることがある。
獣の耳と尻尾を持ち、身の内に貯めておけないほどの魔法力を持って生まれる子ども。先祖返りとして大切に扱われる一方で、その力を持て余され、生涯を幽閉されて終わる場合も多い。
しかし、相性のいい異性――王家ではそれを「つがい」と呼んでいるらしい――と交わることができれば、力は安定し、その能力を国のために役立てられるようになるのだという。
「そんなの、眉唾ものだと思っていた。けど、ナタリアに出会えて、わかったんだ」
最初は、それだけだった。ナタリアを抱くだけで、それまで身を焼くようだった魔法力がみるみるうちに安定し、気分が落ち着く。
けれど、とカーティスは続ける。
「次第に――それだけじゃなくて……ナタリアそのものに、俺は惹かれた。だから……こうして、魔法力が安定して父に認められても、きみを塔から出すのが怖くなった」
もしかしたら、塔から出て外の世界に触れたら、ナタリアは自分から去ってしまうかもしれない。そう思うと、不安で不安で、結局そのままナタリアを塔に住まわせていたのだ、と。
「ばかですね、カーティス様」
くすりと笑うと、ナタリアは肩をすくめた。
「私には、行く当てなんかありません。魔法力なしの貴族の娘なんて、ただのお荷物、厄介者で――カーティス様の元に来られなかったら、どうなっていたか」
「ナタリア……」
震える指で、カーティスがナタリアに触れる。そうっと、なにかを恐れるように。
その手をぎゅっと握りしめ、ナタリアはそれに自分の頬を擦り付けた。
「愛してます、カーティス様。ずっと、何があっても――私はあなたから離れない」
◇ ◇ ◇
城の一角には、真っ白い壁の塔がある。蔦の絡んだその塔は、窓に鉄格子がはまり、分厚い扉で厳重に守られている。
塔に立ち入ることを許されているのは、専属のメイド以外にはたった一人。銀の髪の王子だけ。
そして、そこでは――彼の最愛の妻が、今日も帰りを待っている。
「おかえりなさい、カーティス様」
「ただいま、ナタリア」
幸せそうに、カーティスは愛しい妻の身体を抱きしめた。
「え、ええ……」
というか、現在進行形で見ている。ナタリアが目を瞬かせて頷くと、カーティスが呻いた。
「恐ろしくはないのか」
「恐ろしくは……特には」
というか、むしろかわいい。触らせてほしい。もしかしたら、尻尾もあるのだろうか。確認したいが、軍のものらしき長い外套に身を包んでいるカーティスの背後を確かめることはできなかった。
そんなナタリアの姿に、カーティスは呆然としていたが――やがて、はは、と乾いた笑い声を漏らした。
「そうだ、きみはそういうやつだったよ……」
「そういうやつ、ってなんですか」
ナタリアが呟くと、カーティスはその彼女の頭をぽんと撫でた。
「もっと早くに、打ち明けていればよかった。俺は――いわゆる先祖返り、というやつでね」
遠い昔、まだ神々が地上にいた頃。王家の祖先は神に銀の狼を伴侶として与えられた。神の力により人の姿を与えられたその狼と交わって、力を得たのだという。
それから幾世代にもわたり、その力は王家を繁栄させてきた。しかし、何代かに一人、カーティスのように力の強すぎる子どもが生まれることがある。
獣の耳と尻尾を持ち、身の内に貯めておけないほどの魔法力を持って生まれる子ども。先祖返りとして大切に扱われる一方で、その力を持て余され、生涯を幽閉されて終わる場合も多い。
しかし、相性のいい異性――王家ではそれを「つがい」と呼んでいるらしい――と交わることができれば、力は安定し、その能力を国のために役立てられるようになるのだという。
「そんなの、眉唾ものだと思っていた。けど、ナタリアに出会えて、わかったんだ」
最初は、それだけだった。ナタリアを抱くだけで、それまで身を焼くようだった魔法力がみるみるうちに安定し、気分が落ち着く。
けれど、とカーティスは続ける。
「次第に――それだけじゃなくて……ナタリアそのものに、俺は惹かれた。だから……こうして、魔法力が安定して父に認められても、きみを塔から出すのが怖くなった」
もしかしたら、塔から出て外の世界に触れたら、ナタリアは自分から去ってしまうかもしれない。そう思うと、不安で不安で、結局そのままナタリアを塔に住まわせていたのだ、と。
「ばかですね、カーティス様」
くすりと笑うと、ナタリアは肩をすくめた。
「私には、行く当てなんかありません。魔法力なしの貴族の娘なんて、ただのお荷物、厄介者で――カーティス様の元に来られなかったら、どうなっていたか」
「ナタリア……」
震える指で、カーティスがナタリアに触れる。そうっと、なにかを恐れるように。
その手をぎゅっと握りしめ、ナタリアはそれに自分の頬を擦り付けた。
「愛してます、カーティス様。ずっと、何があっても――私はあなたから離れない」
◇ ◇ ◇
城の一角には、真っ白い壁の塔がある。蔦の絡んだその塔は、窓に鉄格子がはまり、分厚い扉で厳重に守られている。
塔に立ち入ることを許されているのは、専属のメイド以外にはたった一人。銀の髪の王子だけ。
そして、そこでは――彼の最愛の妻が、今日も帰りを待っている。
「おかえりなさい、カーティス様」
「ただいま、ナタリア」
幸せそうに、カーティスは愛しい妻の身体を抱きしめた。