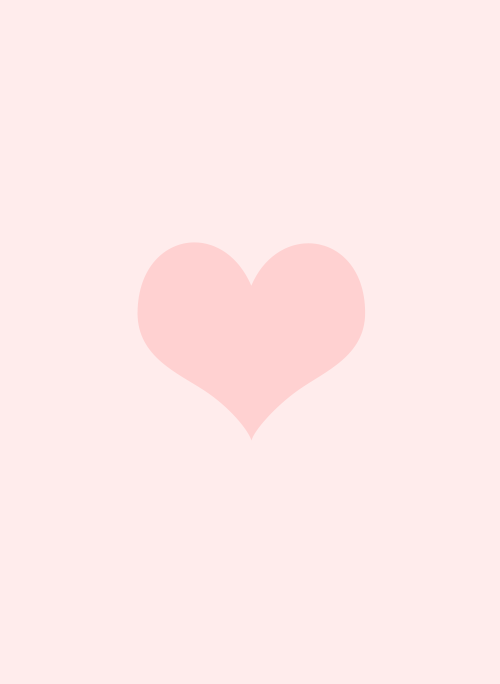その一杯に、恋を少々
第10話「苦味と甘みの間で」
発売日当日。
朝のビルロビーには、見慣れない長蛇の列ができていた。
「これ……全部うちのドリンク目当て!?」
綾子が呆然と声を上げると、隣の英里が満面の笑みで言った。
「ね? “顔”って正義だったでしょ?」
「SNSじゃなくて“口コミポスター”がここまで効くとは……」
悠生が冷静にデータ収集用のタブレットを構え、有里が「レジ横にティッシュ置いて〜」と叫ぶ。
凱はカップの補充とお湯の管理をひたすら繰り返し、背中がすでに汗でぐっしょりだった。
「これだけで一日終わりそうだな……」
海人がぼそりとつぶやくと、綾子がにやっと笑って言う。
「終わりじゃないよ。“始まり”でしょ?」
「……ああ、確かにな」
***
昼過ぎ、ようやくひと段落。
テーブルの端で、綾子と海人は最後の一杯を作っていた。
それぞれが、一つの材料を担当する。黒糖を計る海人。柚子を切る綾子。ミルクの温度を見る凱。器を温める悠生。英里がカップににっこりマークを描き、有里が「紙ナプキン足りてますか〜」と周囲に声をかける。
「これ、ほんとに“みんなの一杯”だね」
綾子が言うと、
「いや。俺たちの“一発目”だ」
海人は、やっぱり不器用にそう返す。
「それにしても、味……変わった?」
綾子が一口含んで、そう言った。
「いや。変えてない。……でも、変わった気がするのは、お前が成分になったからだな」
「……なにその言い回し、キザ」
「事実だ」
「やっぱりずるい。ずっとそう」
綾子は、カップの縁を指でなぞりながら、ぽつりと呟いた。
「……でもね、嫌じゃないよ」
静かに目を合わせた二人の間に、ちょうどよい“沈黙”が生まれる。
温かいけど、甘すぎず。
少しだけ苦いけど、また飲みたくなるような――そんな味。
***
閉店後の試作室。
英里がドリンクの空容器を片付けながら、ふとつぶやく。
「さあて、次はなに作ろっか?」
悠生が即答する。
「“眠くなるのに目が覚める味”とか?」
「それ、地味に需要ありそう!」
有里が笑いながら「私は“飲むだけで人間関係がまろやかになるやつ”が欲しい」と言い、凱が「それ俺が今飲みたい」と頷いた。
綾子がふと、隣を見る。
海人は窓の外を見つめながら、こう言った。
「“飲むだけで、会いたくなるやつ”とかどうだ?」
「……それ、なに? 告白?」
「解釈は任せる」
綾子は、くすっと笑ってから答えた。
「じゃあ、それ、次のテーマにしよっか」
***
ドリンクは、発売一週間で初回製造分が完売。
味覚だけじゃない、“何か”を届ける一杯として、社内外で話題になる。
でも、彼らにとって本当に大切だったのは、そのドリンクが“誰かの記憶”や“気持ち”とつながってくれたこと。
そして何より、自分たち自身を、つないでくれたことだった。
苦味と甘みのちょうど真ん中――
その一杯は、今日も誰かの手に温かく届けられている。
朝のビルロビーには、見慣れない長蛇の列ができていた。
「これ……全部うちのドリンク目当て!?」
綾子が呆然と声を上げると、隣の英里が満面の笑みで言った。
「ね? “顔”って正義だったでしょ?」
「SNSじゃなくて“口コミポスター”がここまで効くとは……」
悠生が冷静にデータ収集用のタブレットを構え、有里が「レジ横にティッシュ置いて〜」と叫ぶ。
凱はカップの補充とお湯の管理をひたすら繰り返し、背中がすでに汗でぐっしょりだった。
「これだけで一日終わりそうだな……」
海人がぼそりとつぶやくと、綾子がにやっと笑って言う。
「終わりじゃないよ。“始まり”でしょ?」
「……ああ、確かにな」
***
昼過ぎ、ようやくひと段落。
テーブルの端で、綾子と海人は最後の一杯を作っていた。
それぞれが、一つの材料を担当する。黒糖を計る海人。柚子を切る綾子。ミルクの温度を見る凱。器を温める悠生。英里がカップににっこりマークを描き、有里が「紙ナプキン足りてますか〜」と周囲に声をかける。
「これ、ほんとに“みんなの一杯”だね」
綾子が言うと、
「いや。俺たちの“一発目”だ」
海人は、やっぱり不器用にそう返す。
「それにしても、味……変わった?」
綾子が一口含んで、そう言った。
「いや。変えてない。……でも、変わった気がするのは、お前が成分になったからだな」
「……なにその言い回し、キザ」
「事実だ」
「やっぱりずるい。ずっとそう」
綾子は、カップの縁を指でなぞりながら、ぽつりと呟いた。
「……でもね、嫌じゃないよ」
静かに目を合わせた二人の間に、ちょうどよい“沈黙”が生まれる。
温かいけど、甘すぎず。
少しだけ苦いけど、また飲みたくなるような――そんな味。
***
閉店後の試作室。
英里がドリンクの空容器を片付けながら、ふとつぶやく。
「さあて、次はなに作ろっか?」
悠生が即答する。
「“眠くなるのに目が覚める味”とか?」
「それ、地味に需要ありそう!」
有里が笑いながら「私は“飲むだけで人間関係がまろやかになるやつ”が欲しい」と言い、凱が「それ俺が今飲みたい」と頷いた。
綾子がふと、隣を見る。
海人は窓の外を見つめながら、こう言った。
「“飲むだけで、会いたくなるやつ”とかどうだ?」
「……それ、なに? 告白?」
「解釈は任せる」
綾子は、くすっと笑ってから答えた。
「じゃあ、それ、次のテーマにしよっか」
***
ドリンクは、発売一週間で初回製造分が完売。
味覚だけじゃない、“何か”を届ける一杯として、社内外で話題になる。
でも、彼らにとって本当に大切だったのは、そのドリンクが“誰かの記憶”や“気持ち”とつながってくれたこと。
そして何より、自分たち自身を、つないでくれたことだった。
苦味と甘みのちょうど真ん中――
その一杯は、今日も誰かの手に温かく届けられている。