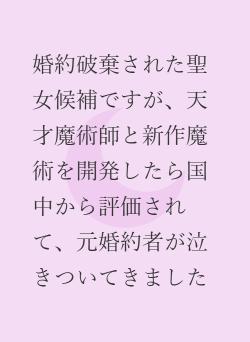貴族令嬢は【魔力ゼロ】の少年との婚約を破棄した。十年後、彼は神をも斬る最強の勇者となり、傲慢な世界に膝をつかせ、ただ私を迎えにきただけだった。
最終話 世界の終わりと、はじまりの中で
雪解けの春が訪れてから、三年目の冬がこの村を包もうとしていた。
辺境の地、フィオレ――森と湖に抱かれたこの場所は、王国の地図からも抜け落ち、誰にも顧みられない静謐な空間として、ただそこに在った。
かつて神を斬り、王国を揺るがした男の姿など、ここにはない。
あるのは、薪を割り、子を抱き、スープを温めるただの父親の姿。
その名も、ノワール。
朝、カローラは戸口を開けて、小さく息をつく。
白い息が空に溶けていき、降り積もる雪はまだ浅く、木々の間から差し込む朝の光が、世界を仄かに照らしていた。
「……寒いわね、今日も」
振り返ると、小さな足音が近づいてくる。
「ママ、ママっ、雪! ほら、ゆきだよ!」
まだ幼い女の子が、嬉しそうに外を指差している。
ふわふわの髪はカローラに似て柔らかく、目元と口元には、どこかノワールの面影が宿っていた。
「ええ、見えてるわ……冷たくなるから、お外はパパが帰ってからにしましょうね」
「うん……でも、あのね、ゆきのにおいって、ちょっとおいしそう」
「ふふ、それは雪じゃなくて、パンの焼ける匂いじゃないかしら?」
母と娘の笑い声が、小さな家の中に柔らかく響いた。
ノワールは、その声を背に受けながら薪小屋から戻ってきた。
戸を開けると、少女が真っ先に駆け寄ってくる。
「パパ、おかえり!」
「ん。……ただいま」
無骨な男の口から返るその一言は、誰よりも誠実で、温かかった。
ノワールは娘の頭をそっと撫で、雪の付いた肩を軽く払い落とす。
その手はかつて神を屠った剣の手でありながら、今はただ、小さな命を優しく包むためだけに存在していた。
カローラは微笑みながら、薪を受け取る。
ノワールと交わす視線の中には、言葉を超えた絆があった。
「朝ごはん、できてるわ……スープ、少し冷めちゃったかも」
「それでいい……熱すぎるのは、あいつにはまだ早いからな」
ノワールはそう言って、娘を片腕に抱え上げる。
娘はくすぐったそうに笑いながら、父の首に小さな腕を回した。
「パパ、きょうもおしごと?」
「ん、昼には終わらせる……雪だるまを作る約束だったからな」
「ほんと!? やったあ!」
その笑顔を、ノワールはただ静かに見つめた。
過去のどんな栄光や、どんな苦しみよりも、この一瞬が、彼にとって最も尊いものだった。
家の中には、暖炉の火が灯っている。
壁には、カローラが押し花にした『白い花』が、額に収められていた。
毎年、春にノワールが贈っていた、誓いの印。
そして今は、その隣に、娘が描いた稚拙な絵――三人で手をつないでいる姿が並べられている。
家族三人――誰にも知られず、誰にも語られない、ささやかで、しかし確かな物語。
それは、世界が拒んだはずの男と、彼を選んだ女、そしてふたりが守ろうと決めた未来の証だった。
ノワールは、そっと娘の手を取りながら、つぶやいた。
「……この手だけは、守り抜く」
ノワールの声は、雪に吸い込まれるように低く、けれど確固たる響きを持っていた。
それは誓いでも宣言でもない。ただ、彼自身に課した決意だった。
誰にも奪わせない。誰にも近づけさせない。
かつて神をも斬り伏せたその手でさえ、いまはただ、小さな命と温もりを包むためにある。
世界が彼を否定しても、歴史がその名を記さなくても構わない。
だが――この手だけは、絶対に手放さない。最後まで、たとえ命が尽きるその瞬間まで。
その横で、カローラがそっと彼の隣に身を寄せる。
衣擦れの音も立てぬほど静かに、けれど迷いなく。
ノワールの腕に肩を重ね、彼の視線と重なるように、静かに言葉を紡いだ。
「ねえ……あなた、幸せ?」
それは突きつけるような問いではなかった。
答えを急ぐ必要もない、ただ確認のような、確かめるような、彼女だけの『祈り』だった。
ノワールは、ほんの一瞬だけ黙し、それから短く、しかし深く頷いた。
その仕草には、飾られた言葉よりも重い真実が宿っていた。
「俺の世界は、もうここにある。お前と……あいつがいる。それだけで、いい」
その声には、一片の虚飾もなかった。
かつて彼が背負っていた国も、剣も、神託も、もうここには存在しない。
残されたのは、名もなきこの村の、小さな家。
そしてそこに息づく、たった三人の暮らし。
それでいい、と彼は思った。いや――それこそが、生涯かけて求めた『本当の世界』だったのだと、今なら確信できる。
カローラは、その言葉を受けて、目を細める。
微笑みというには小さく、涙にするには穏やかなその表情に、すべての答えがあった。
愛している、とも、ありがとう、とも言わない。ただその沈黙が、満ち足りた証だった。
その時、外を見ていた娘が、白い窓辺からこちらを振り返り、ぱっと手を振る。
「パパ!いっしょに、ゆきのなかでおどろうよ!」
その無邪気な声に、ノワールは思わず目を細めた。
かつて耳にしたことのない高音。世界のどんな音楽よりも、心を震わせる呼び声。
「……踊るのは、苦手だ」
そう返す声は、かすかに苦笑を含んでいた。
「いいの! だいじょうぶ、わたしがひっぱってあげる!」
言い切るその声に、ノワールは小さく息を吐いた。
もはや、どんな神の言葉よりも、この声こそが、彼の『命令』だった。
この小さな笑顔を守るためにこそ、彼は生きている。
嘗て、すべての神託に背き、世界を敵に回してまで選んだ未来。
その先にいたのが、今目の前にいる、娘と、その母だった。
小さな笑い声が、ノワールの胸に深く沁みわたる。
十年前、彼は絶望の只中にいた――あらゆるものが敵に見え、信じられるものは何ひとつ残っていなかった。
ただ一人の名だけを、何度も、何度も呼び続けていた。
――カローラ、と。
この声が届くまで、どれほどの血を流したか、どれほど多くの夜を過ごしたか。
だが今、ようやくその手は、彼のものとしてここにある。
そしてもうひとつの手、小さな命が、彼を『パパ』と呼ぶ。
それだけで、世界のどんな勝利にも勝る安らぎが、胸に広がった。
ノワールは娘の手を取りながら、玄関の戸を開けた。
凍える空気が、頬を撫でるように吹き込んでくる。
それを背に、カローラがそっと見送る。
その背――嘗ては王が膝を屈し、神が敗北した力を背負っていたその背は、いまや、ただ一人の父として、子を雪の中へと導いていく。
白く舞う雪の中、小さな足跡がふたつ。
それに続いて、かつての英雄の重い足音が、静かに続いた。
雪が舞っていた。
風が、記憶のように優しく吹いていた。
世界は今日も、彼らの存在を知らないまま、どこか遠くで回り続けている。
けれど、この村の片隅で。
地図にも載らないこの地で。
確かに、誰よりも強く、誰よりも静かな愛が、燃え続けていた。
誰に語られずともいい。祝福されなくても構わない。
それでも、この愛は確かにここにある。
世界の終わりから始まった、たったふたりの物語の、静かで、これからも永遠に続いていく。
辺境の地、フィオレ――森と湖に抱かれたこの場所は、王国の地図からも抜け落ち、誰にも顧みられない静謐な空間として、ただそこに在った。
かつて神を斬り、王国を揺るがした男の姿など、ここにはない。
あるのは、薪を割り、子を抱き、スープを温めるただの父親の姿。
その名も、ノワール。
朝、カローラは戸口を開けて、小さく息をつく。
白い息が空に溶けていき、降り積もる雪はまだ浅く、木々の間から差し込む朝の光が、世界を仄かに照らしていた。
「……寒いわね、今日も」
振り返ると、小さな足音が近づいてくる。
「ママ、ママっ、雪! ほら、ゆきだよ!」
まだ幼い女の子が、嬉しそうに外を指差している。
ふわふわの髪はカローラに似て柔らかく、目元と口元には、どこかノワールの面影が宿っていた。
「ええ、見えてるわ……冷たくなるから、お外はパパが帰ってからにしましょうね」
「うん……でも、あのね、ゆきのにおいって、ちょっとおいしそう」
「ふふ、それは雪じゃなくて、パンの焼ける匂いじゃないかしら?」
母と娘の笑い声が、小さな家の中に柔らかく響いた。
ノワールは、その声を背に受けながら薪小屋から戻ってきた。
戸を開けると、少女が真っ先に駆け寄ってくる。
「パパ、おかえり!」
「ん。……ただいま」
無骨な男の口から返るその一言は、誰よりも誠実で、温かかった。
ノワールは娘の頭をそっと撫で、雪の付いた肩を軽く払い落とす。
その手はかつて神を屠った剣の手でありながら、今はただ、小さな命を優しく包むためだけに存在していた。
カローラは微笑みながら、薪を受け取る。
ノワールと交わす視線の中には、言葉を超えた絆があった。
「朝ごはん、できてるわ……スープ、少し冷めちゃったかも」
「それでいい……熱すぎるのは、あいつにはまだ早いからな」
ノワールはそう言って、娘を片腕に抱え上げる。
娘はくすぐったそうに笑いながら、父の首に小さな腕を回した。
「パパ、きょうもおしごと?」
「ん、昼には終わらせる……雪だるまを作る約束だったからな」
「ほんと!? やったあ!」
その笑顔を、ノワールはただ静かに見つめた。
過去のどんな栄光や、どんな苦しみよりも、この一瞬が、彼にとって最も尊いものだった。
家の中には、暖炉の火が灯っている。
壁には、カローラが押し花にした『白い花』が、額に収められていた。
毎年、春にノワールが贈っていた、誓いの印。
そして今は、その隣に、娘が描いた稚拙な絵――三人で手をつないでいる姿が並べられている。
家族三人――誰にも知られず、誰にも語られない、ささやかで、しかし確かな物語。
それは、世界が拒んだはずの男と、彼を選んだ女、そしてふたりが守ろうと決めた未来の証だった。
ノワールは、そっと娘の手を取りながら、つぶやいた。
「……この手だけは、守り抜く」
ノワールの声は、雪に吸い込まれるように低く、けれど確固たる響きを持っていた。
それは誓いでも宣言でもない。ただ、彼自身に課した決意だった。
誰にも奪わせない。誰にも近づけさせない。
かつて神をも斬り伏せたその手でさえ、いまはただ、小さな命と温もりを包むためにある。
世界が彼を否定しても、歴史がその名を記さなくても構わない。
だが――この手だけは、絶対に手放さない。最後まで、たとえ命が尽きるその瞬間まで。
その横で、カローラがそっと彼の隣に身を寄せる。
衣擦れの音も立てぬほど静かに、けれど迷いなく。
ノワールの腕に肩を重ね、彼の視線と重なるように、静かに言葉を紡いだ。
「ねえ……あなた、幸せ?」
それは突きつけるような問いではなかった。
答えを急ぐ必要もない、ただ確認のような、確かめるような、彼女だけの『祈り』だった。
ノワールは、ほんの一瞬だけ黙し、それから短く、しかし深く頷いた。
その仕草には、飾られた言葉よりも重い真実が宿っていた。
「俺の世界は、もうここにある。お前と……あいつがいる。それだけで、いい」
その声には、一片の虚飾もなかった。
かつて彼が背負っていた国も、剣も、神託も、もうここには存在しない。
残されたのは、名もなきこの村の、小さな家。
そしてそこに息づく、たった三人の暮らし。
それでいい、と彼は思った。いや――それこそが、生涯かけて求めた『本当の世界』だったのだと、今なら確信できる。
カローラは、その言葉を受けて、目を細める。
微笑みというには小さく、涙にするには穏やかなその表情に、すべての答えがあった。
愛している、とも、ありがとう、とも言わない。ただその沈黙が、満ち足りた証だった。
その時、外を見ていた娘が、白い窓辺からこちらを振り返り、ぱっと手を振る。
「パパ!いっしょに、ゆきのなかでおどろうよ!」
その無邪気な声に、ノワールは思わず目を細めた。
かつて耳にしたことのない高音。世界のどんな音楽よりも、心を震わせる呼び声。
「……踊るのは、苦手だ」
そう返す声は、かすかに苦笑を含んでいた。
「いいの! だいじょうぶ、わたしがひっぱってあげる!」
言い切るその声に、ノワールは小さく息を吐いた。
もはや、どんな神の言葉よりも、この声こそが、彼の『命令』だった。
この小さな笑顔を守るためにこそ、彼は生きている。
嘗て、すべての神託に背き、世界を敵に回してまで選んだ未来。
その先にいたのが、今目の前にいる、娘と、その母だった。
小さな笑い声が、ノワールの胸に深く沁みわたる。
十年前、彼は絶望の只中にいた――あらゆるものが敵に見え、信じられるものは何ひとつ残っていなかった。
ただ一人の名だけを、何度も、何度も呼び続けていた。
――カローラ、と。
この声が届くまで、どれほどの血を流したか、どれほど多くの夜を過ごしたか。
だが今、ようやくその手は、彼のものとしてここにある。
そしてもうひとつの手、小さな命が、彼を『パパ』と呼ぶ。
それだけで、世界のどんな勝利にも勝る安らぎが、胸に広がった。
ノワールは娘の手を取りながら、玄関の戸を開けた。
凍える空気が、頬を撫でるように吹き込んでくる。
それを背に、カローラがそっと見送る。
その背――嘗ては王が膝を屈し、神が敗北した力を背負っていたその背は、いまや、ただ一人の父として、子を雪の中へと導いていく。
白く舞う雪の中、小さな足跡がふたつ。
それに続いて、かつての英雄の重い足音が、静かに続いた。
雪が舞っていた。
風が、記憶のように優しく吹いていた。
世界は今日も、彼らの存在を知らないまま、どこか遠くで回り続けている。
けれど、この村の片隅で。
地図にも載らないこの地で。
確かに、誰よりも強く、誰よりも静かな愛が、燃え続けていた。
誰に語られずともいい。祝福されなくても構わない。
それでも、この愛は確かにここにある。
世界の終わりから始まった、たったふたりの物語の、静かで、これからも永遠に続いていく。