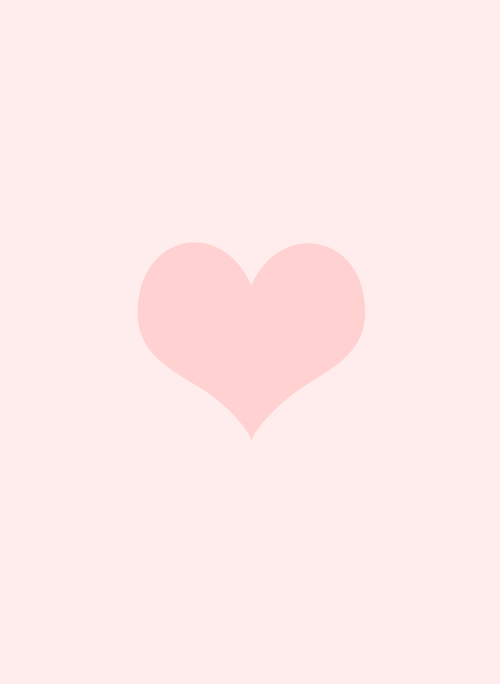ハイスペ男子達の溺愛が止まりません!
17,一歩
「白雪さん、少しお時間良いですか?」
学校に着いて早々、青柳くんに声をかけられた。
いつもは私が1番初めに教室に入るんだけど、今日は青柳くんが勉強している姿が目に入る。
珍しいな、なんて感想を抱きつつ席に座ろうと椅子を引く。
その時青柳くんに声をかけられて言われたのがさっきの言葉だ。
「うん、大丈夫だよ。」
初めて声をかけてもらえた!
その嬉しさから私はウキウキで青柳くんの席に近づく。
「何か用事?」
例え先生からの伝言だろうと、青柳くんとこうやって目を合わせて話す機会は滅多にない。
もしそうなら先生に感謝しないと!
なんて考えながら首を傾げたことで顔にかかった髪を耳にかける。
今日はいつもと違って髪を結ってないから落ちてきてしまったのだ。
ほんのり青柳くんの頬が色づいた気がした。
「っはい、あなたに今までの非礼を詫びたいと思いまして……」
えっと、つまり私に謝りたいってこと?
一体なんの……?
心当たりがなく、キョトンとした私に青柳くんは驚いてシャーペンを落とした。
「どうして不思議そうなんですか?私は今まで、あなたに酷い態度をとっていたじゃないですか!」
「酷い、態度?」
そんなものはとられた覚えもないし、私は青柳くんに謝ってもらうようなことは何もされてないはずだ。
なんのことだろうと更に首を傾げると、青柳くんは後悔するように目を伏せて口を開く。
「必要以上に突っかかって、迷惑をかけてしまったことについてです。」
「あ、あー……私は気にしてないよ?」
確かにそんなこともあったような?
「あなたが気にしてなくても、私が謝罪しないと気が済まないんです。私の至らなさで冷たい態度を取ってしまい、すみませんでした。」
ペコリと深く頭を下げられる。
「そ、そんなことっ!謝ってもらうほどのことじゃないし、私もうるさくしちゃったから……。それに青柳くんは立派な人だよ?全然至らなくなんてないと思う!」
至らなさ……というのはイマイチピンとこないが、私にも非があるわけだし、そんなに真剣に謝られると返って申し訳なくなってしまう。
「ふっ、ありがとうございます。その……言い訳にもなりませんが、私の話を聞いていただけませんか?」
「青柳くんの、お話……?」
なにそれ、すごく気になる。
というか、笑った顔……かわいい!
普段がムッと口を結んでるから大人っぽく見えるけど、笑うと年相応で、なんだか親近感が湧く。
「はい。被害者のあなたは知っておくべきかと思いまして。」
被害者って……。
そんなこと思ってないよと首を振ろうとして止める。
「被害を受けたとは思ってないけど、お話は是非聞きたいです!」
つい前のめりになっていってしまった。
慌てて元の姿勢に戻す私を見て、青柳くんは柔らかく目を細めた。
「入試の時、私はあなたと出会いました。」
「覚えてますか?」と聞かれて、私は必死に記憶を掘り起こした。
入試の日……うーん。
「こうしたらわかりますか?」
青柳くんは前髪をくしゃっとして、両端に分ける。
いわゆるセンターパートにしたわけだ。
あっ、あー!
その髪型、見覚えがある!
「やっと、思い出していただけましたね。試験の時は邪魔なので前髪を避けていたんですよ。」
そうだったんだ……。
入試の時、私はとある男の子に声をかけた。
鞄の中を見ながら顔を真っ青にしていて、心配になったからだ。
話しかけると、どうやら筆記用具を忘れてしまったとのこと。
私は予備で2つ消しゴムとシャーペンを持っていたこともあり、その子に貸すことを決めた。
……とそんなことがあったんだけど、まさかあの時の男の子が青柳くんだったなんて!
「よかった!青柳くんも受かってたんだね!」
試験の時、あれだけのイレギュラーがあったのに受かってしまうなんて、さすが青柳くんだ。
「それはこっちの台詞です。……私はてっきり、私のせいであなたが落ちてしまったとばかり……」
「心配させちゃってたんだね。この通り、ちゃんと受かりました!」
Vサインを作って見せると、青柳くんは「あなたって人は……」と困ったように笑った。
だけど、心なしか嬉しそうだ。
「あれ、でもそのことと私となんの関係が……?」
ふと疑問が浮かぶ。
青柳くんは私と入試で会った子が別人だと思っているようだった。
だから入試のことと入学してからのことは無関係じゃないかと思ったのだ。
「はい。その後のことですが……入学式の日、あなたの姿を探したのですが見つからず、私は私のせいで親切にしてくれた人を不合格にしてしまったと思い込んでいました。」
そっか、私が変装じみたことをしてたから!
それで青柳くんは気づかなかったんだ。
「首席が女子だと聞いた時、あなたじゃないかと心のどこかで期待してしまっていたんです。それが別人で……つい、八つ当たりをしてしまった、というのが経緯です。」
な、なるほど……。
つまり首席だったのが気に入らなかったわけではなく、助けてくれた人じゃなかったから冷たくしてしまった、と。
「……よ、よかったー!」
その理由を聞いてほっと息をつく。
てっきり私が何かやらかして青柳くんに嫌われてしまっているとばかり思っていたから。
私が理由じゃないのなら安心だ。
「よかったって……なんでですか?」
青柳くんが驚いたように私に問いかける。
「だって、私が何かしちゃったわけじゃないってわかったから。青柳くんに嫌われてなくて良かったなって。」
青柳くんは目を見開いた後ふっと笑みを浮かべた。
「あなたは、本当に……」
青柳くんが優しく私の頬に触れる。
指先から体温が伝わって、その暖かさが私の頬にも伝染する。
っ近い!
何かただことじゃない雰囲気を感じて、ゴクンと唾を飲む。
だけど、青柳くんの瞳から逃れることなんてできなかった。
「おはよう!……って、煌!何抜け駆けしてるんだ!?」
ガラガラッと音を立てて赤羽くんの元気の良い声が教室に響く。
「……煌、一体これはどうゆうこと?」
緑川くんは笑顔のままだったけど、その声には冷たさが混じっていて、妙な威圧感を覚える。
「どうもなにも、白雪さんと話させていただいただけですよ。」
青柳くんはパッと私から手を離して、緑川くんを横目で見る。
「ふーん?煌は話す時に相手の顔を触るんだ?」
それは知らなかったな、とニッコリと笑う。
「煌!お前昨日の約束をもう忘れたのか!?」
昨日の約束……は何かわからないけど、何故だか青柳くんが責められ始める。
「まさか1番奥手そうなこうちゃんがね〜」
ひょこっと緑川くんの後ろから口に手を開けた桃瀬くんが姿を現す。
「……約束は、守らないと」
さらに橙山くんまで現れて、クラスの全員が勢揃いする。
「み、みんな今日は早いんだね!」
ピリついた雰囲気をどうにかしようと、私は青柳くんを隠すように体を傾ける。
「あぁ、うん。朝練が早く終わったからね。」
私の疑問に緑川くんが答えてくれる。
そっか、みんながいつも時間ギリギリにきていたのは朝練があったからなんだ!
なるほどと頷くと、緑川くんが楽しそうに笑顔を浮かべた。
「白雪さん、知らなかったんだ?」
「……!いや、あの……」
前にもこんなことがあったような気がする。
あの時は緑川くんに興味があると言ったことで事なきを得たけど、2度も同じ手は使えない。
そうだよね、クラスメイトなのに朝練のこと知らなかったら悲しいよね。
それを緑川くんは揶揄う……という形で表現するというのは履修済み。
な、わけなんだけど……
緑川くんは笑顔のままなんだけど、目が笑っていない。
一体どうしたら!?
「はるちゃん、白雪ちゃんを怖がらせないの!」
「ね?」と桃瀬くんが私の腕をぎゅっと握って味方になってくれる。
「おい、玲央!お前まで……!」
それにいち早く反応したのは赤羽くんだった。
「白雪さん、怖かった……?」
緑川くんはショックを受けたようにか細い声で私に尋ねる。
「ううん!えっと、知らなくてごめんね。これからはもっと緑川くんのこと知れるように頑張るから!」
「教えてね?」と安心させるように笑顔で言うと、緑川くんの頬がボッと赤くなる。
「……うん、喜んで。」
ふいっと目を逸らされた後、顔を隠すように口元を手で覆っている。
「えー、白雪ちゃん!はるちゃんだけじゃなくて僕のこともたくさん知って!僕はね、朝は美術室で絵の練習してるから遅いんだ〜。」
「そうだったんだ!うん、私も桃瀬くんのことたくさん知りたい。」
そう言うと、桃瀬くんは感動したように目をうるうるさせた。
「あっ、でも。白雪ちゃんのことも教えてね!」
「……うん。」
私のこと、か……。
それは……
「……無理にとは、言わないけど。」
私が暗くなったせいか、気を使わせてしまう。
他のみんなも心配して私のことを見ていた。
それで慌てて笑顔を作る。
「無理なんて、そんな……!」
そんなことは、ない。
そう言おうとして、言い淀む。
昔のことを知られてみんなが離れてしまったら……。
そう思うとどうしても声が出なかった。
「そーいや、白雪は今日眼鏡してないんだな。」
赤羽くんが場を盛り上げようと別の話題を振ってくれる。
「あっ、うん。壊れちゃったから……」
伊達眼鏡でレンズに度が入ってないとはいえ、高価なものであることに変わりはない。
決して学生には手の届かない代物なのだ。
今は叔母夫婦にお世話になっている身。
頼めるはずもなかった。
「……変、かな?」
もしかしたら今まで眼鏡をかけていたから違和感があるのかも。
そう思って聞くと、
「そんなことない!」
と全員の声が重なった。
「ふふっ、良かった。」
それがおもしろくてつい笑ってしまうと、みんなは安心したようにほっと息をついていた。
やっぱり、心配かけちゃってたみたい。
私は心配させてしまったことを申し訳なく思いながらも、仲間に恵まれたことを少し嬉しく思ったのだった。
……まだ、人目を克服なんてできてない。
だけど、この人達となら……
窓から太陽が差し込んだ。
私は、前に進める気がする。
学校に着いて早々、青柳くんに声をかけられた。
いつもは私が1番初めに教室に入るんだけど、今日は青柳くんが勉強している姿が目に入る。
珍しいな、なんて感想を抱きつつ席に座ろうと椅子を引く。
その時青柳くんに声をかけられて言われたのがさっきの言葉だ。
「うん、大丈夫だよ。」
初めて声をかけてもらえた!
その嬉しさから私はウキウキで青柳くんの席に近づく。
「何か用事?」
例え先生からの伝言だろうと、青柳くんとこうやって目を合わせて話す機会は滅多にない。
もしそうなら先生に感謝しないと!
なんて考えながら首を傾げたことで顔にかかった髪を耳にかける。
今日はいつもと違って髪を結ってないから落ちてきてしまったのだ。
ほんのり青柳くんの頬が色づいた気がした。
「っはい、あなたに今までの非礼を詫びたいと思いまして……」
えっと、つまり私に謝りたいってこと?
一体なんの……?
心当たりがなく、キョトンとした私に青柳くんは驚いてシャーペンを落とした。
「どうして不思議そうなんですか?私は今まで、あなたに酷い態度をとっていたじゃないですか!」
「酷い、態度?」
そんなものはとられた覚えもないし、私は青柳くんに謝ってもらうようなことは何もされてないはずだ。
なんのことだろうと更に首を傾げると、青柳くんは後悔するように目を伏せて口を開く。
「必要以上に突っかかって、迷惑をかけてしまったことについてです。」
「あ、あー……私は気にしてないよ?」
確かにそんなこともあったような?
「あなたが気にしてなくても、私が謝罪しないと気が済まないんです。私の至らなさで冷たい態度を取ってしまい、すみませんでした。」
ペコリと深く頭を下げられる。
「そ、そんなことっ!謝ってもらうほどのことじゃないし、私もうるさくしちゃったから……。それに青柳くんは立派な人だよ?全然至らなくなんてないと思う!」
至らなさ……というのはイマイチピンとこないが、私にも非があるわけだし、そんなに真剣に謝られると返って申し訳なくなってしまう。
「ふっ、ありがとうございます。その……言い訳にもなりませんが、私の話を聞いていただけませんか?」
「青柳くんの、お話……?」
なにそれ、すごく気になる。
というか、笑った顔……かわいい!
普段がムッと口を結んでるから大人っぽく見えるけど、笑うと年相応で、なんだか親近感が湧く。
「はい。被害者のあなたは知っておくべきかと思いまして。」
被害者って……。
そんなこと思ってないよと首を振ろうとして止める。
「被害を受けたとは思ってないけど、お話は是非聞きたいです!」
つい前のめりになっていってしまった。
慌てて元の姿勢に戻す私を見て、青柳くんは柔らかく目を細めた。
「入試の時、私はあなたと出会いました。」
「覚えてますか?」と聞かれて、私は必死に記憶を掘り起こした。
入試の日……うーん。
「こうしたらわかりますか?」
青柳くんは前髪をくしゃっとして、両端に分ける。
いわゆるセンターパートにしたわけだ。
あっ、あー!
その髪型、見覚えがある!
「やっと、思い出していただけましたね。試験の時は邪魔なので前髪を避けていたんですよ。」
そうだったんだ……。
入試の時、私はとある男の子に声をかけた。
鞄の中を見ながら顔を真っ青にしていて、心配になったからだ。
話しかけると、どうやら筆記用具を忘れてしまったとのこと。
私は予備で2つ消しゴムとシャーペンを持っていたこともあり、その子に貸すことを決めた。
……とそんなことがあったんだけど、まさかあの時の男の子が青柳くんだったなんて!
「よかった!青柳くんも受かってたんだね!」
試験の時、あれだけのイレギュラーがあったのに受かってしまうなんて、さすが青柳くんだ。
「それはこっちの台詞です。……私はてっきり、私のせいであなたが落ちてしまったとばかり……」
「心配させちゃってたんだね。この通り、ちゃんと受かりました!」
Vサインを作って見せると、青柳くんは「あなたって人は……」と困ったように笑った。
だけど、心なしか嬉しそうだ。
「あれ、でもそのことと私となんの関係が……?」
ふと疑問が浮かぶ。
青柳くんは私と入試で会った子が別人だと思っているようだった。
だから入試のことと入学してからのことは無関係じゃないかと思ったのだ。
「はい。その後のことですが……入学式の日、あなたの姿を探したのですが見つからず、私は私のせいで親切にしてくれた人を不合格にしてしまったと思い込んでいました。」
そっか、私が変装じみたことをしてたから!
それで青柳くんは気づかなかったんだ。
「首席が女子だと聞いた時、あなたじゃないかと心のどこかで期待してしまっていたんです。それが別人で……つい、八つ当たりをしてしまった、というのが経緯です。」
な、なるほど……。
つまり首席だったのが気に入らなかったわけではなく、助けてくれた人じゃなかったから冷たくしてしまった、と。
「……よ、よかったー!」
その理由を聞いてほっと息をつく。
てっきり私が何かやらかして青柳くんに嫌われてしまっているとばかり思っていたから。
私が理由じゃないのなら安心だ。
「よかったって……なんでですか?」
青柳くんが驚いたように私に問いかける。
「だって、私が何かしちゃったわけじゃないってわかったから。青柳くんに嫌われてなくて良かったなって。」
青柳くんは目を見開いた後ふっと笑みを浮かべた。
「あなたは、本当に……」
青柳くんが優しく私の頬に触れる。
指先から体温が伝わって、その暖かさが私の頬にも伝染する。
っ近い!
何かただことじゃない雰囲気を感じて、ゴクンと唾を飲む。
だけど、青柳くんの瞳から逃れることなんてできなかった。
「おはよう!……って、煌!何抜け駆けしてるんだ!?」
ガラガラッと音を立てて赤羽くんの元気の良い声が教室に響く。
「……煌、一体これはどうゆうこと?」
緑川くんは笑顔のままだったけど、その声には冷たさが混じっていて、妙な威圧感を覚える。
「どうもなにも、白雪さんと話させていただいただけですよ。」
青柳くんはパッと私から手を離して、緑川くんを横目で見る。
「ふーん?煌は話す時に相手の顔を触るんだ?」
それは知らなかったな、とニッコリと笑う。
「煌!お前昨日の約束をもう忘れたのか!?」
昨日の約束……は何かわからないけど、何故だか青柳くんが責められ始める。
「まさか1番奥手そうなこうちゃんがね〜」
ひょこっと緑川くんの後ろから口に手を開けた桃瀬くんが姿を現す。
「……約束は、守らないと」
さらに橙山くんまで現れて、クラスの全員が勢揃いする。
「み、みんな今日は早いんだね!」
ピリついた雰囲気をどうにかしようと、私は青柳くんを隠すように体を傾ける。
「あぁ、うん。朝練が早く終わったからね。」
私の疑問に緑川くんが答えてくれる。
そっか、みんながいつも時間ギリギリにきていたのは朝練があったからなんだ!
なるほどと頷くと、緑川くんが楽しそうに笑顔を浮かべた。
「白雪さん、知らなかったんだ?」
「……!いや、あの……」
前にもこんなことがあったような気がする。
あの時は緑川くんに興味があると言ったことで事なきを得たけど、2度も同じ手は使えない。
そうだよね、クラスメイトなのに朝練のこと知らなかったら悲しいよね。
それを緑川くんは揶揄う……という形で表現するというのは履修済み。
な、わけなんだけど……
緑川くんは笑顔のままなんだけど、目が笑っていない。
一体どうしたら!?
「はるちゃん、白雪ちゃんを怖がらせないの!」
「ね?」と桃瀬くんが私の腕をぎゅっと握って味方になってくれる。
「おい、玲央!お前まで……!」
それにいち早く反応したのは赤羽くんだった。
「白雪さん、怖かった……?」
緑川くんはショックを受けたようにか細い声で私に尋ねる。
「ううん!えっと、知らなくてごめんね。これからはもっと緑川くんのこと知れるように頑張るから!」
「教えてね?」と安心させるように笑顔で言うと、緑川くんの頬がボッと赤くなる。
「……うん、喜んで。」
ふいっと目を逸らされた後、顔を隠すように口元を手で覆っている。
「えー、白雪ちゃん!はるちゃんだけじゃなくて僕のこともたくさん知って!僕はね、朝は美術室で絵の練習してるから遅いんだ〜。」
「そうだったんだ!うん、私も桃瀬くんのことたくさん知りたい。」
そう言うと、桃瀬くんは感動したように目をうるうるさせた。
「あっ、でも。白雪ちゃんのことも教えてね!」
「……うん。」
私のこと、か……。
それは……
「……無理にとは、言わないけど。」
私が暗くなったせいか、気を使わせてしまう。
他のみんなも心配して私のことを見ていた。
それで慌てて笑顔を作る。
「無理なんて、そんな……!」
そんなことは、ない。
そう言おうとして、言い淀む。
昔のことを知られてみんなが離れてしまったら……。
そう思うとどうしても声が出なかった。
「そーいや、白雪は今日眼鏡してないんだな。」
赤羽くんが場を盛り上げようと別の話題を振ってくれる。
「あっ、うん。壊れちゃったから……」
伊達眼鏡でレンズに度が入ってないとはいえ、高価なものであることに変わりはない。
決して学生には手の届かない代物なのだ。
今は叔母夫婦にお世話になっている身。
頼めるはずもなかった。
「……変、かな?」
もしかしたら今まで眼鏡をかけていたから違和感があるのかも。
そう思って聞くと、
「そんなことない!」
と全員の声が重なった。
「ふふっ、良かった。」
それがおもしろくてつい笑ってしまうと、みんなは安心したようにほっと息をついていた。
やっぱり、心配かけちゃってたみたい。
私は心配させてしまったことを申し訳なく思いながらも、仲間に恵まれたことを少し嬉しく思ったのだった。
……まだ、人目を克服なんてできてない。
だけど、この人達となら……
窓から太陽が差し込んだ。
私は、前に進める気がする。