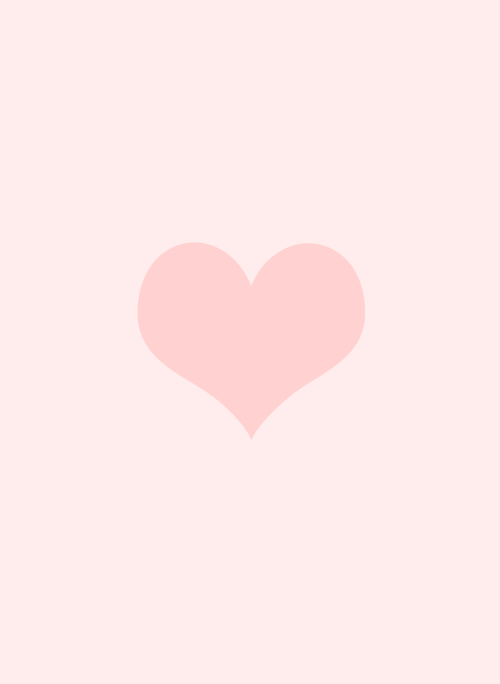初恋の距離~ゼロになる日
披露宴会場は、春の花々の香りとグラスが触れ合う音に満ちていた。
円卓に灯されたキャンドルが、白いクロスに小さな光の輪を落とす。
新郎新婦席に並ぶと、司会の合図で大きな拍手が起こり、二人は軽く会釈した。
「緊張してる?」
囁く悠真の横顔は、式のときより少しだけ砕けている。
「少しだけ。……でも、あなたが隣にいるので」
「それはいい答えだ」
ワイングラスの影が、テーブルの上でふたつ重なる。
友人代表のスピーチが続き、笑いと涙が交互に会場を揺らした。
ケーキ入刀の直前、司会が唐突に言う。
「ここで、お二人の特別な習慣“心ならし”の最終回を、皆さまの前でちょっとだけ――」
会場がざわめき、拍手が起こる。
美琴は思わず悠真を見る。彼は肩をすくめ、マイクを受け取った。
「毎週十五分。互いに三つ、逃げずに言葉にする――そう決めてから、僕らは少しずつ歩けるようになりました」
低い声が柔らかく拡がる。
「今日が最後というわけじゃない。これからも続けますが……せっかくなので、ひとつだけ公開で」
司会が嬉々として頷く。
「では“最後の一問”。新郎から新婦へ、お願いします」
マイクが渡され、悠真は美琴の方へ身体を向けた。
「――質問。君は今、この場で“無理に笑って”いないか」
会場から小さな笑いが漏れる。
美琴もふっと笑みを深くした。
「いいえ。自然に笑っています。……あなたが隣にいるから」
「模範解答すぎて、減点できないな」
拍手が起きる。
「では逆に、僕からの回答も。今日ここで、僕は“君といると安心する”。これは過去形にも未来形にもならない、現在形の宣言です」
その言い切りに、会場の温度が一段上がった。
ケーキ入刀。白いナイフに手を添えると、指輪が同じ角度で光った。
ふたりの手が重なった瞬間、長く続いた“距離の物語”が静かに幕を引き、かわりに“寄り添う日常”の譜面が開かれていくのを、美琴ははっきり感じた。
中座のあと、色を抑えた淡ローズのドレスで再入場。
各テーブルを回り、ゲスト一人ひとりと目を合わせるたび、祝福の言葉が胸に積もっていく。
祖母の席で立ち止まり、手を握る。
「よかったねえ。あんた、ようやく“真ん中”に立てた」
「真ん中?」
「ずっと端っこに立つ子だったから。……今日のあんたは、ちゃんと真ん中にいる」
胸の奥が、ゆっくり温かく満ちる。
ファーストダンスの曲が流れる。
ほんの短いステップ。
悠真の掌が背中にふれると、緊張が解けて、身体が音楽へ自然にゆだねられた。
「踊れる?」
「ええ。あなたとなら」
旋回する視界の中で、彼の瞳だけはぶれない。
「三ヶ月延期しても、君は逃げなかった。……誇りに思う」
「あなたが“離れない”と言ったから。――あれが、私の地面でした」
言葉が、音楽に溶けていく。
ブーケトス、キャンドルサービス、写真撮影――幸せの儀式が次々に過ぎていく。
終盤、ふたりのメッセージの時間。
美琴はマイクを握り、深呼吸をしてから、会場を見渡した。
「――私は、人前に出ると上手に笑えない子どもでした。
けれど、今日、たくさんの方に見守られながら、自然に笑えています。
それは、隣にいてくれる人が“安心”をくれるからです。
怖いときも、不安なときも、逃げずに言葉にする。
これから先、弱い日があっても、私たちは“心ならし”で歩いてゆきます。
どうか、その歩みを見守ってください」
言い終えると、会場にやわらかな拍手が広がった。
涙ぐむ母の姿が見えて、胸の奥がまた一度ふくらむ。
最後の新郎挨拶。
悠真は短く礼をし、まっすぐに言った。
「互いの家に感謝します。友人たちにも。
でも何より、彼女に。
軽口一つで傷つけ、誤解を長く抱かせてしまった。
だから、ここで訂正します――“君といると疲れない”。
“君といると、安心する”。
以上です」
潔い言葉の尾に、すこし照れた笑いが乗り、会場が温かな笑い声と拍手で満ちた。
披露宴がお開きになるころ、春の夜風がホテルのエントランスにやさしく流れ込んでいた。
見送る列の最後に、宮村が立っていた。
「おめでとう。――いい笑顔だね」
「ありがとう、宮村さん」
彼は軽く手を上げ、さわやかに身を引く。
嫉妬の棘を抜いた記憶が、風に触れてしずかに遠ざかった。
夜景のきらめくスカイラウンジで、短い休憩。
窓の向こう、街が星座みたいに瞬く。
「……終わったね」
「いや、始まった」
即答する悠真に、美琴は笑った。
「最初の“心ならし”、もうしますか?」
「今?」
「十五分だけ」
「いいだろう。質問、どうぞ」
「これから先、喧嘩した夜はどうしますか」
「結論が出なくても、同じベッドで寝る」
「なぜですか」
「距離が空くと、俺が余計な軽口を言う」
「……合理的な理由ですね」
「君は?」
「質問。明日の朝、最初に言ってほしい言葉は?」
「“おはよう。愛してる”」
「――満点です」
二人の笑い声が、夜景に溶ける。
ホテルを出ると、春の夜の匂いが濃くなっていた。
エントランスの階段を降りる前に、美琴は小さく立ち止まる。
「ねえ、悠真」
「うん」
「言わせてください。……“距離を測る婚約者”は、今日でおしまいです」
「同意する。これからは、“距離を測らない夫婦”だ」
指先が触れ、自然に絡む。
指輪の感触は、もう冷たくなかった。
車に乗り込むと、運転席からの低い振動が、初めて会った日の緊張を遠い記憶に変えていく。
「家に着くまでに、もう一問」
「どうぞ」
「十年後、私が不安になったら?」
「同じことを言う。“無傷は約束しない。治癒を約束する”。それと――」
「それと?」
「“離さない”」
窓の外、街路樹の若葉が風に揺れた。
胸の奥で、現在形の言葉が静かに根を下ろす。
やがて車は夜の街を抜け、二人の家へ。
玄関灯が灯り、白い花の香りが迎える。
ドアが閉まる音が、世界の音をやわらかく遠ざけた。
美琴は振り返り、微笑む。
「ただいま」
「おかえり」
最短の会話に、これまでの長い道のりが凝縮される。
初恋と現在形が、同じ線の上で重なる。
距離は、もう測らなくていい。
今、ここで――ゼロだ。