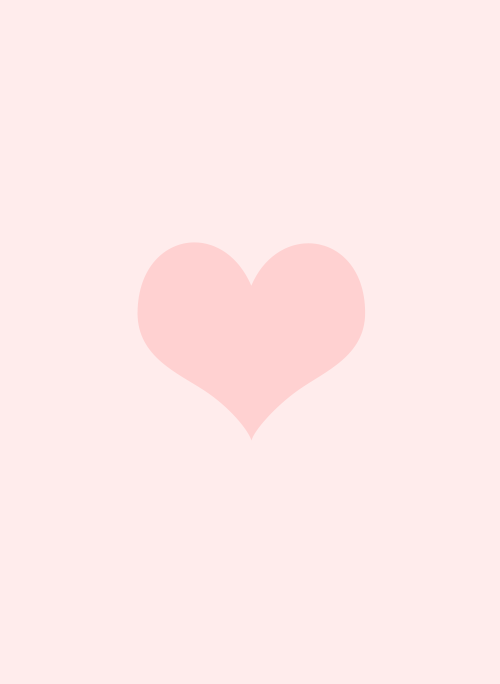真夜中の妖精さん
年下の彼 完
その考えは甘かった。
「佐奈! 家出来た!」
今現在、一学は佐奈の部屋でゲームに興じている。ブロックを組み立てていろいろな建築をするゲームらしい。
あれから三日、終業時刻を狙って連絡してきた一学により、お家で夕飯を食べることになってしまった。お腹いっぱいの一学は帰宅することなくゲームを始めたということである。
──流されちゃってるなぁ。
それもこれも、一学の顔が良いのがいけない。はっきり言って佐奈の好みドストライクなのだ。
「一学、そろそろ帰る時間じゃない?」
時計は二十時半を指している。一学に伝えると、見えない耳がしゅんと垂れた。
「時間、終わり?」
「うん、終わり」
たどたどしい日本語で伝えてくるのを喜ばしく思いながらも時間はきっちり守ってもらう。
しょんぼりしながら帰っていく背中を見送る。なんとなく窓越しにマンションのエントランスから出る一学を眺めていたら、外に怪しい人影を発見した。暗がりで男性か女性かも分からない。
「不審者だったらどうしよう」
不安になり一学に連絡をしようとスマートフォンを手に取ったところで、人影が走って逃げていった。
とりあえず凶器を持った犯罪者ではないことに安心する。念のため注意を促すメッセージを送っておいた。
「なにこれ……」
二日後、帰宅中の電車の中で何気なくスマートフォンをいじっていたら、とんでもないネットニュースが目に飛び込んできた。
遠目に撮られた一学の写真と「若手俳優、日本で熱愛か!?」の文字。佐奈は体が冷えていくのを感じた。
「うそ、あの不審者って一学を張ってたカメラマンだったの!?」
これは大変まずいことになった。せっかく俳優として成功しているのに、自分の存在があるために活動できなくなってしまうかもしれない。しかも、自分と一学はそういう関係ではないのに。
「とにかく、私のところにはもう来ないでって伝えなきゃ」
急いでメッセージを送る。帰宅して一時間経っても既読にはならなかった。おそらく仕事中なのだろう。芸能界に定時は無い。
気持ちを落ち着けるために夕食を食べる。テレビはつけられなかった。食器を片づけた後もずっとそわそわしている。スマートフォンが鳴った。電話だ。
「はい」
『いやだ』
一学だ。彼のたった一言に心が揺らぐ。
「だめだよ。ニュースになってる」
『佐奈に会えないと、仕事もできない』
「一学……」
佐奈は深呼吸をしてから、一学に事の重大さを分かりやすいよう彼の母国語で説明した。
『今、私たちは勘違いされているの。恋人同士だって。それだと仕事に支障をきたしてしまうでしょう? だから』
『いいよ』
「えっ」
一学の返事に、佐奈は目を丸くさせた。
ピンポン。
それと同時にインターフォンが鳴る。画面に映ったのは電話中の彼だった。慌ててドアを開ける。一学が佐奈の手を取って言った。
『いいよ。僕は佐奈が好きだ。佐奈と一緒なら、たくさんのことを乗り越えられる。仕事だって、うちの事務所恋愛NGではないから気にしないで』
至近距離で熱烈な告白を受けた。
出会ってまだ一週間、こんなことになるとは夢にも思わなかった。
どうしよう。
顔が熱い。
迷っているはずなのに、すでに答えは出ていた。
『迷惑かけるかもよ。あと、年上だし』
『僕、年上のお姉さん大好き。それに、年上でも、もしも年下だったとしても、僕は佐奈を選ぶよ』
『……もう、これ以上嬉しいこと言われたら一学の顔見られなくなっちゃうよ』
『あは。じゃあ、OKってこと?』
弾けるような笑顔で言われ、佐奈は少し俯きがちに頷いた。
『うん。よろしくお願いします』
『やったぁ! すぐマネージャーに知らせなきゃ!』
『あ、いちおう世間には内緒にしておいてね』
『ええ、そうなの? 残念だなぁ』
そう言う一学の顔は少年のように明るかった。きっと、いつか佐奈のことが完全にバレた時が来たら、彼は隠すことなく発表するに違いない。それが怖くもあり、嬉しくもあった。
──一夜限りの出会いだと思ったのに。
佐奈はぎゅうぎゅうに抱きしめられながら、百八十度変わるであろうこれからの生活を考えた。
了
「佐奈! 家出来た!」
今現在、一学は佐奈の部屋でゲームに興じている。ブロックを組み立てていろいろな建築をするゲームらしい。
あれから三日、終業時刻を狙って連絡してきた一学により、お家で夕飯を食べることになってしまった。お腹いっぱいの一学は帰宅することなくゲームを始めたということである。
──流されちゃってるなぁ。
それもこれも、一学の顔が良いのがいけない。はっきり言って佐奈の好みドストライクなのだ。
「一学、そろそろ帰る時間じゃない?」
時計は二十時半を指している。一学に伝えると、見えない耳がしゅんと垂れた。
「時間、終わり?」
「うん、終わり」
たどたどしい日本語で伝えてくるのを喜ばしく思いながらも時間はきっちり守ってもらう。
しょんぼりしながら帰っていく背中を見送る。なんとなく窓越しにマンションのエントランスから出る一学を眺めていたら、外に怪しい人影を発見した。暗がりで男性か女性かも分からない。
「不審者だったらどうしよう」
不安になり一学に連絡をしようとスマートフォンを手に取ったところで、人影が走って逃げていった。
とりあえず凶器を持った犯罪者ではないことに安心する。念のため注意を促すメッセージを送っておいた。
「なにこれ……」
二日後、帰宅中の電車の中で何気なくスマートフォンをいじっていたら、とんでもないネットニュースが目に飛び込んできた。
遠目に撮られた一学の写真と「若手俳優、日本で熱愛か!?」の文字。佐奈は体が冷えていくのを感じた。
「うそ、あの不審者って一学を張ってたカメラマンだったの!?」
これは大変まずいことになった。せっかく俳優として成功しているのに、自分の存在があるために活動できなくなってしまうかもしれない。しかも、自分と一学はそういう関係ではないのに。
「とにかく、私のところにはもう来ないでって伝えなきゃ」
急いでメッセージを送る。帰宅して一時間経っても既読にはならなかった。おそらく仕事中なのだろう。芸能界に定時は無い。
気持ちを落ち着けるために夕食を食べる。テレビはつけられなかった。食器を片づけた後もずっとそわそわしている。スマートフォンが鳴った。電話だ。
「はい」
『いやだ』
一学だ。彼のたった一言に心が揺らぐ。
「だめだよ。ニュースになってる」
『佐奈に会えないと、仕事もできない』
「一学……」
佐奈は深呼吸をしてから、一学に事の重大さを分かりやすいよう彼の母国語で説明した。
『今、私たちは勘違いされているの。恋人同士だって。それだと仕事に支障をきたしてしまうでしょう? だから』
『いいよ』
「えっ」
一学の返事に、佐奈は目を丸くさせた。
ピンポン。
それと同時にインターフォンが鳴る。画面に映ったのは電話中の彼だった。慌ててドアを開ける。一学が佐奈の手を取って言った。
『いいよ。僕は佐奈が好きだ。佐奈と一緒なら、たくさんのことを乗り越えられる。仕事だって、うちの事務所恋愛NGではないから気にしないで』
至近距離で熱烈な告白を受けた。
出会ってまだ一週間、こんなことになるとは夢にも思わなかった。
どうしよう。
顔が熱い。
迷っているはずなのに、すでに答えは出ていた。
『迷惑かけるかもよ。あと、年上だし』
『僕、年上のお姉さん大好き。それに、年上でも、もしも年下だったとしても、僕は佐奈を選ぶよ』
『……もう、これ以上嬉しいこと言われたら一学の顔見られなくなっちゃうよ』
『あは。じゃあ、OKってこと?』
弾けるような笑顔で言われ、佐奈は少し俯きがちに頷いた。
『うん。よろしくお願いします』
『やったぁ! すぐマネージャーに知らせなきゃ!』
『あ、いちおう世間には内緒にしておいてね』
『ええ、そうなの? 残念だなぁ』
そう言う一学の顔は少年のように明るかった。きっと、いつか佐奈のことが完全にバレた時が来たら、彼は隠すことなく発表するに違いない。それが怖くもあり、嬉しくもあった。
──一夜限りの出会いだと思ったのに。
佐奈はぎゅうぎゅうに抱きしめられながら、百八十度変わるであろうこれからの生活を考えた。
了