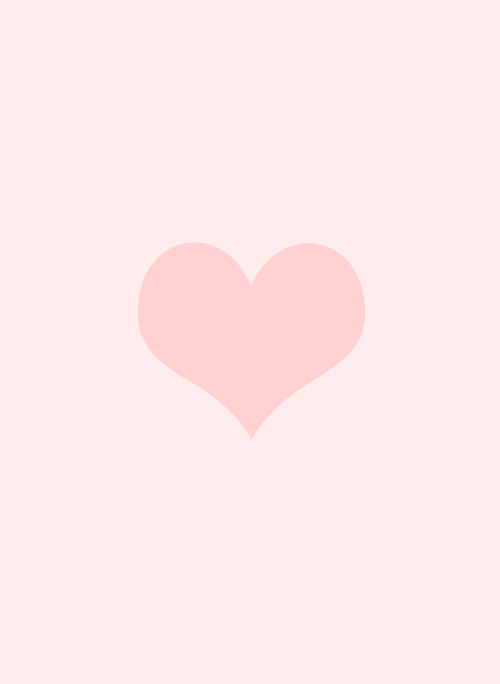女装メイドの従者と、婚約破棄された悪役令嬢は、幸せな結末を目指します
第九十二話 二人との再会
ルネから連絡を受けた私達は慌てて伝書鳩をシヴァに送ったり、追加の護衛を頼んだりしたものだが、遠すぎて全くと言っていいほど間に合ってはいなかった。全ては終わった後で、シヴァからの折り返しの手紙が伝書鳩で届けられた時は肝を冷やしたものだ。
例の男と言うのはオスカー・ヴァルシュと言う。元王宮魔術師だった人間だ。そんな人間とシヴァが何故? と思いはしたが、ヴォルフガングとの繋がりを考えるとそういうこともあるかと納得した。
『オレは無事だ。証拠も手に入ったから、待っていてくれ』
何ともそっけない返事である。伝書鳩だから、そんなに大した内容が送れないのは当然だが。
この手紙を受け取ってから、ルネもお父様も一安心したのかいつも通りの状態に戻っていた。でも、私はそうはいかない。ただでさえシヴァがいなくて不安なのに、こんな事件が起こったら落ち着いてなんかいられない。かといって何ができるわけでもなく、ソワソワしながら待っているだけ。中間試験後の長期休暇があって本当に助かった。これでは落ち着いて授業なんて受けられないだろうから。
それから約一週間。中間試験後の休暇も終わり、明日から学園が始まるという長期休暇の最終日。シヴァは帰宅してきた。
今日到着するとの連絡を受け、朝から私はずっと玄関ホールでシヴァの帰りを待っていた。周囲には私に付き添っているバルバラ以外にも、手の空いている従者達が入れ代わり立ち代わり、私と共にシヴァの帰宅を今か今かと待ってくれていた。
「お嬢様、そんなに慌ててもシルヴィアは早く着いたりしませんよ」
苦笑いしながらバルバラが朝食代わりの軽食や飲み物を持ってきてくれる。もう今日は一日中ここから動かない覚悟だ。そうこうしている内に、時刻はお昼前になり、一台の馬車が走る音が聞こえてきた。
白砂が敷き詰められた広大な前庭を、車輪が規則正しく音を立てて進んでくる。モンリーズ公爵家の紋章が側面に描かれたその馬車は、さすがに長期の移動のためか乾いた泥や草の破片がこびりついていた。確実にシヴァの載っている馬車だと判断すると、私は玄関ホールに用意された椅子から立ち上がり馬車の止まるであろう場所まで小走りで近付いた。
馬車が正面玄関の車寄せに滑り込み、重々しい音を立てて停止する。玄関ホールから続く石造りのポーチ周辺には、手入れの行き届いた色とりどりのバラやゼラニウムが咲き乱れる花壇が広がっていたが、今はその華やかささえ目に入らない。
「お嬢様、危ないですよ。まずは落ち着いて」
バルバラに肩を掴まれて制止させられるまで、私は自分でドアを開ける気満々だった。御者がゆっくりと御者台から飛び降り、そんな私達に一礼する。姿勢を正すと、御者はドアの取っ手に手をかけた。
ドアが開いた瞬間、私はすぐに出てきた人物に飛びつく。
「シヴァ!」
ろくに確認もしていなかったが、それは間違いなくずっと待ち続けたシヴァだった。温かな体温に、布の多い女性服から感じるがっしりした体に温かな体温。一度離れてシヴァの様子を見ようとすると、目が合ったシヴァは空色の瞳を細めて微笑んでくれた。
「ただいま、リリー」
質素な紺のドレスに、所々シルバーグレイの髪が見え隠れする黒髪のウィッグは白いリボンが編み込まれ、後ろで一纏めにされていた。中性的なかおだちをしており、ぱっと見は普通の女性にしか見えない。
「お帰り、シヴァ。体調はどう? 大丈夫だった?」
オスカーとか言う男を想像しただけで、以前は体調を崩していたのだ。今回は大丈夫だったのかと心配でたまらない。キョロキョロとシヴァの体や顔色を見て回る私を見て、シヴァは苦笑いするとぎゅっとその両手で私の頬を挟んだ。黒い皮手袋ごしに、シヴァの体温が伝わってくる。
「ばーか、何ともねぇよ。そんなに心配するな」
笑いかける姿は確実にシヴァのものだ。ここまで来て、私はようやくじわじわとシヴァが帰宅してきたことが実感できた。
「何をイチャイチャしとるんだ。お前さんらは」
シヴァの後ろから声が聞こえる。シヴァと共にそちらを見ると、二メートルはありそうな巨体が馬車から降りてきた。降りた後も馬車の天井に手が届いてしまう大きな体に、濃い茶色の髪と無精髭。そこから覗く紫色の瞳は垂れ目になっていてなんとも愛嬌がある。
「……ヴォルフガング様⁉」
「証人の1人として呼ばれてな。しばらく滞在することになったんだ。よろしく頼むよ。モンリーズのお嬢様」
私の顔を見て彼は歯を出してにかっと笑う。
「ここで茶々を入れてくるとは、随分な態度だなヴォルフガング」
「じゃったらワシはいつ出て来ればいいんだ。このままだと、他のお嬢さんらとも再会を喜びあって、ワシはあのまま一時間は馬車の中で待機するような流れだったぞ?」
軽い言葉のやり取りも忘れない。相変わらずの二人だ。
私はバルバラの方へ向き直り、準備をするように目で合図した。さすがバルバラは意図を察したのか、他の従者達を押しのけて屋敷の中へと入っていく。
私は姿勢を正すと、ヴォルフガングへと向き直った。大柄な彼は通常よりもずっと上を向かなければ目を合わせることもできない。
「ようこそいらっしゃいました。モンリーズ家は貴方を歓迎しますわ。まずはちょうど良いのでこのまま昼食へ。食堂まで案内します」
綺麗にカーテシーを披露し、屋敷の中へと彼を招き入れる。顎髭を撫でつけながら、彼は感心したように微笑むと付いて来てくれた。
例の男と言うのはオスカー・ヴァルシュと言う。元王宮魔術師だった人間だ。そんな人間とシヴァが何故? と思いはしたが、ヴォルフガングとの繋がりを考えるとそういうこともあるかと納得した。
『オレは無事だ。証拠も手に入ったから、待っていてくれ』
何ともそっけない返事である。伝書鳩だから、そんなに大した内容が送れないのは当然だが。
この手紙を受け取ってから、ルネもお父様も一安心したのかいつも通りの状態に戻っていた。でも、私はそうはいかない。ただでさえシヴァがいなくて不安なのに、こんな事件が起こったら落ち着いてなんかいられない。かといって何ができるわけでもなく、ソワソワしながら待っているだけ。中間試験後の長期休暇があって本当に助かった。これでは落ち着いて授業なんて受けられないだろうから。
それから約一週間。中間試験後の休暇も終わり、明日から学園が始まるという長期休暇の最終日。シヴァは帰宅してきた。
今日到着するとの連絡を受け、朝から私はずっと玄関ホールでシヴァの帰りを待っていた。周囲には私に付き添っているバルバラ以外にも、手の空いている従者達が入れ代わり立ち代わり、私と共にシヴァの帰宅を今か今かと待ってくれていた。
「お嬢様、そんなに慌ててもシルヴィアは早く着いたりしませんよ」
苦笑いしながらバルバラが朝食代わりの軽食や飲み物を持ってきてくれる。もう今日は一日中ここから動かない覚悟だ。そうこうしている内に、時刻はお昼前になり、一台の馬車が走る音が聞こえてきた。
白砂が敷き詰められた広大な前庭を、車輪が規則正しく音を立てて進んでくる。モンリーズ公爵家の紋章が側面に描かれたその馬車は、さすがに長期の移動のためか乾いた泥や草の破片がこびりついていた。確実にシヴァの載っている馬車だと判断すると、私は玄関ホールに用意された椅子から立ち上がり馬車の止まるであろう場所まで小走りで近付いた。
馬車が正面玄関の車寄せに滑り込み、重々しい音を立てて停止する。玄関ホールから続く石造りのポーチ周辺には、手入れの行き届いた色とりどりのバラやゼラニウムが咲き乱れる花壇が広がっていたが、今はその華やかささえ目に入らない。
「お嬢様、危ないですよ。まずは落ち着いて」
バルバラに肩を掴まれて制止させられるまで、私は自分でドアを開ける気満々だった。御者がゆっくりと御者台から飛び降り、そんな私達に一礼する。姿勢を正すと、御者はドアの取っ手に手をかけた。
ドアが開いた瞬間、私はすぐに出てきた人物に飛びつく。
「シヴァ!」
ろくに確認もしていなかったが、それは間違いなくずっと待ち続けたシヴァだった。温かな体温に、布の多い女性服から感じるがっしりした体に温かな体温。一度離れてシヴァの様子を見ようとすると、目が合ったシヴァは空色の瞳を細めて微笑んでくれた。
「ただいま、リリー」
質素な紺のドレスに、所々シルバーグレイの髪が見え隠れする黒髪のウィッグは白いリボンが編み込まれ、後ろで一纏めにされていた。中性的なかおだちをしており、ぱっと見は普通の女性にしか見えない。
「お帰り、シヴァ。体調はどう? 大丈夫だった?」
オスカーとか言う男を想像しただけで、以前は体調を崩していたのだ。今回は大丈夫だったのかと心配でたまらない。キョロキョロとシヴァの体や顔色を見て回る私を見て、シヴァは苦笑いするとぎゅっとその両手で私の頬を挟んだ。黒い皮手袋ごしに、シヴァの体温が伝わってくる。
「ばーか、何ともねぇよ。そんなに心配するな」
笑いかける姿は確実にシヴァのものだ。ここまで来て、私はようやくじわじわとシヴァが帰宅してきたことが実感できた。
「何をイチャイチャしとるんだ。お前さんらは」
シヴァの後ろから声が聞こえる。シヴァと共にそちらを見ると、二メートルはありそうな巨体が馬車から降りてきた。降りた後も馬車の天井に手が届いてしまう大きな体に、濃い茶色の髪と無精髭。そこから覗く紫色の瞳は垂れ目になっていてなんとも愛嬌がある。
「……ヴォルフガング様⁉」
「証人の1人として呼ばれてな。しばらく滞在することになったんだ。よろしく頼むよ。モンリーズのお嬢様」
私の顔を見て彼は歯を出してにかっと笑う。
「ここで茶々を入れてくるとは、随分な態度だなヴォルフガング」
「じゃったらワシはいつ出て来ればいいんだ。このままだと、他のお嬢さんらとも再会を喜びあって、ワシはあのまま一時間は馬車の中で待機するような流れだったぞ?」
軽い言葉のやり取りも忘れない。相変わらずの二人だ。
私はバルバラの方へ向き直り、準備をするように目で合図した。さすがバルバラは意図を察したのか、他の従者達を押しのけて屋敷の中へと入っていく。
私は姿勢を正すと、ヴォルフガングへと向き直った。大柄な彼は通常よりもずっと上を向かなければ目を合わせることもできない。
「ようこそいらっしゃいました。モンリーズ家は貴方を歓迎しますわ。まずはちょうど良いのでこのまま昼食へ。食堂まで案内します」
綺麗にカーテシーを披露し、屋敷の中へと彼を招き入れる。顎髭を撫でつけながら、彼は感心したように微笑むと付いて来てくれた。