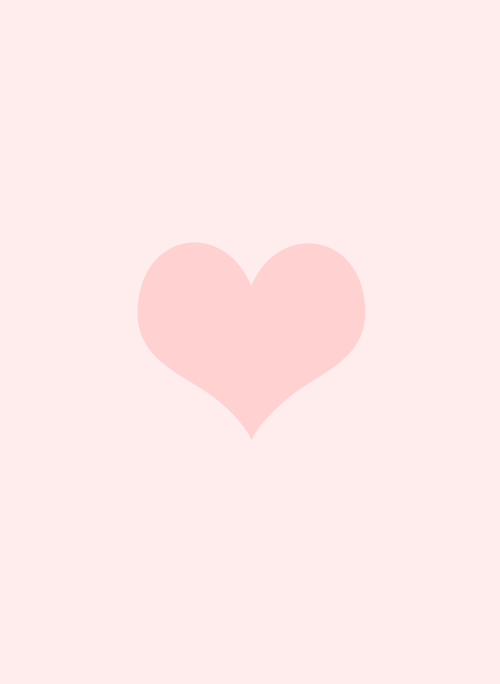ピュアホワイトクリスタルホライズンミッドナイトムーンジェイド~甘い毒と「ありがとう」から始まる魔導学院ライフ~
春の終わり、夕焼けが王都の屋根を淡い桃色に染めていたころ。
王立魔導学院の最上階にある星見の塔で、結唯はひとり、棚のほこりと戦っていた。
薄い灰色のローブの袖を肘までまくった結唯は、古びた魔導器の山をひとつひとつ持ち上げては、柔らかい布でこすっていく。ガラス窓の向こうでは、空を渡る飛竜のシルエットが、夕陽を切り裂くように滑っていった。
今日ここにいるのは、本来なら教師の助手がやるはずの仕事を、結唯が「わたし、手伝います」と言って引き受けたからだ。
掃除を頼まれた時、研究棟の廊下で書類の山をかかえてよろけた優真を見てしまった。あの、慌てて笑ってごまかそうとする顔が妙に気になって、そのまま立ち去ることができなかったのだ。
結唯は棚の一番下の段から、重そうな木箱を引きずり出す。箱の蓋には、見たことのない紋章が刻まれている。
「……重っ」
箱をずりずりと床に引き出した瞬間、かすかな鈴の音がした。
耳の奥で、ちりん、と透明な音が跳ねる。
結唯は動きを止め、息をひそめる。誰もいない塔の部屋に、その音だけが何度も反響した。
「……今の、なんだろ」
彼女が育った北方の領地では、「妙な音がしたら近づくな」と何度も言われてきた。けれど、その教えを守っていたら、ここでは何も始まらない。
追放同然に領地を出て、この王立魔導学院にやってきた時、彼女は心のどこかで決めたのだ。――怖くても、一歩だけ前に出てみる、と。
結唯は箱の留め金にそっと指をかける。冷たい金属が指先に吸い付いた。
ぱちん、と金具が外れる。
蓋を開けた瞬間、まぶしい光が周囲にあふれ出した。
「わ、わあっ……!」
箱の中に眠っていたのは、掌ほどの大きさの結晶だった。
真っ白な光を中心に、薄い翡翠色と夜のような群青が、水平線のような帯を描いてゆらめいている。結晶の表面には、星空を閉じ込めたみたいな銀の粒子が散っていた。
見ているだけで、胸の奥がじんわり温かくなる。けれど同時に、喉の奥がからからに渇いていくような、不思議な感覚もあった。
(……きれい。でも、ちょっとこわい)
結唯は目をそらせずに、そっと結晶に触れる。
指先に冷たさが移った瞬間、頭の中に、くぐもった声が流れ込んできた。
『――名称、確認。ピュアホワイトクリスタルホライズンミッドナイトムーンジェイド』
「……長い」
思わず、つっこみが口から漏れる。
その瞬間、結晶の中心で光がちかっ、と瞬いた。
結唯は慌てて手を引っ込めると、箱ごと抱え上げ、よろよろと立ち上がった。
(こんな変な……じゃなくて、すごい結晶、勝手に触ってて怒られたらどうしよう。でも、見つけちゃったし――)
迷った末に、結唯はその足で優真の研究室へ向かうことにした。
知らないことは、知っている人に聞く。それがいちばん早くて、いちばん確かだ。
星見の塔から続く狭い螺旋階段を、結唯は息を切らしながら駆け下りる。結晶の入った箱はずしりと重く、そのたびに中で光が揺れた。
◆
研究棟の一番奥、魔導理論研究室の扉は、夜になりかけた今もほのかな光を漏らしている。
結唯は片方の肩で箱を支えながら、片手でノックした。
「――どうぞ」
落ち着いた声が中から返ってくる。
結唯は深呼吸をひとつしてから、扉を押し開けた。
部屋の中には、紙束と本と魔導器が、これでもかというほど積み上がっている。その中心で、優真が机に向かってペンを走らせていた。
黒髪を後ろでまとめ、少し着崩したローブの胸元から、銀のペンダントがのぞいている。
「夕方の見回りかと思ったら……結唯さん?」
顔を上げた優真の目が丸くなる。
結唯はどたどたと机のそばまで走り寄ると、勢いよく箱を置いた。
「せ、先生! わたし『ピュアホワイトクリスタルホライズンミッドナイトムーンジェイド』を見つけました!」
勢い余って、最後の「ジェイド」が少し裏返った。
優真は一瞬、固まる。手に持っていたペンが、ぱたりと机に落ちた。
「……今、なんて?」
「えっと、その……ピュアホワイト……クリスタル……ホラ……」
もう一度言おうとして、見事につっかえる。
結唯は頬を赤くしながら、箱の蓋を開けてみせた。
ふわり、と部屋の中に光があふれる。
さっき塔で見たより、さらに強い輝きだ。
優真の瞳に、純白と翡翠色が映り込む。
さっきまで紙束と格闘していたはずの彼の表情から、疲れがすっと抜けていった。
「……本当に、あったのか」
小さな呟きが、結唯の耳に届く。
「先生、知ってるんですか?」
「名前だけはね。学院の創立記録に一度だけ出てくる、伝説級の結晶だよ。あまりにも長い名前だから、途中で写本係が書くのをやめたっていう、情けない逸話つきの」
優真は、困ったように笑いながらも、目は結晶から離さなかった。
そっと箱の中に手を伸ばし、結晶に触れる。
瞬間、室内の空気が甘く変わった。
草原に咲く白い花のような香りが、ふわりと鼻先をくすぐる。
胸の奥が、じんわり熱くなる。
(……甘い。けど、胸がぎゅっとする)
結唯は、自分の心臓が早鐘を打ち始めたのを感じながら、こっそり胸に手を当てた。
優真は低く息を吐き、結晶から指を離す。
「……危ない」
「危ない、んですか?」
「今、ほんの一瞬触っただけで、すごく幸せな気分になった。これは、感情に作用するタイプの魔導器だね。ありがたさを増幅するというか……甘い毒、かな」
「甘い毒……」
結唯は、その言葉を口の中で転がしてみた。
お菓子のように甘いのに、気づけば手放せなくなる。そんなイメージが浮かぶ。
「ありがとうって言われるのは、本来、いいことだ。でもこれに頼りすぎると、『感謝される快感』ばかり追いかけるようになってしまうかもしれない。人の心を、うまく利用する者がいたら――」
そこで優真は言葉を切り、結唯の方を見る。
「だからこそ、この結晶を見つけた君に、まず言っておかないとね」
彼はまっすぐに結唯を見つめ、わずかに口元をほころばせた。
「ありがとう、結唯さん。君が見つけてくれて、本当に助かった」
その言葉は、ピュアホワイトクリスタルホライズンミッドナイトムーンジェイドの力なんて関係なく、真っ直ぐに結唯の胸へと飛び込んできた。
喉の奥が熱くなる。
領地にいたころ、「厄災を呼ぶ子」と呼ばれていた時には、一度も向けられなかったまなざしだ。
(変な結晶を見つけたのに、怒られるどころか、ちゃんとお礼を言ってくれるんだ……)
結唯が俯きかけた時、箱の中の結晶が、ひときわ強く輝いた。
「わっ!」
白と翡翠と深い夜色が一度に弾け、部屋の中を満たす。
紙束の端がふわりと浮き、ペン立ての影が長く伸びる。
光の中で、結唯は一瞬だけ、見たことのない景色を垣間見た。
夜空に浮かぶ巨大な月。
翼の生えた馬が飛び交う、どこか遠い空。
その真ん中で、誰かと肩を並べて笑っている、自分。
その隣にいる横顔が、ほんの少しだけ優真に似ていた気がして、結唯は慌てて目をこする。
「今の、見えました?」
「少しだけね。未来の断片かもしれない。……結唯さん」
優真は結晶を見下ろしながら、真面目な顔つきになる。
「この結晶は、感謝と願いを糧にして、持ち主の『境遇』を変えると言われている。虐げられてきた者にこそ、よく効くらしい」
結唯の肩が、小さく震えた。
彼女の出自を、優真はうっかり口にしない。そういうところにも、彼の細やかさがにじむ。
「だけど、誰かを見返すためだけに使ったら、本当の意味での大逆転にはならないと思う。君が、君自身の幸せのために笑えるようになってこそ、この結晶は力を発揮するんじゃないかな」
「……わたしの、幸せ」
結唯は小さく復唱する。
領地を追われてここに来た日のことが、頭をよぎった。雨の中、ひとりで歩いた街道。泥にまみれた靴。
それでも諦めずに、この学院の門を叩いた自分。
あの日の震える指先が、今、結晶の光に照らされている。
「じゃあ――」
結唯は顔を上げ、結晶にそっと手を伸ばした。
「この子を悪い人に使わせないように、見張る役目を、わたしにください。誰かを傷つけるためじゃなくて、ちゃんと『ありがとう』が届く場所にだけ、力を使えるように」
優真の目が、大きく見開かれる。
驚いた後で、すぐに柔らかく笑った。
「君は、本当に人のために動くんだね」
「だって……この学院に来られたのも、わたしを拾ってくれた人たちのおかげだから。恩返ししたいんです。ちゃんと、ここで生きていけるように」
結唯の言葉に、結晶がまたひとつ、鈴の音を響かせた。
ちりん、と。
それは、どこかお祝いの鐘のような音だった。
「わかった。では、結唯さんを、この結晶の管理者候補に正式に任命するよ。もちろん、僕も一緒に研究させてもらう。君ひとりに、甘い毒の誘惑は背負わせられないからね」
「はいっ!」
結唯は思わず声を弾ませた。
その笑顔を見た瞬間、優真はふと視線をそらし、咳払いをひとつする。
「それに……」
「それに?」
「この名前を毎回ちゃんと言える人材は貴重だから」
「それは……がんばります!」
結唯が胸を張ると、優真は肩を揺らして笑った。
さっきまで部屋中に積もっていた疲労が、少しだけ薄くなっている気がする。
箱の中のピュアホワイトクリスタルホライズンミッドナイトムーンジェイドは、ふたりのやりとりに合わせるように、静かに瞬きを繰り返していた。
甘くてあたたかい、けれど気を抜けばどこまでも深く沈んでしまいそうな光。
それはたしかに、甘い毒に似ていた。
けれど、その毒に飲み込まれるか、それとも甘さを抱きしめて前へ進むかを決めるのは――
ここで、肩を並べて立つふたり自身だ。
追放された先の王立魔導学院で、結唯の物語はようやく動き出した。
その始まりを照らすのは、長い名前を持つひとつの結晶と、心からの「ありがとう」の光だった。
王立魔導学院の最上階にある星見の塔で、結唯はひとり、棚のほこりと戦っていた。
薄い灰色のローブの袖を肘までまくった結唯は、古びた魔導器の山をひとつひとつ持ち上げては、柔らかい布でこすっていく。ガラス窓の向こうでは、空を渡る飛竜のシルエットが、夕陽を切り裂くように滑っていった。
今日ここにいるのは、本来なら教師の助手がやるはずの仕事を、結唯が「わたし、手伝います」と言って引き受けたからだ。
掃除を頼まれた時、研究棟の廊下で書類の山をかかえてよろけた優真を見てしまった。あの、慌てて笑ってごまかそうとする顔が妙に気になって、そのまま立ち去ることができなかったのだ。
結唯は棚の一番下の段から、重そうな木箱を引きずり出す。箱の蓋には、見たことのない紋章が刻まれている。
「……重っ」
箱をずりずりと床に引き出した瞬間、かすかな鈴の音がした。
耳の奥で、ちりん、と透明な音が跳ねる。
結唯は動きを止め、息をひそめる。誰もいない塔の部屋に、その音だけが何度も反響した。
「……今の、なんだろ」
彼女が育った北方の領地では、「妙な音がしたら近づくな」と何度も言われてきた。けれど、その教えを守っていたら、ここでは何も始まらない。
追放同然に領地を出て、この王立魔導学院にやってきた時、彼女は心のどこかで決めたのだ。――怖くても、一歩だけ前に出てみる、と。
結唯は箱の留め金にそっと指をかける。冷たい金属が指先に吸い付いた。
ぱちん、と金具が外れる。
蓋を開けた瞬間、まぶしい光が周囲にあふれ出した。
「わ、わあっ……!」
箱の中に眠っていたのは、掌ほどの大きさの結晶だった。
真っ白な光を中心に、薄い翡翠色と夜のような群青が、水平線のような帯を描いてゆらめいている。結晶の表面には、星空を閉じ込めたみたいな銀の粒子が散っていた。
見ているだけで、胸の奥がじんわり温かくなる。けれど同時に、喉の奥がからからに渇いていくような、不思議な感覚もあった。
(……きれい。でも、ちょっとこわい)
結唯は目をそらせずに、そっと結晶に触れる。
指先に冷たさが移った瞬間、頭の中に、くぐもった声が流れ込んできた。
『――名称、確認。ピュアホワイトクリスタルホライズンミッドナイトムーンジェイド』
「……長い」
思わず、つっこみが口から漏れる。
その瞬間、結晶の中心で光がちかっ、と瞬いた。
結唯は慌てて手を引っ込めると、箱ごと抱え上げ、よろよろと立ち上がった。
(こんな変な……じゃなくて、すごい結晶、勝手に触ってて怒られたらどうしよう。でも、見つけちゃったし――)
迷った末に、結唯はその足で優真の研究室へ向かうことにした。
知らないことは、知っている人に聞く。それがいちばん早くて、いちばん確かだ。
星見の塔から続く狭い螺旋階段を、結唯は息を切らしながら駆け下りる。結晶の入った箱はずしりと重く、そのたびに中で光が揺れた。
◆
研究棟の一番奥、魔導理論研究室の扉は、夜になりかけた今もほのかな光を漏らしている。
結唯は片方の肩で箱を支えながら、片手でノックした。
「――どうぞ」
落ち着いた声が中から返ってくる。
結唯は深呼吸をひとつしてから、扉を押し開けた。
部屋の中には、紙束と本と魔導器が、これでもかというほど積み上がっている。その中心で、優真が机に向かってペンを走らせていた。
黒髪を後ろでまとめ、少し着崩したローブの胸元から、銀のペンダントがのぞいている。
「夕方の見回りかと思ったら……結唯さん?」
顔を上げた優真の目が丸くなる。
結唯はどたどたと机のそばまで走り寄ると、勢いよく箱を置いた。
「せ、先生! わたし『ピュアホワイトクリスタルホライズンミッドナイトムーンジェイド』を見つけました!」
勢い余って、最後の「ジェイド」が少し裏返った。
優真は一瞬、固まる。手に持っていたペンが、ぱたりと机に落ちた。
「……今、なんて?」
「えっと、その……ピュアホワイト……クリスタル……ホラ……」
もう一度言おうとして、見事につっかえる。
結唯は頬を赤くしながら、箱の蓋を開けてみせた。
ふわり、と部屋の中に光があふれる。
さっき塔で見たより、さらに強い輝きだ。
優真の瞳に、純白と翡翠色が映り込む。
さっきまで紙束と格闘していたはずの彼の表情から、疲れがすっと抜けていった。
「……本当に、あったのか」
小さな呟きが、結唯の耳に届く。
「先生、知ってるんですか?」
「名前だけはね。学院の創立記録に一度だけ出てくる、伝説級の結晶だよ。あまりにも長い名前だから、途中で写本係が書くのをやめたっていう、情けない逸話つきの」
優真は、困ったように笑いながらも、目は結晶から離さなかった。
そっと箱の中に手を伸ばし、結晶に触れる。
瞬間、室内の空気が甘く変わった。
草原に咲く白い花のような香りが、ふわりと鼻先をくすぐる。
胸の奥が、じんわり熱くなる。
(……甘い。けど、胸がぎゅっとする)
結唯は、自分の心臓が早鐘を打ち始めたのを感じながら、こっそり胸に手を当てた。
優真は低く息を吐き、結晶から指を離す。
「……危ない」
「危ない、んですか?」
「今、ほんの一瞬触っただけで、すごく幸せな気分になった。これは、感情に作用するタイプの魔導器だね。ありがたさを増幅するというか……甘い毒、かな」
「甘い毒……」
結唯は、その言葉を口の中で転がしてみた。
お菓子のように甘いのに、気づけば手放せなくなる。そんなイメージが浮かぶ。
「ありがとうって言われるのは、本来、いいことだ。でもこれに頼りすぎると、『感謝される快感』ばかり追いかけるようになってしまうかもしれない。人の心を、うまく利用する者がいたら――」
そこで優真は言葉を切り、結唯の方を見る。
「だからこそ、この結晶を見つけた君に、まず言っておかないとね」
彼はまっすぐに結唯を見つめ、わずかに口元をほころばせた。
「ありがとう、結唯さん。君が見つけてくれて、本当に助かった」
その言葉は、ピュアホワイトクリスタルホライズンミッドナイトムーンジェイドの力なんて関係なく、真っ直ぐに結唯の胸へと飛び込んできた。
喉の奥が熱くなる。
領地にいたころ、「厄災を呼ぶ子」と呼ばれていた時には、一度も向けられなかったまなざしだ。
(変な結晶を見つけたのに、怒られるどころか、ちゃんとお礼を言ってくれるんだ……)
結唯が俯きかけた時、箱の中の結晶が、ひときわ強く輝いた。
「わっ!」
白と翡翠と深い夜色が一度に弾け、部屋の中を満たす。
紙束の端がふわりと浮き、ペン立ての影が長く伸びる。
光の中で、結唯は一瞬だけ、見たことのない景色を垣間見た。
夜空に浮かぶ巨大な月。
翼の生えた馬が飛び交う、どこか遠い空。
その真ん中で、誰かと肩を並べて笑っている、自分。
その隣にいる横顔が、ほんの少しだけ優真に似ていた気がして、結唯は慌てて目をこする。
「今の、見えました?」
「少しだけね。未来の断片かもしれない。……結唯さん」
優真は結晶を見下ろしながら、真面目な顔つきになる。
「この結晶は、感謝と願いを糧にして、持ち主の『境遇』を変えると言われている。虐げられてきた者にこそ、よく効くらしい」
結唯の肩が、小さく震えた。
彼女の出自を、優真はうっかり口にしない。そういうところにも、彼の細やかさがにじむ。
「だけど、誰かを見返すためだけに使ったら、本当の意味での大逆転にはならないと思う。君が、君自身の幸せのために笑えるようになってこそ、この結晶は力を発揮するんじゃないかな」
「……わたしの、幸せ」
結唯は小さく復唱する。
領地を追われてここに来た日のことが、頭をよぎった。雨の中、ひとりで歩いた街道。泥にまみれた靴。
それでも諦めずに、この学院の門を叩いた自分。
あの日の震える指先が、今、結晶の光に照らされている。
「じゃあ――」
結唯は顔を上げ、結晶にそっと手を伸ばした。
「この子を悪い人に使わせないように、見張る役目を、わたしにください。誰かを傷つけるためじゃなくて、ちゃんと『ありがとう』が届く場所にだけ、力を使えるように」
優真の目が、大きく見開かれる。
驚いた後で、すぐに柔らかく笑った。
「君は、本当に人のために動くんだね」
「だって……この学院に来られたのも、わたしを拾ってくれた人たちのおかげだから。恩返ししたいんです。ちゃんと、ここで生きていけるように」
結唯の言葉に、結晶がまたひとつ、鈴の音を響かせた。
ちりん、と。
それは、どこかお祝いの鐘のような音だった。
「わかった。では、結唯さんを、この結晶の管理者候補に正式に任命するよ。もちろん、僕も一緒に研究させてもらう。君ひとりに、甘い毒の誘惑は背負わせられないからね」
「はいっ!」
結唯は思わず声を弾ませた。
その笑顔を見た瞬間、優真はふと視線をそらし、咳払いをひとつする。
「それに……」
「それに?」
「この名前を毎回ちゃんと言える人材は貴重だから」
「それは……がんばります!」
結唯が胸を張ると、優真は肩を揺らして笑った。
さっきまで部屋中に積もっていた疲労が、少しだけ薄くなっている気がする。
箱の中のピュアホワイトクリスタルホライズンミッドナイトムーンジェイドは、ふたりのやりとりに合わせるように、静かに瞬きを繰り返していた。
甘くてあたたかい、けれど気を抜けばどこまでも深く沈んでしまいそうな光。
それはたしかに、甘い毒に似ていた。
けれど、その毒に飲み込まれるか、それとも甘さを抱きしめて前へ進むかを決めるのは――
ここで、肩を並べて立つふたり自身だ。
追放された先の王立魔導学院で、結唯の物語はようやく動き出した。
その始まりを照らすのは、長い名前を持つひとつの結晶と、心からの「ありがとう」の光だった。