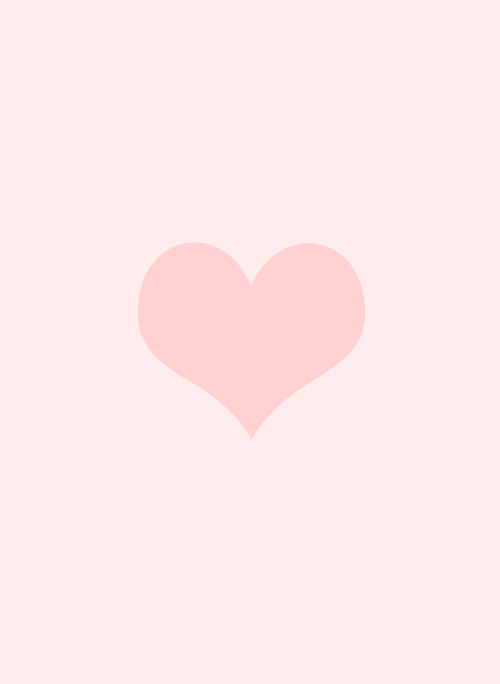赤き月の調べ
「今は、書店の駐車場だ」
「分かった。いま向かってるから、そこに居なさいよ!」
「悪いが、それはできない。厄介事はごめんだからな。彼女は向かいにあるコンビニの一番端に座らせておく」
「ちょっと! あそこは」
「問題ない」
これ以上、話すことはないとばかりに、朔夜は通話終了ボタンを押した。耳元で小型犬のように、きゃんきゃん騒がれるのは鬱陶しい。
携帯電話を鞄に戻し、落ちていた紙袋を拾い上げ、また希空を抱き上げる。
誰に見られているか分からないから、道の反対側にあるコンビニまで人間らしい速さで歩いていく。