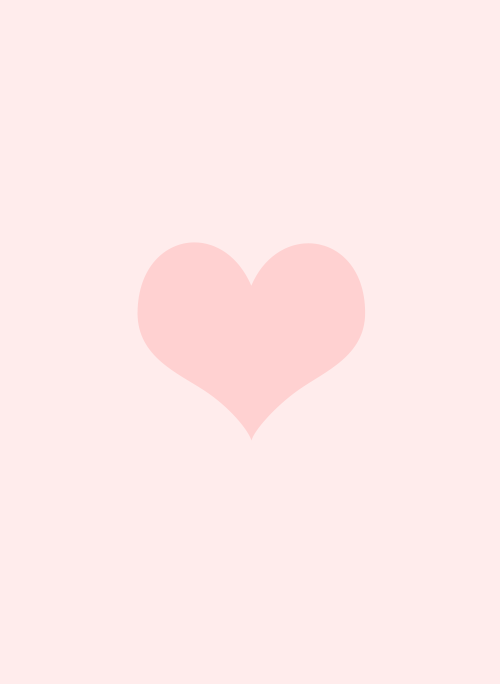LAST SEX
きっとみんな笑っている。自分で仕掛けたこととはいえ、ネガティブな波に飲み込まれていく。クロークから、ジャッケトを受け取ると、目の前に紳士的な笑みを浮かべて桂木が立っていた。
「すみません。グラスを割ってしまって。後で請求してください。もう帰ります。私には場違いでした」
桂木の姿をみると、怒りにも似た感情が湧いてきた。
「グラスの事は気になさらずに。それより怪我はございませんか?それと、場違いなんてとんでもない。ブルーローズは貴女のような方のための場所なんです」
「バツ一子持ち四十女を貶して憐れむ場所ってこと?」
桂木は優しく微笑んだ。
「貴女は素敵な女性です。それをご自身で認めてみてはいかがですか?」
「認めるって?私には好い所なんて一つもないし」
「勿体無いです。貴女はチャーミングなのに」
チャーミングという言葉は嫌いだった。チャーミングはブスに使うフレーズだととらえている。とことん『私』はネガティブなウザい奴に成り下がっているのだ。こんな『私』を認めろと?無理な相談だった。
「気がついてください。自分は綺麗だと」
黙っている『私』に深い優しい旋律で桂木が言った。そして、『私』にある事を提案した。
「次回のブルーローズにまたお越し願いませんか?勿論代金は不要です。私がご招待したので」
桂木が何を企んでいるのか、その意味が分からなくて『私』は、返事に詰ってしまった。
「下心はありません。貴女に幸せになってほしいのです」
桂木の意図が読めない。私の事を何も知らないくせに、そう願えることがわからない。訝しげに、桂木を見つめた。
「…予定が合えば…でも、今度はグラスを3つ割るかもしれませんよ?」
逃げるようにそう言い残し『私』は、その場を立ち去った。エレベーターが来て、最後に桂木を見ると深々と頭を下げている。『私』はより一層自分が嫌いになるような思いがした。
エントランスに到着して、ドアが開くの同時に『私』はエレベーターを降りた。
「ばかばかしい!」
カツカツとヒールの音を響かせながら出口へと向かう。そんな『私』の視界が急に低くなった。そう、『私』はなにもないところで、右脚を滑らせたのだった。ぎりぎりのところで、転けずにいれたのは幸いだったと思う。
「なんなのよ!もう」
羞恥と腹ただしさが会い重なってもう、どこに怒りをぶつけていいかわからない。ここまできたらただの八つ当たりだ。ちらほらと人が居た気がしたが、あえて無視することにする。
踝が痛むが、なにもなかったかのように、『私』は深呼吸するとタバコの匂いが漂ってきた。匂いのする方向を探すと、喫煙ルームがあった。そこから誰か退室するためにドアが開きその隙間をぬって、煙草の匂いが漂ってきたのだろう。
「煙草吸って帰ろう」
『私』は時々煙草を吸った。煙草が灰になるまでの時間は、私にとって冷静になるには丁度良い。肺まで深く吸い込むと、頭がくらりとして、心地よい感じさえすることもある。
『私』は、喫煙ルームのドアを開けた。ヤニの匂いが充満している。正直、煙草の残り香は苦手だ。自分の体に染み込むような気にさえなる。それでも、喫煙は決められた場所でしか吸えない。健康被害が明らかだから、致し方ない。
喫煙ルームには、黒いスーツを着た男が一人いて、一瞬視線が合ったが、『私』は煙草を探す為にバッグに視線を移した。煙草はすぐに取り出せたが、肝心のライターが見つからない。
(マジで?ここに入ってライターないってどうよ?私?)
自分で自分にツッコミを入れながら、人がいるので出るにも出られずにいた。
(借りようかな…。いやでも、女がライター借りるのってちょっと…でも、吸いたい…)
「火ないの?貸そうか?」
くぐもったトーンで、黒いスーツの男が使いこまれたジッポを差し出してくれた。
「…え?はい?あ、ありがとうございます」
殆ど反射的に、見知らぬ男のジッポを手にとっていた。『私』はジッポを開ける時の、金属音が好きだ。煙草を左の人差し指と中指で挟み、右の親指でフリント・ホイールを弾く。
「ちょっ…硬っ」
二、三度試したがフリント・ホイールはギリッ鈍い音をたてるだけで、回らない。錆びてるんじゃないの、これ。もう一度回そうと、親指に力を入れた。ようやく、ホイールが一回転した。しかし、火花が拒むように、小さな火花を散らしただけで火が着くことはなかった。
「もう、いいです」
煙草を吸いたい気持ちが萎えて、ジッポの蓋を閉めて持ち主に返した。
「女の人にはキツいでしょ。コイツにははコツがいるんだ」
持ち主の男はジッポの蓋を片手で開けると、フリント・ホイールを回した。主人に忠実なようで、ジッポはボォ声をあげ火を灯した。
「どうぞ」
男は火が消えないように、『私』の目の前に持ってくる。男は笑顔だったが、どこか嘘くささが漂っていた。そんな男の表情が読めないまま『私』煙草を挟み直して、唇にあてた。
「やっぱりいいです。煙草やめます」
「いらんの?」
『私』が頷くと 男は火を閉じた。
「ええ。煙草って人前じゃ吸えないんです。そもそも煙草は普段吸わないから。ちょっと冷静になりたい時に、吹かす程度なんで」
「じゃ俺が出て行ったら吸ったらいいよ。ジッポ預けて外で待ってるけど?」
独特の声帯の持ち主の男の顔を初めてまともに見上げた。肌が浅黒く、整った眉と瞳鼻筋が通ったその顔は一見怖そうな感じがする。
三十前後といったところだろう。ニコリと笑うが、そこにわざとらしさが感じずにはいられなかった。
多くの患者と接する『私』の仕事は、言わば接客業だ。第一印象で、どのタイプの人間か大体わかる。無意識にグループわけをするのだ。そのグループによって、パターンを、合わせ自分の言動を選ぶ。時には、間違いもあるが初診では、約七割はそのグループを分けられるのだ。そこは、『私』が人の顔色伺いながら生きてきた結果に、得られた所でもあったのかもしれない。長所的ではない特技だろう。
「いいです。いいです。それに、女性がってか、私が煙を鼻から出す姿がちょっと嫌で…あんまり人に見られたくないなーって」
視線を外さないまま、男に告げると男は、声をあげて笑い出した。
「確かに」
声をあげて笑う男からは、嘘くささが消えていた。
「俺、片野敬太。もう一本、代わりに吸うから、副流煙すいこんでおきなよ」
片野敬太と名乗った男は、笑い背広のポケットから、見覚えのある煙草を取り出した。
「いやです。副流煙なんて。…あ…それ」
「そう。同じ。女でこれ吸ってるって見たことない」
敬太は、もう一度笑うとジッポに火を灯した。『私』の心がその炎にあわせユラユラするのを感じた。不思議な気持ちだった。
「すみません。グラスを割ってしまって。後で請求してください。もう帰ります。私には場違いでした」
桂木の姿をみると、怒りにも似た感情が湧いてきた。
「グラスの事は気になさらずに。それより怪我はございませんか?それと、場違いなんてとんでもない。ブルーローズは貴女のような方のための場所なんです」
「バツ一子持ち四十女を貶して憐れむ場所ってこと?」
桂木は優しく微笑んだ。
「貴女は素敵な女性です。それをご自身で認めてみてはいかがですか?」
「認めるって?私には好い所なんて一つもないし」
「勿体無いです。貴女はチャーミングなのに」
チャーミングという言葉は嫌いだった。チャーミングはブスに使うフレーズだととらえている。とことん『私』はネガティブなウザい奴に成り下がっているのだ。こんな『私』を認めろと?無理な相談だった。
「気がついてください。自分は綺麗だと」
黙っている『私』に深い優しい旋律で桂木が言った。そして、『私』にある事を提案した。
「次回のブルーローズにまたお越し願いませんか?勿論代金は不要です。私がご招待したので」
桂木が何を企んでいるのか、その意味が分からなくて『私』は、返事に詰ってしまった。
「下心はありません。貴女に幸せになってほしいのです」
桂木の意図が読めない。私の事を何も知らないくせに、そう願えることがわからない。訝しげに、桂木を見つめた。
「…予定が合えば…でも、今度はグラスを3つ割るかもしれませんよ?」
逃げるようにそう言い残し『私』は、その場を立ち去った。エレベーターが来て、最後に桂木を見ると深々と頭を下げている。『私』はより一層自分が嫌いになるような思いがした。
エントランスに到着して、ドアが開くの同時に『私』はエレベーターを降りた。
「ばかばかしい!」
カツカツとヒールの音を響かせながら出口へと向かう。そんな『私』の視界が急に低くなった。そう、『私』はなにもないところで、右脚を滑らせたのだった。ぎりぎりのところで、転けずにいれたのは幸いだったと思う。
「なんなのよ!もう」
羞恥と腹ただしさが会い重なってもう、どこに怒りをぶつけていいかわからない。ここまできたらただの八つ当たりだ。ちらほらと人が居た気がしたが、あえて無視することにする。
踝が痛むが、なにもなかったかのように、『私』は深呼吸するとタバコの匂いが漂ってきた。匂いのする方向を探すと、喫煙ルームがあった。そこから誰か退室するためにドアが開きその隙間をぬって、煙草の匂いが漂ってきたのだろう。
「煙草吸って帰ろう」
『私』は時々煙草を吸った。煙草が灰になるまでの時間は、私にとって冷静になるには丁度良い。肺まで深く吸い込むと、頭がくらりとして、心地よい感じさえすることもある。
『私』は、喫煙ルームのドアを開けた。ヤニの匂いが充満している。正直、煙草の残り香は苦手だ。自分の体に染み込むような気にさえなる。それでも、喫煙は決められた場所でしか吸えない。健康被害が明らかだから、致し方ない。
喫煙ルームには、黒いスーツを着た男が一人いて、一瞬視線が合ったが、『私』は煙草を探す為にバッグに視線を移した。煙草はすぐに取り出せたが、肝心のライターが見つからない。
(マジで?ここに入ってライターないってどうよ?私?)
自分で自分にツッコミを入れながら、人がいるので出るにも出られずにいた。
(借りようかな…。いやでも、女がライター借りるのってちょっと…でも、吸いたい…)
「火ないの?貸そうか?」
くぐもったトーンで、黒いスーツの男が使いこまれたジッポを差し出してくれた。
「…え?はい?あ、ありがとうございます」
殆ど反射的に、見知らぬ男のジッポを手にとっていた。『私』はジッポを開ける時の、金属音が好きだ。煙草を左の人差し指と中指で挟み、右の親指でフリント・ホイールを弾く。
「ちょっ…硬っ」
二、三度試したがフリント・ホイールはギリッ鈍い音をたてるだけで、回らない。錆びてるんじゃないの、これ。もう一度回そうと、親指に力を入れた。ようやく、ホイールが一回転した。しかし、火花が拒むように、小さな火花を散らしただけで火が着くことはなかった。
「もう、いいです」
煙草を吸いたい気持ちが萎えて、ジッポの蓋を閉めて持ち主に返した。
「女の人にはキツいでしょ。コイツにははコツがいるんだ」
持ち主の男はジッポの蓋を片手で開けると、フリント・ホイールを回した。主人に忠実なようで、ジッポはボォ声をあげ火を灯した。
「どうぞ」
男は火が消えないように、『私』の目の前に持ってくる。男は笑顔だったが、どこか嘘くささが漂っていた。そんな男の表情が読めないまま『私』煙草を挟み直して、唇にあてた。
「やっぱりいいです。煙草やめます」
「いらんの?」
『私』が頷くと 男は火を閉じた。
「ええ。煙草って人前じゃ吸えないんです。そもそも煙草は普段吸わないから。ちょっと冷静になりたい時に、吹かす程度なんで」
「じゃ俺が出て行ったら吸ったらいいよ。ジッポ預けて外で待ってるけど?」
独特の声帯の持ち主の男の顔を初めてまともに見上げた。肌が浅黒く、整った眉と瞳鼻筋が通ったその顔は一見怖そうな感じがする。
三十前後といったところだろう。ニコリと笑うが、そこにわざとらしさが感じずにはいられなかった。
多くの患者と接する『私』の仕事は、言わば接客業だ。第一印象で、どのタイプの人間か大体わかる。無意識にグループわけをするのだ。そのグループによって、パターンを、合わせ自分の言動を選ぶ。時には、間違いもあるが初診では、約七割はそのグループを分けられるのだ。そこは、『私』が人の顔色伺いながら生きてきた結果に、得られた所でもあったのかもしれない。長所的ではない特技だろう。
「いいです。いいです。それに、女性がってか、私が煙を鼻から出す姿がちょっと嫌で…あんまり人に見られたくないなーって」
視線を外さないまま、男に告げると男は、声をあげて笑い出した。
「確かに」
声をあげて笑う男からは、嘘くささが消えていた。
「俺、片野敬太。もう一本、代わりに吸うから、副流煙すいこんでおきなよ」
片野敬太と名乗った男は、笑い背広のポケットから、見覚えのある煙草を取り出した。
「いやです。副流煙なんて。…あ…それ」
「そう。同じ。女でこれ吸ってるって見たことない」
敬太は、もう一度笑うとジッポに火を灯した。『私』の心がその炎にあわせユラユラするのを感じた。不思議な気持ちだった。