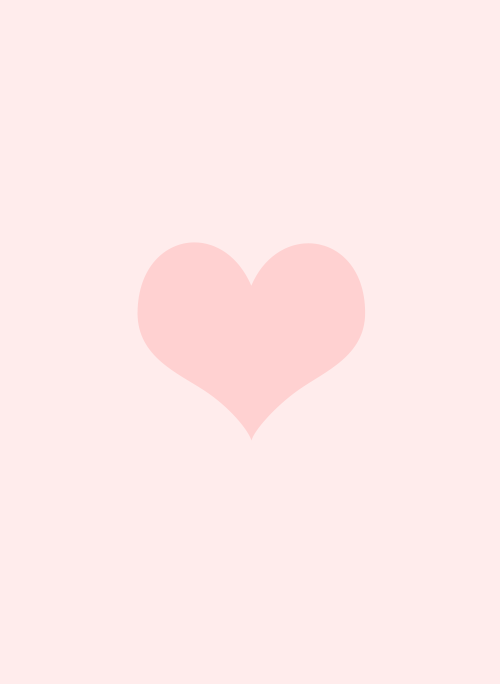秋色紫陽花
無防備な首筋に押しつけられるやわらかな感触。丁寧に啄ばまれて、体中のすべての感覚が彼へと向かう。
やがて彼の感触が鎖骨へと滑り降りていく。息とともに声が漏れて、反らした体が浮き上がる。触れた彼の手が、そっと右肩を抑えた。
私の頬を左手で包み込んで、彼が目を細める。
「だから言ったんだ、本気になる前に帰れって」
耳元で囁く彼の息遣いが、体の奥を震わせる。
「だって……ひとりはイヤだから」
つい零れてしまったのは本音。こんな台風の夜、ひとりで家に居るのは怖いから。だけど帰りたくないなんて、カッコ悪くて言えない。今夜だけ泊まらせてなんて言える訳がない。
そんな私の気持ちも知らず『早く帰れ』という彼に、ただ苛立っていた。
もし彼がわかっていたとしたら、かなりの意地悪だ。
悔しいけれど、本当は期待していたのかもしれない。こうなることを。
「だったら、一緒に居てやるよ」
唇を割いて入り込んできた彼が、やわらかく甘い水音を奏でる。
穏やかな揺らぎに、ゆっくりと呑み込まれていく。
もう、雨音は聴こえない。
- 完 -