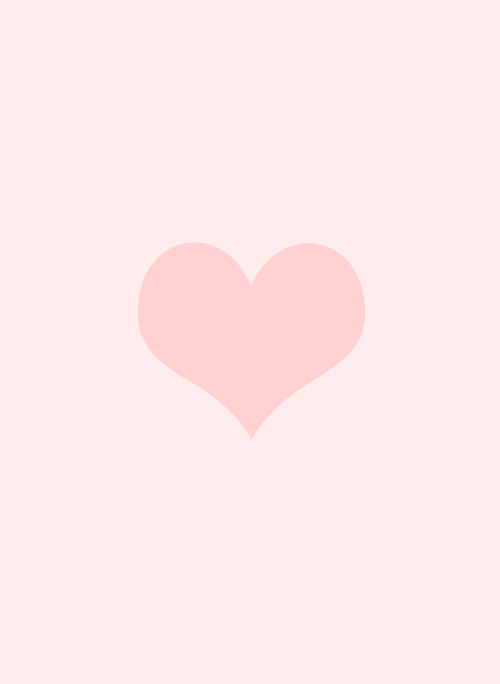婚約破棄をされたとしても、あの娘にだけは譲らない 〜悪辣令嬢はヒロイン「風」に擬態して、二人の恋の邪魔をする〜
こんな場面を見るくらいなら、この道を通らなければよかった――。
柔らかな太陽の光が降り注ぐ、セントポーリア学園の昼休みも終わり間際。友人と一緒に教室へと戻ろうと中庭を歩いていた伯爵令嬢のサリー・カンテノルは、ぎゅうと艷やかな唇を噛み締めた。
目に飛び込んできたのは、新緑が眩しい植栽の向こうの東屋の下。ツインテールのピンクブロンドの髪を楽しげに揺らす女子学生と、サリーの婚約者である候爵子息のユーリ・ブローニュを中心に、数人の男子学生の談笑をしている姿だった。
この髪色の持ち主は学園には一人しか在籍していない。また男爵令嬢のアイリス・ラグーンだ。
視線を逸らしたサリーは深呼吸すると、そのまま立ち去ろうとした。
けれど。
「――しかしサリー・カンテノル嬢、彼女は令嬢としては完璧かもしれないけれど、本当に可愛げがないよな」
そんな一言に、今度こそ足がピタリと止まってしまった。
「サリー嬢のあのツンと澄ました態度。薄氷色の髪色も、情が薄そうな感じだし」
「幼い頃から決められていたとはいえ、あんなのが婚約者だなんて、ユーリも災難だな」
「……こんな時まで彼女の事を思い出させないでくれよ」
チョコレート色の長い睫毛を伏せ物憂げな表情を浮かべたユーリを、傍らに座る少女が気遣わしげに覗き込む。
「ユーリ様、元気がありませんね?大丈夫ですか?」
「そうかい?……アイリスは優しいね」
「いいなー俺もアイリスに心配されたいなあ」
「えっ?!も、もう皆さんったらっ」
周囲の野次にピンクブロンドの髪の女学生は、わたわたと手を振り頬を染める。
そんなやり取りを見ていた誰かが「そういえば」と呟いた。
「二人を見ていると、ムルー・ジュルトンの劇が思い出されるな」
「ああ、『薔薇の乙女と貴公子』かい?……確かに言われてみればそうかもしれないね」
ムルー・ジュルトンとは匿名で活動をする劇作家だ。顔も本名も誰も知らない。けれど彼が生み出す作品は、どれもドラマチックだと評判を呼んでいる。そんな彼の最新作である「薔薇の乙女と貴公子」とは、平民として育った主人公がひょんな事から貴族の一員となり、薔薇の花咲き誇る園遊会で貴公子と恋に落ちるラブストーリーだ。けれど貴公子には親に決められた許嫁がいて――。
「主人公が嫉妬に駆られた許嫁から虐められて可哀想だけれど、貴公子を想う純粋な気持ちがいじらしくてな。困難に打ち勝って、二人が結ばれる最後のシーンは本当に感動的だったよ」
「そうそう。でもあの高慢で冷徹な許嫁って――」
その続きの言葉にサリーは眉間に皺を寄せ、いよいよ表情を強張らせた。
「設定といい劇中の見た目といい、サリー・カンテノル嬢そっくりなんだよな」
劇中の許嫁は、淡い紫陽花色の髪と瞳を持つ美しい高位貴族として描かれている。しかしその性格は極めて悪辣な令嬢だ。政略結婚の相手である貴公子の家名に異様な程の固執を見せ、主人公らにありとあらゆる嫌がらせをするのだ。
「サリーが悪辣令嬢そっくりですって?!なんて酷いことをっ……!」
「待って」
余りの言い草に東屋へと駆け寄って行こうとする友人のキャシーの腕を掴み、サリーは静かに首を横に振る。
彼らの話を立ち聞きしていたのはこちらである。口論になったのなら分が悪い。それに――。
この話題に彼はどんな反応をするのだろう。
自身の婚約者はそんな人物ではないと、せめて反論してはくれないだろうか。
サリーは固唾を呑んで、会話の行方に聞き耳を立てた。
「彼女が欲しいのはブローニュの名前だけさ。僕自身にはなんの興味も持っていない。そんな冷たいところがそっくりだよ」
自嘲気味に呟くユーリに「そんな……お可哀想なユーリ様!」と、アイリスが悲壮な声を上げる。
「あの、ユーリ様。こんな事を言うと貴族らしくないと思われるかもしれませんが……。やっぱり結婚は、愛し合ってこそだと、私は思いますよ?」
「……そうだね。僕の婚約者がアイリスだったら良かったのに」
潤んだ瞳のアイリスが、そっとユーリの腕に触れる。すると彼もまたその手に手を重ね、愛おしそうにに彼女に向けて微笑んだ。
――十年来の婚約者の不名誉な噂を否定しないばかりか、彼は今、市井出身だという男爵令嬢にうつつを抜かしている。
ユーリの薄情な態度に、今更ながらサリーは言いようのない衝撃を受けていた。
平民として育ったアイリスが、その優秀さから男爵の養女となり学園に転入してきたのは三ヶ月前の事。
貴族らしからぬ天真爛漫さと率直さが物珍しかったのか。はたまた珍しいピンクブロンドに揺れる美しい髪色に魅せられたとでも言うのだろうか。彼女が学園中の有力貴族の子息の心を掴んでいったのはあっという間のことだった。
彼女は「サロン」と称し、いつしか周囲に彼らを侍らすようになっていった。そしてあろうことかサリーの婚約者であるユーリまでもがそのサロンの仲間となり……そして彼女へ心を寄せるようになってしまったのだった。
「あんなマナーもなっていないような女の何がいいっていうのかしら?」
東屋から離れたベンチに腰掛けると、キャシーは怒りも露わにハンカチをぎゅうと握り締めている。
サロンに在籍する子息の中には、ユーリだけでなく婚約している者もいる。
「仲良くなるのにに、男も女も関係ないわ!ましてや婚約者がいたとしたって友情を育むのになんの問題があるというの?」
とは、アイリスの弁である。けれどそんなことを力説する彼女と行動を共にする同性の友人の姿を見たものは誰もいない。
「私、平民出身だから令嬢の皆さんに嫌われているのかも」
そんなことを言いながら涙の一つも溢せば、庇護欲でもそそられるのかあっという間に崇拝者の出来上がりだ。
「大体あの女が転入してまだたったの三ヶ月ですよ?それなのに簡単に心変わりするだなんて!」
未だ怒りが冷めやらぬキャシーとは裏腹に、思案げにしていたサリーはポツリと呟いた。
「あの娘にあって、私にないものって何かしら?」
「え……。妙に距離感が近くて、喜怒哀楽の感情表現が大袈裟で、あけすけ……とか?」
キャシーが戸惑いながら答えると、うつむいていたサリーはスッと顔を上げた。
「私、彼から婚約破棄したいと言われたら、それはそれで仕方のないことだとは思いますの」
「ええっ?」
キャシーが驚いて、サリーの顔をまじまじと見つめる。
そもそもユーリとサリーの婚約は、格上であるブローニュ家との縁を繋ぐ代わりに、産業が発達するカンテノル家の技術を提供するという契約の元に取り交わされた、所謂戦略的なものである。貴族社会における婚姻というものは多かれ少なかれ「家の発展の為」であることが多い。それ故この婚約について、サリー個人としては今まで特段不満を感じたことは無かった。
「……でもね」
キラリと光るその瞳には固い決意のようなものが見え隠れする。
「破棄されたとしても、彼があの娘と結ばれるのだけは嫌なんですの」
「え?」
「妙に距離感が近くて、喜怒哀楽の感情表現が大袈裟で、あけすけな女性が好みですって?ならばあの娘よりもそんな魅力に溢れている女性と出会ったなら、そちらに心惹かれるに違いないわよね」
「サリー……。あなた、何をする気なの?」
キャシーの問いかけに、優美な、けれど有無を言わせぬ様な威圧的な微笑みを称えたサリーがゆっくりと口を開く。
「彼はこの三ヶ月で心変わりをされのでしょう?だから……私も三ヶ月かけて、あの方々の恋を駄目にしてさしあげますのよ」
◇◇◇
柔らかな太陽の光が降り注ぐ、セントポーリア学園の昼休みも終わり間際。友人と一緒に教室へと戻ろうと中庭を歩いていた伯爵令嬢のサリー・カンテノルは、ぎゅうと艷やかな唇を噛み締めた。
目に飛び込んできたのは、新緑が眩しい植栽の向こうの東屋の下。ツインテールのピンクブロンドの髪を楽しげに揺らす女子学生と、サリーの婚約者である候爵子息のユーリ・ブローニュを中心に、数人の男子学生の談笑をしている姿だった。
この髪色の持ち主は学園には一人しか在籍していない。また男爵令嬢のアイリス・ラグーンだ。
視線を逸らしたサリーは深呼吸すると、そのまま立ち去ろうとした。
けれど。
「――しかしサリー・カンテノル嬢、彼女は令嬢としては完璧かもしれないけれど、本当に可愛げがないよな」
そんな一言に、今度こそ足がピタリと止まってしまった。
「サリー嬢のあのツンと澄ました態度。薄氷色の髪色も、情が薄そうな感じだし」
「幼い頃から決められていたとはいえ、あんなのが婚約者だなんて、ユーリも災難だな」
「……こんな時まで彼女の事を思い出させないでくれよ」
チョコレート色の長い睫毛を伏せ物憂げな表情を浮かべたユーリを、傍らに座る少女が気遣わしげに覗き込む。
「ユーリ様、元気がありませんね?大丈夫ですか?」
「そうかい?……アイリスは優しいね」
「いいなー俺もアイリスに心配されたいなあ」
「えっ?!も、もう皆さんったらっ」
周囲の野次にピンクブロンドの髪の女学生は、わたわたと手を振り頬を染める。
そんなやり取りを見ていた誰かが「そういえば」と呟いた。
「二人を見ていると、ムルー・ジュルトンの劇が思い出されるな」
「ああ、『薔薇の乙女と貴公子』かい?……確かに言われてみればそうかもしれないね」
ムルー・ジュルトンとは匿名で活動をする劇作家だ。顔も本名も誰も知らない。けれど彼が生み出す作品は、どれもドラマチックだと評判を呼んでいる。そんな彼の最新作である「薔薇の乙女と貴公子」とは、平民として育った主人公がひょんな事から貴族の一員となり、薔薇の花咲き誇る園遊会で貴公子と恋に落ちるラブストーリーだ。けれど貴公子には親に決められた許嫁がいて――。
「主人公が嫉妬に駆られた許嫁から虐められて可哀想だけれど、貴公子を想う純粋な気持ちがいじらしくてな。困難に打ち勝って、二人が結ばれる最後のシーンは本当に感動的だったよ」
「そうそう。でもあの高慢で冷徹な許嫁って――」
その続きの言葉にサリーは眉間に皺を寄せ、いよいよ表情を強張らせた。
「設定といい劇中の見た目といい、サリー・カンテノル嬢そっくりなんだよな」
劇中の許嫁は、淡い紫陽花色の髪と瞳を持つ美しい高位貴族として描かれている。しかしその性格は極めて悪辣な令嬢だ。政略結婚の相手である貴公子の家名に異様な程の固執を見せ、主人公らにありとあらゆる嫌がらせをするのだ。
「サリーが悪辣令嬢そっくりですって?!なんて酷いことをっ……!」
「待って」
余りの言い草に東屋へと駆け寄って行こうとする友人のキャシーの腕を掴み、サリーは静かに首を横に振る。
彼らの話を立ち聞きしていたのはこちらである。口論になったのなら分が悪い。それに――。
この話題に彼はどんな反応をするのだろう。
自身の婚約者はそんな人物ではないと、せめて反論してはくれないだろうか。
サリーは固唾を呑んで、会話の行方に聞き耳を立てた。
「彼女が欲しいのはブローニュの名前だけさ。僕自身にはなんの興味も持っていない。そんな冷たいところがそっくりだよ」
自嘲気味に呟くユーリに「そんな……お可哀想なユーリ様!」と、アイリスが悲壮な声を上げる。
「あの、ユーリ様。こんな事を言うと貴族らしくないと思われるかもしれませんが……。やっぱり結婚は、愛し合ってこそだと、私は思いますよ?」
「……そうだね。僕の婚約者がアイリスだったら良かったのに」
潤んだ瞳のアイリスが、そっとユーリの腕に触れる。すると彼もまたその手に手を重ね、愛おしそうにに彼女に向けて微笑んだ。
――十年来の婚約者の不名誉な噂を否定しないばかりか、彼は今、市井出身だという男爵令嬢にうつつを抜かしている。
ユーリの薄情な態度に、今更ながらサリーは言いようのない衝撃を受けていた。
平民として育ったアイリスが、その優秀さから男爵の養女となり学園に転入してきたのは三ヶ月前の事。
貴族らしからぬ天真爛漫さと率直さが物珍しかったのか。はたまた珍しいピンクブロンドに揺れる美しい髪色に魅せられたとでも言うのだろうか。彼女が学園中の有力貴族の子息の心を掴んでいったのはあっという間のことだった。
彼女は「サロン」と称し、いつしか周囲に彼らを侍らすようになっていった。そしてあろうことかサリーの婚約者であるユーリまでもがそのサロンの仲間となり……そして彼女へ心を寄せるようになってしまったのだった。
「あんなマナーもなっていないような女の何がいいっていうのかしら?」
東屋から離れたベンチに腰掛けると、キャシーは怒りも露わにハンカチをぎゅうと握り締めている。
サロンに在籍する子息の中には、ユーリだけでなく婚約している者もいる。
「仲良くなるのにに、男も女も関係ないわ!ましてや婚約者がいたとしたって友情を育むのになんの問題があるというの?」
とは、アイリスの弁である。けれどそんなことを力説する彼女と行動を共にする同性の友人の姿を見たものは誰もいない。
「私、平民出身だから令嬢の皆さんに嫌われているのかも」
そんなことを言いながら涙の一つも溢せば、庇護欲でもそそられるのかあっという間に崇拝者の出来上がりだ。
「大体あの女が転入してまだたったの三ヶ月ですよ?それなのに簡単に心変わりするだなんて!」
未だ怒りが冷めやらぬキャシーとは裏腹に、思案げにしていたサリーはポツリと呟いた。
「あの娘にあって、私にないものって何かしら?」
「え……。妙に距離感が近くて、喜怒哀楽の感情表現が大袈裟で、あけすけ……とか?」
キャシーが戸惑いながら答えると、うつむいていたサリーはスッと顔を上げた。
「私、彼から婚約破棄したいと言われたら、それはそれで仕方のないことだとは思いますの」
「ええっ?」
キャシーが驚いて、サリーの顔をまじまじと見つめる。
そもそもユーリとサリーの婚約は、格上であるブローニュ家との縁を繋ぐ代わりに、産業が発達するカンテノル家の技術を提供するという契約の元に取り交わされた、所謂戦略的なものである。貴族社会における婚姻というものは多かれ少なかれ「家の発展の為」であることが多い。それ故この婚約について、サリー個人としては今まで特段不満を感じたことは無かった。
「……でもね」
キラリと光るその瞳には固い決意のようなものが見え隠れする。
「破棄されたとしても、彼があの娘と結ばれるのだけは嫌なんですの」
「え?」
「妙に距離感が近くて、喜怒哀楽の感情表現が大袈裟で、あけすけな女性が好みですって?ならばあの娘よりもそんな魅力に溢れている女性と出会ったなら、そちらに心惹かれるに違いないわよね」
「サリー……。あなた、何をする気なの?」
キャシーの問いかけに、優美な、けれど有無を言わせぬ様な威圧的な微笑みを称えたサリーがゆっくりと口を開く。
「彼はこの三ヶ月で心変わりをされのでしょう?だから……私も三ヶ月かけて、あの方々の恋を駄目にしてさしあげますのよ」
◇◇◇