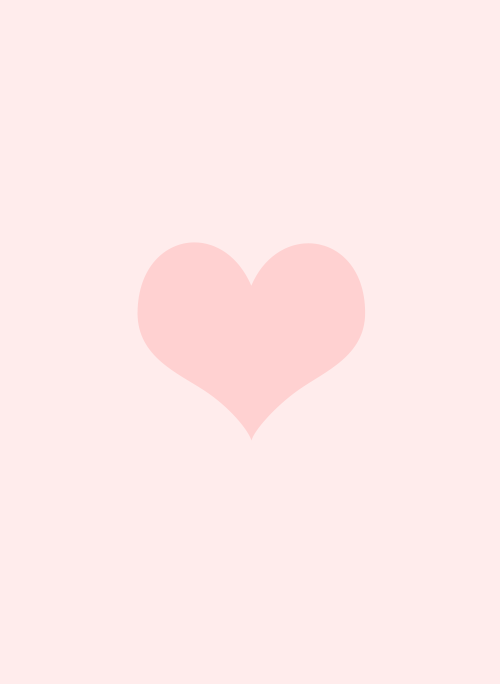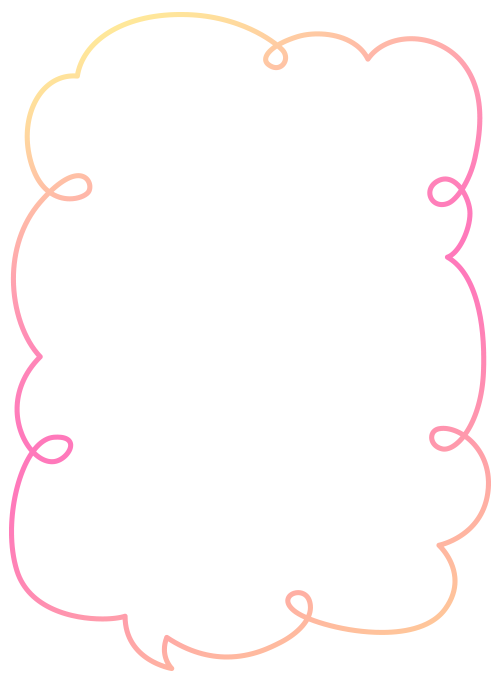紫陽花の憂鬱
電車に乗って30分、そこから徒歩で10分ほどで目的の場所に到着した。
「あの、本当にフリープランでいいの?」
「うん。早く出てくる分には問題ないんでしょ?」
「そう…だけど、でも日向くんは読書とか普段そんなにしてないって…。」
「んー…まぁそれはそうなんだけど。でも今日は本を読みに来た部分もあるけど、休日の紫月さんを見に来たって言った方が正しいから。紫月さんが居たいだけいてくれた方がいいし、終わりの時間が決まってる方がなんだかせかせかしちゃわない?」
日向の提案は正直ありがたかったが、付き合わせすぎてはいないかと不安にはなる。その不安がありありと表情に出てしまっていたのかもしれない。日向はくすっと笑って、言葉を続けた。
「本当に、紫月さんの休日に俺が混ぜてもらってるだけなんだから、そんなに気にしなくていいよ。あと、こういう隠れ家っぽいというかさ、自分が行ったことない場所ってちょっと気になるし。行こう?」
日向に軽く背を押されて、ブックカフェの戸を開けた。
* * *
ドリンクはフリーであるため、すぐ手に取ってもよかったのだが、紫月はどうしても見たいものがあった。そのため、入る手続きを済ませた後、くるりと日向の方を振り返った。
「あの…。」
「うん。どこか見たいところとか、ある感じ?」
「あっ、うん。多分ちょっと奥のところというか、手前にはないっぽいので…少し探検してもいいかな?あ、でも喉乾いてるとかなら全然!休憩してからでも…。」
「大丈夫。紫月さんが見たかったもの、俺も見たいし。何だろ?」
ブックカフェというものに行ったことがないから普通が何かはわからないが、もはやちょっとした図書館といえるのではないかというくらいの蔵書に目が奪われて、あちこちを凝視してしまう。少し後ろからくすっという笑い声が聞こえて、紫月は振り返った。
「…な、なんか変なこと、しちゃった?」
「ううん。なんかわくわくしてる紫月さんが面白くて。一生懸命だよね、いつも。」
「ご、ごめん!年甲斐もなくはしゃいじゃって…!」
「え?いいじゃん。はしゃぐところなんて初めて見たし。ずっと新鮮で楽しいよ?」
そう言って笑う日向にとくんと心臓が鳴る。言葉に詰まって、恥ずかしさから目を逸らしたくなってしまう。それでも紫月は両手をぐっと握って、頷いた。
「…じゃっ…じゃあ、進みます。」
「うん。隊長についていきます!」
そのまま奥まで進むと、壁一面の蔵書が2人を出迎えた。少し古い紙の匂いがして、紫月はスンと鼻を鳴らした。
「…これが…見たかったの。」
「…圧巻だね、これ。」
「ね。…こういう景色だったのかなぁ。」
「え?」
「あ、あの…えっと、好きな映画があってね。」
「うん。」
日向の声はずっと優しい。職場にいても声は優しいけれど、今日はそれ以上にずっと優しく聞こえる。その優しい響きに頑張る力をもらって、紫月は口を開いた。今日は口も重くは感じない。
「私、美女と野獣っていう映画が好きなの。…特に、野獣がヒロインに図書室をプレゼントするところが好きで。…ヒロインはね本が好きで、だから野獣はそれをプレゼントしてくれるんだけど、こんな感じで壁一面に本がずらーって。それこそ天井まであるような空間でね。だからずっと、憧れがあって。…一人じゃちょっと行こうって思えなかったから、今日は一緒に来てくれてありがとう。見たかったものが一つ、見れた。」
紫月は日向に笑みを向けた。一瞬驚いたような表情を浮かべた日向は、笑みを深くした。
「…ヒロインの本当に好きなものをドンピシャでプレゼントするなんて、なかなかやるね、野獣も。」
「不器用だけど、…わかりにくいけどでも野獣はね、本当は優しいの。だって、彼女が本当に何を好きかなんて、もちろんお城のメイドたちも少しは教えてくれるけど、よく見ていないとそうだって気付けないでしょう?」
「うん、そうだね。よく見てないと、好きなものってわからない。よく見ててもまだまだわからないこと、いっぱいあるし。」
「日向くんもそう?」
「紫月さんも?」
「…うん。わからないことだらけ。私、人と関わることを多分、いっぱいサボってきちゃったんだと思う。だから今も、全然上手じゃない。日向くんが優しいから、今日は何とかなってるだけ、です。」
日向が一歩、紫月との距離を詰めた。そして紫月の視線の高さまで、膝を曲げて下りてくる。
「紫月さんの視線からだとこうなるんだね。これは確かにヒロイン目線。」
「え?」
「まぁ俺は多分野獣よりでかくはないけどさ、紫月さんはきっとヒロインと同じじゃない?だから、視界いっぱいに好きな本が並ぶっていう光景とか視野のリアルさは体験できてる気がする。」
「…そっか。…嬉しくて、こんなの本当ににこにこの笑顔になっちゃうね。」
「なってるなってる。」
「え?」
「紫月さん、ずっとにこにこだよ。」
指摘されて自分の両頬に触れると、確かに上がっている、そんな気がした。
「ね?」
「…そ、そのようです…。」
「せっかくだからこのでっかい本棚の中から1冊探そうかな。背表紙だけで惹きつけられたものを1冊選ぶ…とかでもいいのかな?図書館と同じシステム?」
そう問われて紫月は辺りを見回した。別の客が棚から2冊、本を取り出して持って行った。おそらく、ここの棚のものも自由に持ち出していいのだろう。
「…多分、持って行って良さそう。あ、書いてた。ご自由にお読みいただけますって。読んだ後返せばいいみたい。」
「そっかそっか。じゃあなるべく薄いのにしようかな。久しぶりだな…こんなに本に触れるの。」
「全部読み切らなくても、ぺらぺらっとめくるだけでも楽しい、…時もある…かも。」
「はは、最後何でそんな聞こえない声で言うのさ。そうだよね、別に全部読み切らないといけないわけじゃない。紫月さんの言う通りだよ。だから俺も、そんなに肩肘張らずに選ぶね。」
そしてゆっくりと日向が離れていく。その背中を見送ってから、紫月は目の前の大きな本棚に集中した。
「あの、本当にフリープランでいいの?」
「うん。早く出てくる分には問題ないんでしょ?」
「そう…だけど、でも日向くんは読書とか普段そんなにしてないって…。」
「んー…まぁそれはそうなんだけど。でも今日は本を読みに来た部分もあるけど、休日の紫月さんを見に来たって言った方が正しいから。紫月さんが居たいだけいてくれた方がいいし、終わりの時間が決まってる方がなんだかせかせかしちゃわない?」
日向の提案は正直ありがたかったが、付き合わせすぎてはいないかと不安にはなる。その不安がありありと表情に出てしまっていたのかもしれない。日向はくすっと笑って、言葉を続けた。
「本当に、紫月さんの休日に俺が混ぜてもらってるだけなんだから、そんなに気にしなくていいよ。あと、こういう隠れ家っぽいというかさ、自分が行ったことない場所ってちょっと気になるし。行こう?」
日向に軽く背を押されて、ブックカフェの戸を開けた。
* * *
ドリンクはフリーであるため、すぐ手に取ってもよかったのだが、紫月はどうしても見たいものがあった。そのため、入る手続きを済ませた後、くるりと日向の方を振り返った。
「あの…。」
「うん。どこか見たいところとか、ある感じ?」
「あっ、うん。多分ちょっと奥のところというか、手前にはないっぽいので…少し探検してもいいかな?あ、でも喉乾いてるとかなら全然!休憩してからでも…。」
「大丈夫。紫月さんが見たかったもの、俺も見たいし。何だろ?」
ブックカフェというものに行ったことがないから普通が何かはわからないが、もはやちょっとした図書館といえるのではないかというくらいの蔵書に目が奪われて、あちこちを凝視してしまう。少し後ろからくすっという笑い声が聞こえて、紫月は振り返った。
「…な、なんか変なこと、しちゃった?」
「ううん。なんかわくわくしてる紫月さんが面白くて。一生懸命だよね、いつも。」
「ご、ごめん!年甲斐もなくはしゃいじゃって…!」
「え?いいじゃん。はしゃぐところなんて初めて見たし。ずっと新鮮で楽しいよ?」
そう言って笑う日向にとくんと心臓が鳴る。言葉に詰まって、恥ずかしさから目を逸らしたくなってしまう。それでも紫月は両手をぐっと握って、頷いた。
「…じゃっ…じゃあ、進みます。」
「うん。隊長についていきます!」
そのまま奥まで進むと、壁一面の蔵書が2人を出迎えた。少し古い紙の匂いがして、紫月はスンと鼻を鳴らした。
「…これが…見たかったの。」
「…圧巻だね、これ。」
「ね。…こういう景色だったのかなぁ。」
「え?」
「あ、あの…えっと、好きな映画があってね。」
「うん。」
日向の声はずっと優しい。職場にいても声は優しいけれど、今日はそれ以上にずっと優しく聞こえる。その優しい響きに頑張る力をもらって、紫月は口を開いた。今日は口も重くは感じない。
「私、美女と野獣っていう映画が好きなの。…特に、野獣がヒロインに図書室をプレゼントするところが好きで。…ヒロインはね本が好きで、だから野獣はそれをプレゼントしてくれるんだけど、こんな感じで壁一面に本がずらーって。それこそ天井まであるような空間でね。だからずっと、憧れがあって。…一人じゃちょっと行こうって思えなかったから、今日は一緒に来てくれてありがとう。見たかったものが一つ、見れた。」
紫月は日向に笑みを向けた。一瞬驚いたような表情を浮かべた日向は、笑みを深くした。
「…ヒロインの本当に好きなものをドンピシャでプレゼントするなんて、なかなかやるね、野獣も。」
「不器用だけど、…わかりにくいけどでも野獣はね、本当は優しいの。だって、彼女が本当に何を好きかなんて、もちろんお城のメイドたちも少しは教えてくれるけど、よく見ていないとそうだって気付けないでしょう?」
「うん、そうだね。よく見てないと、好きなものってわからない。よく見ててもまだまだわからないこと、いっぱいあるし。」
「日向くんもそう?」
「紫月さんも?」
「…うん。わからないことだらけ。私、人と関わることを多分、いっぱいサボってきちゃったんだと思う。だから今も、全然上手じゃない。日向くんが優しいから、今日は何とかなってるだけ、です。」
日向が一歩、紫月との距離を詰めた。そして紫月の視線の高さまで、膝を曲げて下りてくる。
「紫月さんの視線からだとこうなるんだね。これは確かにヒロイン目線。」
「え?」
「まぁ俺は多分野獣よりでかくはないけどさ、紫月さんはきっとヒロインと同じじゃない?だから、視界いっぱいに好きな本が並ぶっていう光景とか視野のリアルさは体験できてる気がする。」
「…そっか。…嬉しくて、こんなの本当ににこにこの笑顔になっちゃうね。」
「なってるなってる。」
「え?」
「紫月さん、ずっとにこにこだよ。」
指摘されて自分の両頬に触れると、確かに上がっている、そんな気がした。
「ね?」
「…そ、そのようです…。」
「せっかくだからこのでっかい本棚の中から1冊探そうかな。背表紙だけで惹きつけられたものを1冊選ぶ…とかでもいいのかな?図書館と同じシステム?」
そう問われて紫月は辺りを見回した。別の客が棚から2冊、本を取り出して持って行った。おそらく、ここの棚のものも自由に持ち出していいのだろう。
「…多分、持って行って良さそう。あ、書いてた。ご自由にお読みいただけますって。読んだ後返せばいいみたい。」
「そっかそっか。じゃあなるべく薄いのにしようかな。久しぶりだな…こんなに本に触れるの。」
「全部読み切らなくても、ぺらぺらっとめくるだけでも楽しい、…時もある…かも。」
「はは、最後何でそんな聞こえない声で言うのさ。そうだよね、別に全部読み切らないといけないわけじゃない。紫月さんの言う通りだよ。だから俺も、そんなに肩肘張らずに選ぶね。」
そしてゆっくりと日向が離れていく。その背中を見送ってから、紫月は目の前の大きな本棚に集中した。