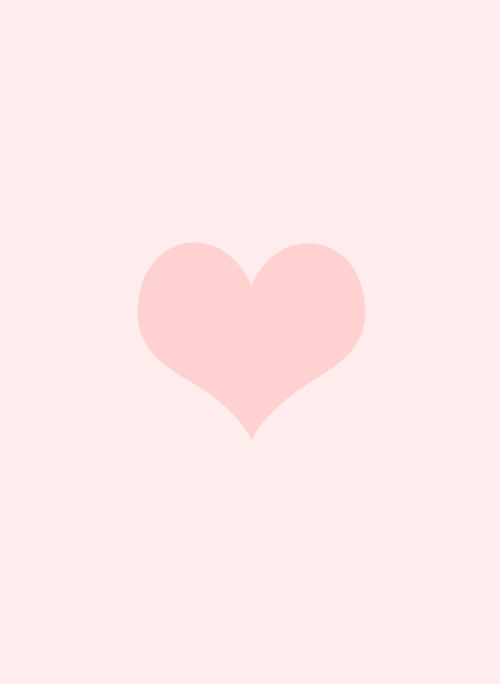「おまえほどの男、殺すには惜しい」と父に言われた敵国の王子の妻になりました
せめて今だけでも、私を「愛している」と錯覚させてほしかった。
ゼインは、短く息を吐いて、私の頬に触れた。
その手は、少しだけ震えていた。
「もちろん、君は俺の妻だ。」
その言葉は、優しさのようでいて、どこか苦しげだった。
本当にそう思ってくれているのか。
それとも「妻だから」という義務の仮面をかぶった優しさなのか――
私は分からなかった。
けれどその時の私は、確かめる勇気も持ち合わせていなかった。
ただ、彼の体温を感じたかった。
その腕の中で、私は「愛されている」と信じたかった。
ゼインが私に顔を近づける。
唇が重なる瞬間、私は瞳を閉じた。
ただただ、私だけを見てほしい。
そう願いながら。
ゼインは、短く息を吐いて、私の頬に触れた。
その手は、少しだけ震えていた。
「もちろん、君は俺の妻だ。」
その言葉は、優しさのようでいて、どこか苦しげだった。
本当にそう思ってくれているのか。
それとも「妻だから」という義務の仮面をかぶった優しさなのか――
私は分からなかった。
けれどその時の私は、確かめる勇気も持ち合わせていなかった。
ただ、彼の体温を感じたかった。
その腕の中で、私は「愛されている」と信じたかった。
ゼインが私に顔を近づける。
唇が重なる瞬間、私は瞳を閉じた。
ただただ、私だけを見てほしい。
そう願いながら。