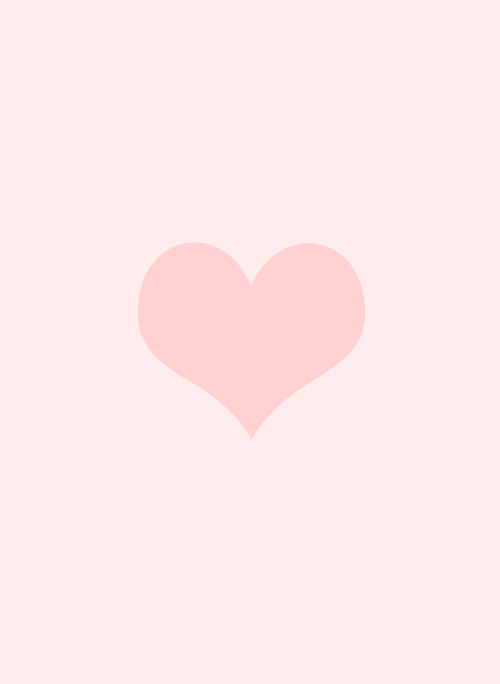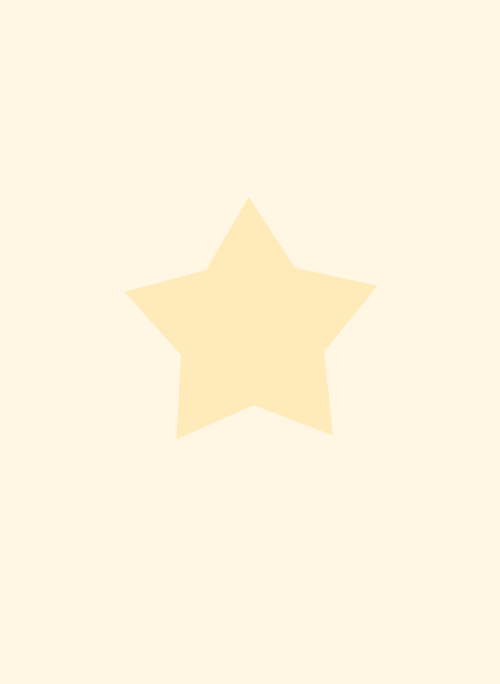オフィスでは忠犬、でも二人きりになると獣でした~年下部下の甘すぎる独占愛~
快感が波のように押し寄せてきて、私は思わずシートにしがみついた。
しばらく余韻に震えていると、藤堂君が静かに自分の指を舐めながら、こう呟いた。
「……甘いな。」
――恥ずかしい。死にたいくらい。
私は咄嗟に彼に背を向けた。
「……藤堂君の、馬鹿っ!」
震える声でそう吐き出すと、彼はため息まじりに言った。
「こうでもしないと、俺のこと、男として見てくれないでしょ?」
痛いところを突かれた気がした。
確かにそうだった。
彼のことを、ずっと“年下で、部下で、わんこ”だと決めつけていた。
でも――奪われた快感は、そんな言い訳ごと全部、壊してしまった。
悔しい。
こんなふうにされて、感じてしまった自分が――悔しくてたまらなかった。
しばらく余韻に震えていると、藤堂君が静かに自分の指を舐めながら、こう呟いた。
「……甘いな。」
――恥ずかしい。死にたいくらい。
私は咄嗟に彼に背を向けた。
「……藤堂君の、馬鹿っ!」
震える声でそう吐き出すと、彼はため息まじりに言った。
「こうでもしないと、俺のこと、男として見てくれないでしょ?」
痛いところを突かれた気がした。
確かにそうだった。
彼のことを、ずっと“年下で、部下で、わんこ”だと決めつけていた。
でも――奪われた快感は、そんな言い訳ごと全部、壊してしまった。
悔しい。
こんなふうにされて、感じてしまった自分が――悔しくてたまらなかった。