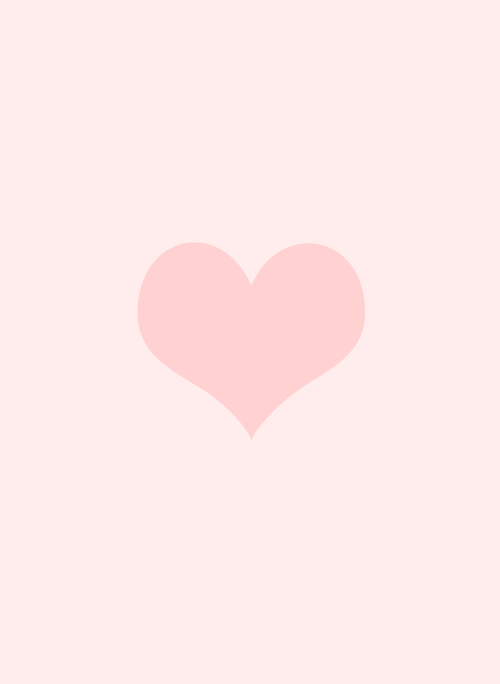君と見た花火は、苦情だらけ
第20話 新しい屋上と、君と見る花火
川辺交流センターの新しい外壁は、朝の光を少しだけ眩しそうに跳ね返していた。
ベージュと淡いグレーのタイル。
ガラス越しに見えるロビーは、以前より天井が高くなり、奥のほうまで柔らかい明かりが伸びている。
入口の自動ドアの横には、真新しいプレートが取り付けられていた。
『川辺交流センター
――君と語りたくなる場所へ。』
「……これ、本当にこのまま行くんですね」
開館前のロビーで、詩織がプレートを見上げながらぼそりと言った。
「最後まで粘ったの、誰でしたっけ」
受付カウンターの奥で名札を並べていた千妃呂が、口元をゆるめる。
「キャッチコピーはもっと短く、って言ったのは私だけど」
「『君と語りたくなる場所』って、ちょっと照れるけど、ここにはぴったりじゃない?」
千妃呂は、カウンターの上にフリーペーパー最新号を並べる。
表紙には、新しいセンターの写真と一緒に、例のコピーが印刷されていた。
『特集:君と語りたくなる場所の使い方』
「これで逃げ道はないですね」
詩織が苦笑したそのとき、自動ドアが静かに開いた。
「おはようございます」
スーツ姿に腕章、ヘルメットを片手に持った一輝が、少し息を弾ませながら入ってくる。
「おはようございます」
詩織は、無意識に背筋を伸ばした。
ロビーをぐるりと見回した一輝の目が、中央の柱の前で止まる。
そこには、一冊の分厚い白い冊子が立てかけられていた。
『川辺センター 記憶のアルバム』
「……ちゃんと、引っ越しできたんですね」
かつて壁いっぱいに貼られていた文章たち。
それらが写真と文字でまとめられ、新しいセンターの一角に居場所をもらっている。
「壁はなくなっちゃったけど、読む人の顔は、またここに集まりますよ」
詩織がそう言うと、一輝は静かにうなずいた。
◇
午前十時。
オープン初日のセンターには、思った以上に多くの人が集まっていた。
子ども連れの親子、買い物帰りのお年寄り、スーツ姿の人たち。
誰もが、少し落ち着かない様子で新しい建物を見上げている。
喫茶コーナーでは、マスターが新しいカウンターにまだ慣れない手つきでカップを並べていた。
「いやあ、前より広くなったけど、ここから見える景色はあんまり変わらないね」
「それがいいんじゃないですか」
一輝が笑う。
「コーヒー飲む場所から見る川が、急に都会っぽくなっても落ち着かないですし」
「それもそうだ」
マスターは、記念すべき一杯目をカウンターに置いた。
◇
そのころ、二階の教室でも準備が進んでいた。
ホワイトボードの上には、『私がアツく語りたい』の文字。
机には、新しい受講生用のノートとペンが並んでいる。
詩織は、教室のドアから廊下をのぞいた。
すでに何人かが入口前でそわそわしている。
「緊張してます?」
いつの間にか後ろにいた千妃呂が、肩を軽く叩く。
「ちょっとだけ。
今日、変なこと言ったらどうしようって」
「大丈夫。
変なこと言っても、『あの講師さん、今日アツかったね』ってネタになります」
励ましなのかどうなのか、微妙な言葉だったが、不思議と気持ちは軽くなった。
◇
講座が始まると、教室はすぐに人でいっぱいになった。
詩織は、いつものように受講生に質問を投げ、ノートに書いてもらいながら進めていく。
「今日は、『このセンターで語りたいもの』をテーマにします」
スライドには、いくつかの写真が映し出された。
かつての壁に貼られていた文章。
喫茶コーナーで笑っている人たち。
そして、書庫で封筒を持ち上げているスーツ姿の男性。
「この人は、『見なかったことにしたい箱を、ちゃんと開けよう』と言いました」
写真の男性――永羽の姿に、教室のあちこちから笑いが漏れる。
「で」
詩織は、黒板の前に戻った。
「今日、私が一番アツく語りたい人は」
教室の視線が、一斉に前へ向く。
「後ろのドアの近くで、『どうか当たりませんように』って顔をしている人です」
みんなが振り返る先で、一輝がぴたりと固まっていた。
「え、ちょっと待ってください」
小声の抗議は、笑いにかき消される。
「川辺センターを『終わらせるかどうか』の話を持ってきたのも、
ここを『使い続ける方法』を一緒に考えてくれたのも、この人です」
詩織は、冗談半分、本気半分のまなざしで一輝を見る。
「せっかくなので、少しだけ語ってもらいましょう」
マイク代わりのペンが差し出される。
◇
一輝は、前に出るつもりはなかった。
気づけば、前に立っていた。
「……相沢です」
自己紹介だけで笑いが起こる。
「僕は、最初、このビルをどうやって『終わらせるか』を考えに来ました」
その言葉に、教室が静かになる。
「でも、皆さんと、ここで出会った人たちのおかげで、
ここをどうやって『使い続けるか』を考えるようになりました」
記憶のアルバムに閉じ込められた文章。
書庫で見つけた封筒。
家族会議のテーブル。
「これからも、このセンターが『温もりを求める瞳』が集まる場所であるように、
できる限りのことをします」
自分でも驚くほど素直な言葉だった。
「その代わり、たまに疲れた顔をしていたら、喫茶コーナーでコーヒーを奢ってください」
教室に再び笑いが広がる。
「それと……」
前列の椅子に座る詩織を見る。
「この人が、『怖い』って言ったときは、一緒に考える人でいたいです」
詩織の目が、わずかに潤んだ。
「仕事のことも、家族のことも、将来のことも。
全部まぜこぜのまま、それでも『一緒にいてよかった』って思える形を、
これからも探していきたいと思っています」
教室のどこかで、誰かがそっとハンカチで目元を押さえた。
◇
夜。
屋上テラスには、小さな花火台が組まれていた。
安全基準をぎりぎりまでクリアした、控えめなサイズの花火。
それでも、川沿いの夜空には十分な光だった。
「大きな花火大会じゃないけど」
詩織が、隣でぽつりと言う。
「今の私たちには、ちょうどいいかも」
「そうですね。
これ以上大きいと、たぶん課長の胃が持ちません」
屋上の端では、永羽が遠巻きに花火台を見守っている。
手には、いつもの銀色のシート。
打ち上がった花火が、小さく夜空に咲いた。
かつて河川敷で見上げた花火より、少し控えめで、少し近い。
「今年は、一緒に見られましたね」
詩織の言葉に、一輝はうなずく。
「途中で仕事に逃げずに済みました」
「途中で怖さに飲まれずに済みました」
ふたりは、顔を見合わせて笑った。
花火の残り香が、夜風に混ざって漂う。
遠くで子どもの歓声が聞こえた。
「……これからのこと、またちゃんと話しましょうね」
詩織が、少しだけ照れた声で言う。
「センターが落ち着いた頃に。
『まぜこぜ案』の続きのページも」
「はい。
そのときまでに、もう少しだけ図面描けるようになっておきます」
「じゃあ私は、文字数オーバーしないように気をつけます」
それは、どこかこの数ヶ月を総括するような宣言だった。
最後の花火が夜空に咲き、静かに散る。
ふたりは肩を並べたまま、その光が消えていくのを見届けた。
――君と見た花火を、これから何度でも語れるように。
新しい屋上の上で、小さな願いが確かに灯っていた。
ベージュと淡いグレーのタイル。
ガラス越しに見えるロビーは、以前より天井が高くなり、奥のほうまで柔らかい明かりが伸びている。
入口の自動ドアの横には、真新しいプレートが取り付けられていた。
『川辺交流センター
――君と語りたくなる場所へ。』
「……これ、本当にこのまま行くんですね」
開館前のロビーで、詩織がプレートを見上げながらぼそりと言った。
「最後まで粘ったの、誰でしたっけ」
受付カウンターの奥で名札を並べていた千妃呂が、口元をゆるめる。
「キャッチコピーはもっと短く、って言ったのは私だけど」
「『君と語りたくなる場所』って、ちょっと照れるけど、ここにはぴったりじゃない?」
千妃呂は、カウンターの上にフリーペーパー最新号を並べる。
表紙には、新しいセンターの写真と一緒に、例のコピーが印刷されていた。
『特集:君と語りたくなる場所の使い方』
「これで逃げ道はないですね」
詩織が苦笑したそのとき、自動ドアが静かに開いた。
「おはようございます」
スーツ姿に腕章、ヘルメットを片手に持った一輝が、少し息を弾ませながら入ってくる。
「おはようございます」
詩織は、無意識に背筋を伸ばした。
ロビーをぐるりと見回した一輝の目が、中央の柱の前で止まる。
そこには、一冊の分厚い白い冊子が立てかけられていた。
『川辺センター 記憶のアルバム』
「……ちゃんと、引っ越しできたんですね」
かつて壁いっぱいに貼られていた文章たち。
それらが写真と文字でまとめられ、新しいセンターの一角に居場所をもらっている。
「壁はなくなっちゃったけど、読む人の顔は、またここに集まりますよ」
詩織がそう言うと、一輝は静かにうなずいた。
◇
午前十時。
オープン初日のセンターには、思った以上に多くの人が集まっていた。
子ども連れの親子、買い物帰りのお年寄り、スーツ姿の人たち。
誰もが、少し落ち着かない様子で新しい建物を見上げている。
喫茶コーナーでは、マスターが新しいカウンターにまだ慣れない手つきでカップを並べていた。
「いやあ、前より広くなったけど、ここから見える景色はあんまり変わらないね」
「それがいいんじゃないですか」
一輝が笑う。
「コーヒー飲む場所から見る川が、急に都会っぽくなっても落ち着かないですし」
「それもそうだ」
マスターは、記念すべき一杯目をカウンターに置いた。
◇
そのころ、二階の教室でも準備が進んでいた。
ホワイトボードの上には、『私がアツく語りたい』の文字。
机には、新しい受講生用のノートとペンが並んでいる。
詩織は、教室のドアから廊下をのぞいた。
すでに何人かが入口前でそわそわしている。
「緊張してます?」
いつの間にか後ろにいた千妃呂が、肩を軽く叩く。
「ちょっとだけ。
今日、変なこと言ったらどうしようって」
「大丈夫。
変なこと言っても、『あの講師さん、今日アツかったね』ってネタになります」
励ましなのかどうなのか、微妙な言葉だったが、不思議と気持ちは軽くなった。
◇
講座が始まると、教室はすぐに人でいっぱいになった。
詩織は、いつものように受講生に質問を投げ、ノートに書いてもらいながら進めていく。
「今日は、『このセンターで語りたいもの』をテーマにします」
スライドには、いくつかの写真が映し出された。
かつての壁に貼られていた文章。
喫茶コーナーで笑っている人たち。
そして、書庫で封筒を持ち上げているスーツ姿の男性。
「この人は、『見なかったことにしたい箱を、ちゃんと開けよう』と言いました」
写真の男性――永羽の姿に、教室のあちこちから笑いが漏れる。
「で」
詩織は、黒板の前に戻った。
「今日、私が一番アツく語りたい人は」
教室の視線が、一斉に前へ向く。
「後ろのドアの近くで、『どうか当たりませんように』って顔をしている人です」
みんなが振り返る先で、一輝がぴたりと固まっていた。
「え、ちょっと待ってください」
小声の抗議は、笑いにかき消される。
「川辺センターを『終わらせるかどうか』の話を持ってきたのも、
ここを『使い続ける方法』を一緒に考えてくれたのも、この人です」
詩織は、冗談半分、本気半分のまなざしで一輝を見る。
「せっかくなので、少しだけ語ってもらいましょう」
マイク代わりのペンが差し出される。
◇
一輝は、前に出るつもりはなかった。
気づけば、前に立っていた。
「……相沢です」
自己紹介だけで笑いが起こる。
「僕は、最初、このビルをどうやって『終わらせるか』を考えに来ました」
その言葉に、教室が静かになる。
「でも、皆さんと、ここで出会った人たちのおかげで、
ここをどうやって『使い続けるか』を考えるようになりました」
記憶のアルバムに閉じ込められた文章。
書庫で見つけた封筒。
家族会議のテーブル。
「これからも、このセンターが『温もりを求める瞳』が集まる場所であるように、
できる限りのことをします」
自分でも驚くほど素直な言葉だった。
「その代わり、たまに疲れた顔をしていたら、喫茶コーナーでコーヒーを奢ってください」
教室に再び笑いが広がる。
「それと……」
前列の椅子に座る詩織を見る。
「この人が、『怖い』って言ったときは、一緒に考える人でいたいです」
詩織の目が、わずかに潤んだ。
「仕事のことも、家族のことも、将来のことも。
全部まぜこぜのまま、それでも『一緒にいてよかった』って思える形を、
これからも探していきたいと思っています」
教室のどこかで、誰かがそっとハンカチで目元を押さえた。
◇
夜。
屋上テラスには、小さな花火台が組まれていた。
安全基準をぎりぎりまでクリアした、控えめなサイズの花火。
それでも、川沿いの夜空には十分な光だった。
「大きな花火大会じゃないけど」
詩織が、隣でぽつりと言う。
「今の私たちには、ちょうどいいかも」
「そうですね。
これ以上大きいと、たぶん課長の胃が持ちません」
屋上の端では、永羽が遠巻きに花火台を見守っている。
手には、いつもの銀色のシート。
打ち上がった花火が、小さく夜空に咲いた。
かつて河川敷で見上げた花火より、少し控えめで、少し近い。
「今年は、一緒に見られましたね」
詩織の言葉に、一輝はうなずく。
「途中で仕事に逃げずに済みました」
「途中で怖さに飲まれずに済みました」
ふたりは、顔を見合わせて笑った。
花火の残り香が、夜風に混ざって漂う。
遠くで子どもの歓声が聞こえた。
「……これからのこと、またちゃんと話しましょうね」
詩織が、少しだけ照れた声で言う。
「センターが落ち着いた頃に。
『まぜこぜ案』の続きのページも」
「はい。
そのときまでに、もう少しだけ図面描けるようになっておきます」
「じゃあ私は、文字数オーバーしないように気をつけます」
それは、どこかこの数ヶ月を総括するような宣言だった。
最後の花火が夜空に咲き、静かに散る。
ふたりは肩を並べたまま、その光が消えていくのを見届けた。
――君と見た花火を、これから何度でも語れるように。
新しい屋上の上で、小さな願いが確かに灯っていた。