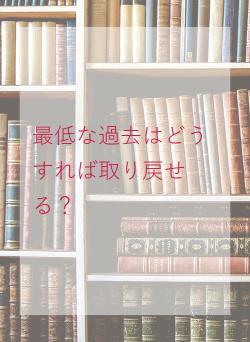雨の日に、後輩と
第5話 たまには寄りかかるのも
「佐伯さんはなんで男避けをしているんですか? きっかけとかあるんですか?」
時任おすすめのイタリアン居酒屋にてスパークリングワインで乾杯し、前菜として頼んだサーモンのカルパッチョをひとくち食べたところで、ずばっと尋ねられた。
酔いが進んだとことで様子を窺いつつさりげなくというわけではなく、いきなりの直球である。
いま? と思いながら凛は正直に答えた。
「……いままで男のひとと、付き合いたいと思ったことがなかったからだと思う」
ワイングラスを手にしていた時任は、目を瞬いた。
「何か理由がありますか」
「すごい、ぐいぐい聞いてくる」
「聞きますよ。俺にとって、すごく重要なところなので」
凛は返答を考えながら、グラスに手を伸ばした。上の空だったせいで、思いっきりぐいっと煽ってしまう。ばちばちと口の中で泡が弾けるのを痛く感じながら、声に出さずに叫んでいた。
(ジャブを打たない! 意外。もっとそつがないタイプかと思っていたのに。告白してしまったから、もう毒を喰らわば皿までということ?)
食い気味の態度に動揺し、目の前のカルパッチョの皿をぐいっと押し出した。
「まず食べて」
「わかりました。じゃあ、三皿食べたらもう一回聞きます」
宣言するなり、時任は店員を呼び止めて追加注文をしていた。トリッパのヴェネツィア風、サルティンボッカ、ラザニア。
(全部美味しそう)
趣味がいいなと思っていたら、ちらっと凛を見た時任が心を見透かしたように「全部美味しいですよ」と言ってきた。
「今日は味がわからないかもしれないけど。たぶん、ずっと上の空……」
呟きながらグラスを傾けているのを見て、凛は意図せぬ「待て」をしてしまったと気付き、口を開く。
「すみません『三皿食べてから』は私が課した条件ではないので、なしなし。もったいぶるような理由は何もないですよ。そうですね……私、もともとひとりでいるのが苦にならないタイプなんだと思います。でも、寂しいとか、大切にされてみたいという感情はあるんだなって今日すごく感じました。親切にされるとぐらっときてしまって、こういう関係性というのはいいものなんだなって自然に」
どことなく、男性との間に壁を築きながら過ごしてきた凛は、時任のような距離の詰められ方をしたのは初めての経験だった。
それが、思っていたほど全然嫌ではなかったのだ。
(キスにも抵抗感がなくて……)
自分にとってまったく他人だった相手と、不意に距離が縮まる。
その結果として凛は、自分の中にある当たり前の感情から目を逸らし、無いものとしてきたことに気づいてしまった。
雨が降る休日に、落ち着ける部屋で他愛もない会話をしてありあわせのもので作った料理を食べる。雨が晴れたら、夕方からふらっと二人で肩を並べて近所のレストランまで出かける。そうやって、家族ではない相手と親密な距離で過ごすのがとても楽しいということ。
この時間が、終わらないでずっと続いて欲しいと願っているということ。
「ぐらっときたっていうことは、もう一押しなのかなぁ」
わざと声に出して思案している時任を前にして、凛はふきだした。
「そういう手の内は相手の前で明かさないんじゃないかなぁ。時任さんみたいに器用なタイプなら、何かあると思うんですけど。搦め手のような策が」
「佐伯さんは、俺をなんだと思っているんですか」
「百戦錬磨」
ジロッと睨まれて凛は口をつぐむ。黙らせておいて、時任は噛んで含めるように言った。
「俺がそれを言われて嬉しい男ではないと、そろそろわかってほしいですね」
「はい。すみませんでした」
でも、本当のところ時任さんがどういうひとかはわかってないんですよねえ、と凛は胸の中で呟く。
わかっていないのは、知らない相手だからだ。
知るためには距離を詰める必要があり、それは危険と隣合わせで勇気がいることでもある。
(付き合ってから本性が出る男。見る目がなかったと後悔しても遅い。社内恋愛はリスク。もっとよく知ってからでなくては……踏み出す足を止めてしまう理由はいくらでも思いつく。世の恋人たちは、どういうときにこの一線を越えようと決断するんだろう)
ぐるぐると考えているうちに、凛は料理を食べ進めつつ杯を重ねてしまった。
けらけら笑いながらおかわりをしようとしたところで、時任にストップをかけられて「次は水で」とオーダーを変えられる。
「それ飲んだら帰りますよ。酔わないといろいろ勢いがつかないのはわかりましたけど、俺は酔った女性に手を出す気はありません。酒を言い訳にはさせない」
少しだけひんやりとした空気を漂わせながら時任はそう言って、会計を済ませていた。
いつもなら「いくら? 払う払う」と騒ぐ凛だが、この日はてきぱきとした時任に任せてぼーっと見ていた。
酔っているのはたしかだったが、正体を失うほど酔っていたわけではない。
ただ、何かと尽くしてくれる時任に寄りかかるのも悪くないなと思ってしまったのだ。
帰り道、時任から手を繋がれたときには、自分も指を絡ませてしまった。
「ちょっと買い物。待っててください」
と、コンビニ前で別れて待つ間にもぐるぐる考えたが、この短い待ち時間でさえ切ないという感覚に、結論が出てしまっていた。
(五年前から知り合いだった人の中にも、これほど近く感じたひとはいなかったわけで。たぶん時任さんは私にとってとても相性の良いひとなんだと思う)
これ以上の人にはもう巡り合わないかもしれないという予感は、どこか怖い。
本当に、落ちてしまった気がする。策略だったらどうしよう?
マンションについて、階段をのぼり、部屋の前まで来てしまった。
先にどうぞと促されて中に入ったら、後ろでドアを閉めて鍵をかける音に続いて、背中から抱きすくめられる。
「佐伯さん、いま転びかけた」
色っぽい理由ではないらしい。凛も気づいていた。足元が危なっかしすぎる。
「そんな気がしました」
時任に体重を預けたら、足から力が抜けてしまってもう立つのも難しくなってしまった。酔いが全身にまわっている。そこまで飲んだつもりはない、というのは凛の思い込みで、立派な酔っぱらいであった。
凛の体がぐだぐだなのは伝わったようで、時任は一度凛を両腕に抱え上げた。いわゆるお姫様抱っこである。
「すごい……! こんなことってある?」
「笑い事じゃなくて。下ろしますよ。靴を脱ぎましょう」
玄関先に凛をそっと下ろして、一緒にしゃがみこんだ時任がそのまま凛の靴を脱がせる。世話をされっぱなしの凛は、時任の首に両腕をまわした。目の前にあったので、そうしたくなったのだ。離れがたい気持ち。
「佐伯さん……!」
「キスしませんか?」
ぽろっと思いつきを口にしたら、その場で押し倒されて唇を奪われた。映画の中で見かけるシーンのように、胸が締め付けられるな一瞬の後。
凛の上で、時任は切ないため息をこぼして体を起こした。
「今日はここまで。自分としては、既に十分な進展と、考えていまして」
押し殺したような声で耳元で囁かれ、凛はぐっと歯を食いしばって吐息をこらえた。
それから、おそるおそる呼吸を再開する。
「お好きなようにしてください」
「佐伯さん、酔ってます、よね。判断力残って言ってますか」
「言い分としてずるいのは承知の上ですが、こうしないと思い切りがつかなくて、ですね。でも、飲む前から気持ちは固まっていたので、大丈夫です。同意の上です」
「……安心しました」
安堵に満ちたような柔らかな声はとても近く。
時任は、もう一度優しく唇を重ねてきた。
けれどすぐにため息とともに体を起こし、凛を抱え上げて部屋まで進む。
断腸の思いというほど苦しげに、宣言をした。
「今日はここまでです。これ以上に関して、俺『が』同意できません」
鉄の意志だった。
時任おすすめのイタリアン居酒屋にてスパークリングワインで乾杯し、前菜として頼んだサーモンのカルパッチョをひとくち食べたところで、ずばっと尋ねられた。
酔いが進んだとことで様子を窺いつつさりげなくというわけではなく、いきなりの直球である。
いま? と思いながら凛は正直に答えた。
「……いままで男のひとと、付き合いたいと思ったことがなかったからだと思う」
ワイングラスを手にしていた時任は、目を瞬いた。
「何か理由がありますか」
「すごい、ぐいぐい聞いてくる」
「聞きますよ。俺にとって、すごく重要なところなので」
凛は返答を考えながら、グラスに手を伸ばした。上の空だったせいで、思いっきりぐいっと煽ってしまう。ばちばちと口の中で泡が弾けるのを痛く感じながら、声に出さずに叫んでいた。
(ジャブを打たない! 意外。もっとそつがないタイプかと思っていたのに。告白してしまったから、もう毒を喰らわば皿までということ?)
食い気味の態度に動揺し、目の前のカルパッチョの皿をぐいっと押し出した。
「まず食べて」
「わかりました。じゃあ、三皿食べたらもう一回聞きます」
宣言するなり、時任は店員を呼び止めて追加注文をしていた。トリッパのヴェネツィア風、サルティンボッカ、ラザニア。
(全部美味しそう)
趣味がいいなと思っていたら、ちらっと凛を見た時任が心を見透かしたように「全部美味しいですよ」と言ってきた。
「今日は味がわからないかもしれないけど。たぶん、ずっと上の空……」
呟きながらグラスを傾けているのを見て、凛は意図せぬ「待て」をしてしまったと気付き、口を開く。
「すみません『三皿食べてから』は私が課した条件ではないので、なしなし。もったいぶるような理由は何もないですよ。そうですね……私、もともとひとりでいるのが苦にならないタイプなんだと思います。でも、寂しいとか、大切にされてみたいという感情はあるんだなって今日すごく感じました。親切にされるとぐらっときてしまって、こういう関係性というのはいいものなんだなって自然に」
どことなく、男性との間に壁を築きながら過ごしてきた凛は、時任のような距離の詰められ方をしたのは初めての経験だった。
それが、思っていたほど全然嫌ではなかったのだ。
(キスにも抵抗感がなくて……)
自分にとってまったく他人だった相手と、不意に距離が縮まる。
その結果として凛は、自分の中にある当たり前の感情から目を逸らし、無いものとしてきたことに気づいてしまった。
雨が降る休日に、落ち着ける部屋で他愛もない会話をしてありあわせのもので作った料理を食べる。雨が晴れたら、夕方からふらっと二人で肩を並べて近所のレストランまで出かける。そうやって、家族ではない相手と親密な距離で過ごすのがとても楽しいということ。
この時間が、終わらないでずっと続いて欲しいと願っているということ。
「ぐらっときたっていうことは、もう一押しなのかなぁ」
わざと声に出して思案している時任を前にして、凛はふきだした。
「そういう手の内は相手の前で明かさないんじゃないかなぁ。時任さんみたいに器用なタイプなら、何かあると思うんですけど。搦め手のような策が」
「佐伯さんは、俺をなんだと思っているんですか」
「百戦錬磨」
ジロッと睨まれて凛は口をつぐむ。黙らせておいて、時任は噛んで含めるように言った。
「俺がそれを言われて嬉しい男ではないと、そろそろわかってほしいですね」
「はい。すみませんでした」
でも、本当のところ時任さんがどういうひとかはわかってないんですよねえ、と凛は胸の中で呟く。
わかっていないのは、知らない相手だからだ。
知るためには距離を詰める必要があり、それは危険と隣合わせで勇気がいることでもある。
(付き合ってから本性が出る男。見る目がなかったと後悔しても遅い。社内恋愛はリスク。もっとよく知ってからでなくては……踏み出す足を止めてしまう理由はいくらでも思いつく。世の恋人たちは、どういうときにこの一線を越えようと決断するんだろう)
ぐるぐると考えているうちに、凛は料理を食べ進めつつ杯を重ねてしまった。
けらけら笑いながらおかわりをしようとしたところで、時任にストップをかけられて「次は水で」とオーダーを変えられる。
「それ飲んだら帰りますよ。酔わないといろいろ勢いがつかないのはわかりましたけど、俺は酔った女性に手を出す気はありません。酒を言い訳にはさせない」
少しだけひんやりとした空気を漂わせながら時任はそう言って、会計を済ませていた。
いつもなら「いくら? 払う払う」と騒ぐ凛だが、この日はてきぱきとした時任に任せてぼーっと見ていた。
酔っているのはたしかだったが、正体を失うほど酔っていたわけではない。
ただ、何かと尽くしてくれる時任に寄りかかるのも悪くないなと思ってしまったのだ。
帰り道、時任から手を繋がれたときには、自分も指を絡ませてしまった。
「ちょっと買い物。待っててください」
と、コンビニ前で別れて待つ間にもぐるぐる考えたが、この短い待ち時間でさえ切ないという感覚に、結論が出てしまっていた。
(五年前から知り合いだった人の中にも、これほど近く感じたひとはいなかったわけで。たぶん時任さんは私にとってとても相性の良いひとなんだと思う)
これ以上の人にはもう巡り合わないかもしれないという予感は、どこか怖い。
本当に、落ちてしまった気がする。策略だったらどうしよう?
マンションについて、階段をのぼり、部屋の前まで来てしまった。
先にどうぞと促されて中に入ったら、後ろでドアを閉めて鍵をかける音に続いて、背中から抱きすくめられる。
「佐伯さん、いま転びかけた」
色っぽい理由ではないらしい。凛も気づいていた。足元が危なっかしすぎる。
「そんな気がしました」
時任に体重を預けたら、足から力が抜けてしまってもう立つのも難しくなってしまった。酔いが全身にまわっている。そこまで飲んだつもりはない、というのは凛の思い込みで、立派な酔っぱらいであった。
凛の体がぐだぐだなのは伝わったようで、時任は一度凛を両腕に抱え上げた。いわゆるお姫様抱っこである。
「すごい……! こんなことってある?」
「笑い事じゃなくて。下ろしますよ。靴を脱ぎましょう」
玄関先に凛をそっと下ろして、一緒にしゃがみこんだ時任がそのまま凛の靴を脱がせる。世話をされっぱなしの凛は、時任の首に両腕をまわした。目の前にあったので、そうしたくなったのだ。離れがたい気持ち。
「佐伯さん……!」
「キスしませんか?」
ぽろっと思いつきを口にしたら、その場で押し倒されて唇を奪われた。映画の中で見かけるシーンのように、胸が締め付けられるな一瞬の後。
凛の上で、時任は切ないため息をこぼして体を起こした。
「今日はここまで。自分としては、既に十分な進展と、考えていまして」
押し殺したような声で耳元で囁かれ、凛はぐっと歯を食いしばって吐息をこらえた。
それから、おそるおそる呼吸を再開する。
「お好きなようにしてください」
「佐伯さん、酔ってます、よね。判断力残って言ってますか」
「言い分としてずるいのは承知の上ですが、こうしないと思い切りがつかなくて、ですね。でも、飲む前から気持ちは固まっていたので、大丈夫です。同意の上です」
「……安心しました」
安堵に満ちたような柔らかな声はとても近く。
時任は、もう一度優しく唇を重ねてきた。
けれどすぐにため息とともに体を起こし、凛を抱え上げて部屋まで進む。
断腸の思いというほど苦しげに、宣言をした。
「今日はここまでです。これ以上に関して、俺『が』同意できません」
鉄の意志だった。