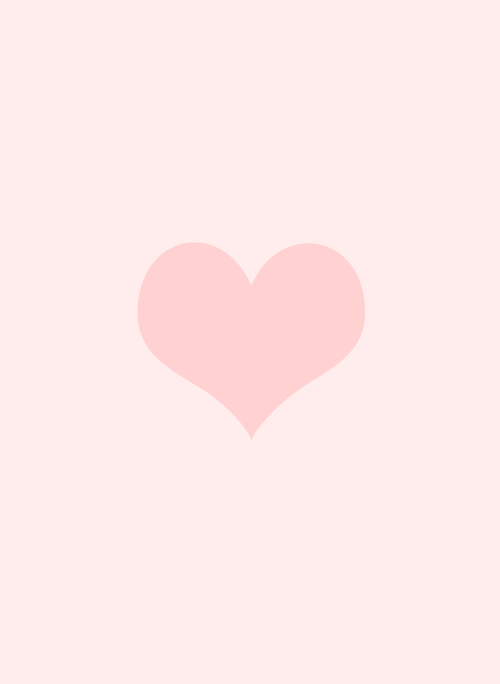ラベンダーミストムーンストーンの花嫁
第20話 同じ台所で、同じ明日
秋の土曜、昼の光がやわらかい。ミッドナイト・ムーンストーンの屋上ガーデンは、風が少しだけ冷えていて、葉の匂いがした。
白い椅子は二十脚。並び方は、きっちりではなく、ほどほど。裕喬がメジャーで測ろうとしたのを、優が止めたからだ。
「一センチずれたら、世界が終わります?」
「終わりません」
裕喬は、言い切ってから一呼吸置き、メジャーをしまった。しまい方が丁寧すぎて、それが笑いを誘う。
「じゃあ、今日は終わらない日にしましょう」
優が言うと、裕喬はうなずいた。声は出さないが、うなずきだけで返事の種類が分かる人だった。
その一週間前の金曜、午後三時。下町の区役所の窓口で、優と颯人は並んで立っていた。婚姻届の紙は薄いのに、ペンの先がやけに重い。
颯人の署名は迷いなく、優の署名は最後の一画で少しだけ震えた。受付印が押された瞬間、優は息を吸い直した。三か月の約束の紙よりも、今はこの一枚が現実だった。
優は式の準備をしながら、何度も裾を握り直してしまう。
自分の手は、朝から小麦粉と砂糖に触れてきた手だ。ホテルのスイートで出される白い手袋とは、住む場所が違う。
けれど今日は、そこに引かれた線を越えて、同じ場所に立つ。
「優」
呼ばれて顔を上げると、颯人が目の前にいた。タキシードは着ているのに、襟のあたりが落ち着かない。鏡の前で何度も結び直した顔だ。
「……その、苦しくないですか」
優がネクタイの結び目を指で押すと、颯人は小さく息を吐いた。
「苦しいです。でも、ここで倒れたら、あなたに抱えられる」
「抱えません。救急車を呼びます」
「冷静ですね」
「冷静でいないと、手順が崩れます」
優が言うと、颯人は笑った。笑い方が、昨日よりも軽い。体のどこかに余っていた緊張が、もう要らなくなったみたいに。
花のアーチの横で、七夕が水筒を抱えて立っていた。銀色の保冷ボトルが、二本。三本。いつの間にか増えている。
「飲んで。喉が乾いたら、言葉が噛むから」
七夕は、そう言って優にストロー付きのボトルを渡した。渡し方が早い。断る隙がない。
「ありがとうございます」
「礼は、あとで。今は飲む」
優が飲むと、七夕は次に颯人へボトルを差し出した。
「支配人も。今日は、偉い人より、喉が弱い人」
颯人は一瞬だけ目を丸くしてから、素直に受け取った。
「……助かります」
「はい。言えた」
七夕は満足げにうなずき、また別のボトルを抱え直した。
少し離れた場所で、史周がギターを抱えて、弦を軽く鳴らしている。音は小さく、風に溶ける。
「鳴らしすぎると、泣くからな」
史周が独り言みたいに言うと、ちほが袖を引っぱった。
「泣くのは勝手だけど、泣くならあと。今、泣いたら化粧落ちる」
ちほは自分の目尻を指で押さえながら言った。押さえ方が、もう泣いている。
「泣いてない」
「声が泣いてる」
史周が言うと、ちほは睨んだ。睨みながら、優の髪飾りの位置だけは直してくれる。
「ずれてる。……こう。ほら、まっすぐ」
直された瞬間、優の胸がふっと軽くなった。言い方は乱暴でも、手はやさしい。
式が始まる直前、ホテルの正面から運ばれてきた箱がひとつあった。金色の紋章が入った封が貼られている。
裕喬が受け取りを躊躇したのを、颯人が止めた。
「開けます」
颯人は封を破り、箱の中を見た。中身は、大きな花輪と、カード。
『盛大に。家の名に恥のない形で』
文字が、硬い。紙も硬い。匂いまで硬い気がした。
優は、言葉が出ないまま、指先を握りしめた。下町の菓子店で育った自分が、ここに立つこと自体が、誰かにとっては“恥”の範囲に入るのだろうか。
「優」
颯人が、カードを折りたたんで、優の手に触れない距離で止めた。
「これは、屋上には置きません」
言い方が、穏やかなのに、決定の速度が速い。
「でも……」
優が言いかけると、颯人は視線を逸らさずに続けた。
「あなたを隠すための花は、いりません。あなたを見せるための椅子が、ここにあります」
颯人の指が、並んだ椅子を示した。厨房の仲間。清掃の仲間。受付の子。夜勤の警備員。優が名前を知っている人たちが、ちゃんと座っている。
誰も、優を値踏みする目をしていない。今日の風の匂いと同じで、ただそこにいる。
司会役の裕喬が、マイクを持つ手を落ち着かせた。
「それでは――」
声が、かすれない。準備は前日に終えている声だ。
誓いの言葉は、長くなかった。颯人は“守る”と言わない代わりに、具体的なことを言った。
「朝、あなたが起きる前に、洗い物を終える」
誰かが小さく笑った。優は思わず顔を赤くする。
颯人は続けた。
「あなたが菓子を焼く日に、仕込み台の横に立って、温度計を持つ」
今度は、厨房の仲間が笑った。温度計係の仕事量を知っている笑いだ。
「あなたが泣きそうなとき、黙って背中を押さない。ちゃんと名前を呼ぶ」
その一言だけは、笑いが起きなかった。風の音が、少し大きくなった気がした。
優の番になって、優は息を吸った。甘い匂いがする。自分が焼いたものの匂いだ。
「私は、颯人さんの“ありがとう”を、減らさない」
颯人の眉が、わずかに上がった。
「忙しいときほど、言わなくなるから。私が、言わせます」
七夕が小さく拍手をした。史周が肩を揺らして笑う。ちほは、泣きながら笑っている。
「それから……家の格とか、服の値段とか、そういう数字で私を測る人がいても。私は、菓子の焼き色で自分を決めます」
優は言い切って、颯人を見た。颯人は、まるで当たり前のようにうなずいた。
「うん。あなたの焼き色は、あなたの名前だ」
指輪の石は、淡い青紫の霧を閉じ込めたまま、太陽の下で少しだけ明るくなった。
「ラベンダーミストムーンストーン」
颯人が、照れを隠さずにその名を言う。長い名前を、間違えないように。
優は笑って、指を差し出した。
「覚えました?」
「毎日言います」
「……毎日?」
優が問い返すと、颯人は真顔でうなずいた。
「毎日、結婚したから」
その言い方が、子どもの理屈みたいで、優は吹き出した。笑いながら泣きそうになって、七夕の水筒に助けられた。
式が終わると、屋上の隅に小さなテーブルが並んだ。豪華なケーキではない。優が焼いた小さな焼き菓子が、星形の皿に並んでいる。
「これ、“ラベンダーミストムーンストーン”です」
優が言うと、清掃の仲間が目を丸くした。
「石、食べていいの?」
「食べていい石です。歯に優しいです」
優が言うと、颯人が横で真面目に補足した。
「歯科検診は、来月予約済みです」
裕喬が目を閉じて、深くうなずいた。
「段取りが強い」
夕方、下町のムーンストーン洋菓子店。
店先には、ホテルの制服と、清掃のエプロンと、私服が入り混じっていた。身分の線が、ここではほどける。
優はオーブンの扉を開け、焼き上がりを確かめる。香りが、店の外まで流れていく。
「ねえ、支配人。今日くらい、手を出すな」
ちほが言い、颯人の手首を軽く叩いた。叩き方が、遠慮がない。
「支配人じゃないです。今日は、夫です」
颯人はそう言って、エプロンを結び直した。結び目が曲がっている。
優が直そうとすると、颯人が先に言った。
「曲がってます?」
「曲がってます」
「直してください」
言葉が素直すぎて、優は笑った。下町の店で、跡取りの夫が、結び目を直してもらう。誰が想像しただろう。
夜、ふたりが帰ったのは、ホテルのスイートではなかった。
駅から歩いて十分の、普通の部屋。キッチンは狭い。シンクは浅い。換気扇の音は、ちょっと大きい。
「……これが、うち」
優が言うと、颯人は靴を揃えた。揃える指が、少し震えている。
「ここなら、あなたの歩幅に合わせられる」
「合わせなくていいです。私も、颯人さんの歩幅、覚えます」
優がそう言うと、颯人は肩を落として笑った。笑い方が、屋上よりも家っぽい。
夕飯の皿を流しに運び、ふたりで並んで立つ。今日は、すすぎ係も洗い係も、交代制だ。
颯人がスポンジを握ると、泡がすぐに増えた。増え方が豪快で、優が止める。
「……洗剤、出しすぎです」
「これくらいが安心だと思って」
「安心は泡じゃありません」
優が水を足し、泡を調整すると、颯人は真剣に見ている。経営会議の資料を見る目と同じだ。
「覚えます」
「覚えること、多いですね」
「あなたのことは、増えてもいい」
最後の皿を立てかけて、優が蛇口を締める。
颯人は泡だらけの手のまま、優の横顔に向けて言った。
「今日も、ありがとう」
優は、乾いた布巾を渡した。
「こちらこそ。……明日も言います?」
颯人は布巾を受け取り、目を細めた。
「明日も。明後日も。言い逃げしません」
「じゃあ、私は毎朝、焼き色を外しません」
優が言うと、颯人はうなずいた。
そのうなずきに、家の格も、席の順番も、もう入っていなかった。
狭いキッチンの蛍光灯の下、指輪の淡い霧が、静かに光った。
同じ台所で、同じ明日を迎える。
それが、身分の差を越えるやり方だと、優は今夜、腹の底で理解した。
白い椅子は二十脚。並び方は、きっちりではなく、ほどほど。裕喬がメジャーで測ろうとしたのを、優が止めたからだ。
「一センチずれたら、世界が終わります?」
「終わりません」
裕喬は、言い切ってから一呼吸置き、メジャーをしまった。しまい方が丁寧すぎて、それが笑いを誘う。
「じゃあ、今日は終わらない日にしましょう」
優が言うと、裕喬はうなずいた。声は出さないが、うなずきだけで返事の種類が分かる人だった。
その一週間前の金曜、午後三時。下町の区役所の窓口で、優と颯人は並んで立っていた。婚姻届の紙は薄いのに、ペンの先がやけに重い。
颯人の署名は迷いなく、優の署名は最後の一画で少しだけ震えた。受付印が押された瞬間、優は息を吸い直した。三か月の約束の紙よりも、今はこの一枚が現実だった。
優は式の準備をしながら、何度も裾を握り直してしまう。
自分の手は、朝から小麦粉と砂糖に触れてきた手だ。ホテルのスイートで出される白い手袋とは、住む場所が違う。
けれど今日は、そこに引かれた線を越えて、同じ場所に立つ。
「優」
呼ばれて顔を上げると、颯人が目の前にいた。タキシードは着ているのに、襟のあたりが落ち着かない。鏡の前で何度も結び直した顔だ。
「……その、苦しくないですか」
優がネクタイの結び目を指で押すと、颯人は小さく息を吐いた。
「苦しいです。でも、ここで倒れたら、あなたに抱えられる」
「抱えません。救急車を呼びます」
「冷静ですね」
「冷静でいないと、手順が崩れます」
優が言うと、颯人は笑った。笑い方が、昨日よりも軽い。体のどこかに余っていた緊張が、もう要らなくなったみたいに。
花のアーチの横で、七夕が水筒を抱えて立っていた。銀色の保冷ボトルが、二本。三本。いつの間にか増えている。
「飲んで。喉が乾いたら、言葉が噛むから」
七夕は、そう言って優にストロー付きのボトルを渡した。渡し方が早い。断る隙がない。
「ありがとうございます」
「礼は、あとで。今は飲む」
優が飲むと、七夕は次に颯人へボトルを差し出した。
「支配人も。今日は、偉い人より、喉が弱い人」
颯人は一瞬だけ目を丸くしてから、素直に受け取った。
「……助かります」
「はい。言えた」
七夕は満足げにうなずき、また別のボトルを抱え直した。
少し離れた場所で、史周がギターを抱えて、弦を軽く鳴らしている。音は小さく、風に溶ける。
「鳴らしすぎると、泣くからな」
史周が独り言みたいに言うと、ちほが袖を引っぱった。
「泣くのは勝手だけど、泣くならあと。今、泣いたら化粧落ちる」
ちほは自分の目尻を指で押さえながら言った。押さえ方が、もう泣いている。
「泣いてない」
「声が泣いてる」
史周が言うと、ちほは睨んだ。睨みながら、優の髪飾りの位置だけは直してくれる。
「ずれてる。……こう。ほら、まっすぐ」
直された瞬間、優の胸がふっと軽くなった。言い方は乱暴でも、手はやさしい。
式が始まる直前、ホテルの正面から運ばれてきた箱がひとつあった。金色の紋章が入った封が貼られている。
裕喬が受け取りを躊躇したのを、颯人が止めた。
「開けます」
颯人は封を破り、箱の中を見た。中身は、大きな花輪と、カード。
『盛大に。家の名に恥のない形で』
文字が、硬い。紙も硬い。匂いまで硬い気がした。
優は、言葉が出ないまま、指先を握りしめた。下町の菓子店で育った自分が、ここに立つこと自体が、誰かにとっては“恥”の範囲に入るのだろうか。
「優」
颯人が、カードを折りたたんで、優の手に触れない距離で止めた。
「これは、屋上には置きません」
言い方が、穏やかなのに、決定の速度が速い。
「でも……」
優が言いかけると、颯人は視線を逸らさずに続けた。
「あなたを隠すための花は、いりません。あなたを見せるための椅子が、ここにあります」
颯人の指が、並んだ椅子を示した。厨房の仲間。清掃の仲間。受付の子。夜勤の警備員。優が名前を知っている人たちが、ちゃんと座っている。
誰も、優を値踏みする目をしていない。今日の風の匂いと同じで、ただそこにいる。
司会役の裕喬が、マイクを持つ手を落ち着かせた。
「それでは――」
声が、かすれない。準備は前日に終えている声だ。
誓いの言葉は、長くなかった。颯人は“守る”と言わない代わりに、具体的なことを言った。
「朝、あなたが起きる前に、洗い物を終える」
誰かが小さく笑った。優は思わず顔を赤くする。
颯人は続けた。
「あなたが菓子を焼く日に、仕込み台の横に立って、温度計を持つ」
今度は、厨房の仲間が笑った。温度計係の仕事量を知っている笑いだ。
「あなたが泣きそうなとき、黙って背中を押さない。ちゃんと名前を呼ぶ」
その一言だけは、笑いが起きなかった。風の音が、少し大きくなった気がした。
優の番になって、優は息を吸った。甘い匂いがする。自分が焼いたものの匂いだ。
「私は、颯人さんの“ありがとう”を、減らさない」
颯人の眉が、わずかに上がった。
「忙しいときほど、言わなくなるから。私が、言わせます」
七夕が小さく拍手をした。史周が肩を揺らして笑う。ちほは、泣きながら笑っている。
「それから……家の格とか、服の値段とか、そういう数字で私を測る人がいても。私は、菓子の焼き色で自分を決めます」
優は言い切って、颯人を見た。颯人は、まるで当たり前のようにうなずいた。
「うん。あなたの焼き色は、あなたの名前だ」
指輪の石は、淡い青紫の霧を閉じ込めたまま、太陽の下で少しだけ明るくなった。
「ラベンダーミストムーンストーン」
颯人が、照れを隠さずにその名を言う。長い名前を、間違えないように。
優は笑って、指を差し出した。
「覚えました?」
「毎日言います」
「……毎日?」
優が問い返すと、颯人は真顔でうなずいた。
「毎日、結婚したから」
その言い方が、子どもの理屈みたいで、優は吹き出した。笑いながら泣きそうになって、七夕の水筒に助けられた。
式が終わると、屋上の隅に小さなテーブルが並んだ。豪華なケーキではない。優が焼いた小さな焼き菓子が、星形の皿に並んでいる。
「これ、“ラベンダーミストムーンストーン”です」
優が言うと、清掃の仲間が目を丸くした。
「石、食べていいの?」
「食べていい石です。歯に優しいです」
優が言うと、颯人が横で真面目に補足した。
「歯科検診は、来月予約済みです」
裕喬が目を閉じて、深くうなずいた。
「段取りが強い」
夕方、下町のムーンストーン洋菓子店。
店先には、ホテルの制服と、清掃のエプロンと、私服が入り混じっていた。身分の線が、ここではほどける。
優はオーブンの扉を開け、焼き上がりを確かめる。香りが、店の外まで流れていく。
「ねえ、支配人。今日くらい、手を出すな」
ちほが言い、颯人の手首を軽く叩いた。叩き方が、遠慮がない。
「支配人じゃないです。今日は、夫です」
颯人はそう言って、エプロンを結び直した。結び目が曲がっている。
優が直そうとすると、颯人が先に言った。
「曲がってます?」
「曲がってます」
「直してください」
言葉が素直すぎて、優は笑った。下町の店で、跡取りの夫が、結び目を直してもらう。誰が想像しただろう。
夜、ふたりが帰ったのは、ホテルのスイートではなかった。
駅から歩いて十分の、普通の部屋。キッチンは狭い。シンクは浅い。換気扇の音は、ちょっと大きい。
「……これが、うち」
優が言うと、颯人は靴を揃えた。揃える指が、少し震えている。
「ここなら、あなたの歩幅に合わせられる」
「合わせなくていいです。私も、颯人さんの歩幅、覚えます」
優がそう言うと、颯人は肩を落として笑った。笑い方が、屋上よりも家っぽい。
夕飯の皿を流しに運び、ふたりで並んで立つ。今日は、すすぎ係も洗い係も、交代制だ。
颯人がスポンジを握ると、泡がすぐに増えた。増え方が豪快で、優が止める。
「……洗剤、出しすぎです」
「これくらいが安心だと思って」
「安心は泡じゃありません」
優が水を足し、泡を調整すると、颯人は真剣に見ている。経営会議の資料を見る目と同じだ。
「覚えます」
「覚えること、多いですね」
「あなたのことは、増えてもいい」
最後の皿を立てかけて、優が蛇口を締める。
颯人は泡だらけの手のまま、優の横顔に向けて言った。
「今日も、ありがとう」
優は、乾いた布巾を渡した。
「こちらこそ。……明日も言います?」
颯人は布巾を受け取り、目を細めた。
「明日も。明後日も。言い逃げしません」
「じゃあ、私は毎朝、焼き色を外しません」
優が言うと、颯人はうなずいた。
そのうなずきに、家の格も、席の順番も、もう入っていなかった。
狭いキッチンの蛍光灯の下、指輪の淡い霧が、静かに光った。
同じ台所で、同じ明日を迎える。
それが、身分の差を越えるやり方だと、優は今夜、腹の底で理解した。