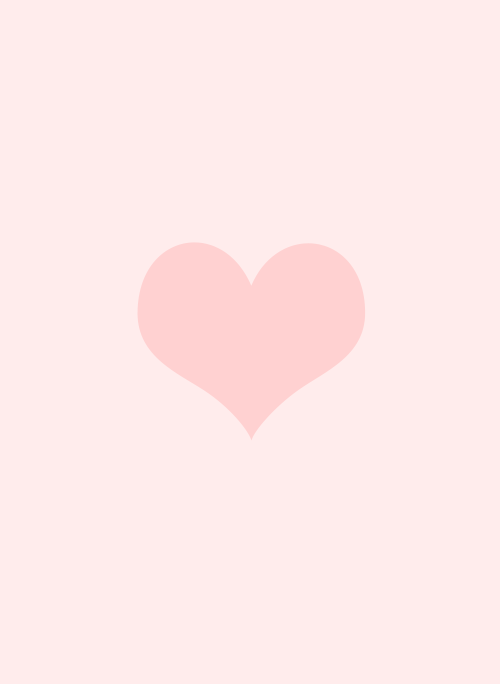最強令嬢は国外追放されたので、隣国で自由に暮らすことにした
宵闇が迫るシルヴィヌ王宮はまさに今、嫌な熱気に包まれていた。
王太子主催の舞踏会が開催されていた大広間で、一人の麗人――アルテミア・ジンクールへの糾弾が始まったのだ。
公爵家の令嬢であるアルテミアは騎士団長でもある父の鍛錬に付き合い、幼い頃より剣術や武術を嗜み成長してきた。長身で、動きやすいパンツスタイルを好む彼女は細い身体で舞うように剣を振う。優雅な動きで相手を倒すその姿は、まるで神話に登場する戦いの女神そのもの。そんな彼女は周囲から「麗しの騎士令嬢」と称賛されていた。
今夜の彼女の装いは、襟元にアクアマリンのビーズを施したシンプルながら美しいシルエットのジャケットとスラックスといった組み合わせ。ドレスコードの王太子の瞳の色となる、青を基調としたものだった。銀の長い髪も青のリボンで一つにまとめている。
質実剛健、華美な場所を好まないアルテミアはめったに夜会には出席しない。しかし、今夜この場所に身を置いたのには理由があった。父が国王らの諸国外遊に帯同した為、不在だったのだ。本来であればジンクール家は欠席すると伝えれば良いだけだ。しかし今回だけは様子が違った。招待状に『必ず屋敷から一名は出席せよ』との文が添えられていたのだ。
ジンクール家は父一人子一人。
仕方なくアルテミアは父の代理として出席していたのだが、夜会には珍しく、また美しい彼女の存在は人々の注目を浴びてしまう。一目彼女の姿を見ようと周囲は早速人集りが出来ていた。
しかし壇上の玉座に座る王太子のリオナスだけは異なった。彼女を視界に認めると、目を吊り上げて立ち上がったのだ。
「アルテミア! 貴様、その格好はどういうつもりだ!」
彼のその剣幕に、華やかな空気が一転する。
「珍しく舞踏会に出席したかと思えばこの有様。令嬢が男装で出席するとは何事か!これは王族……私に対する不敬の現れであるぞ!」
アルテミアが着ている服は、王都一番と謳われる職人が仕立てた最高級品である。しかし舞踏会に関わらず殆どの令嬢は、ドレスを着用するのが慣例だ。
彼女は王太子の視線を受け止めると、恭しく頭を垂れた。
「殿下、私に不敬の意図などございません」
アルテミアの凛とした声が、静まり返った大広間に響く。
「舞踏会の案内にはドレスコードが『青を基調とする装い』とありましたが、『ドレスを着用すべし』という文言はございませんでした。ですので私もこの通り青をあしらった装いにて登城させて頂いたのです」
襟元を指でなぞると、アクアマリンの淡い青がゆらゆら光を反射する。その所作の美しさに周囲からは賛辞のため息が漏れるが、それがますますリオナスを逆上させる。
「黙れ! 言葉遊びをするな!いつもいつもそんな真似ばかりする、貴様のその態度が問題だと言うのだ!」
リオナスは近くに控えていた従者に合図すると、分厚い書類を受け取った。
「いい機会だ。ここで今迄貴様が何をしてきたのかを教えてやろう」
書類の束を叩くと、顔を歪めて口角を上げる。
「まず貴様は先日、女人禁制にも関わらず騎士団の訓練に参加し、部隊長を打ち負かしたと聞いている。これは騎士団の秩序を著しく乱す行為である!」
アルテミアは肩をすくめた。
「女性が在籍していないだけで、そもそも騎士団に女人禁制という規則はございません。それに父――騎士団長にきちんと確認を取った上で参加をしておりました。騎士団に所属しておらずとも、護身術の一環として剣技を磨くことは推奨されるべきだと思いますので」
アルテミアは何度か騎士団の入団試験を受けている。しかし試験を順調に進んでも、最終審査で「騎士としての適性にそぐわず」という内容でいつも落とされていた。因みにその合否を下すのは騎士団長ではなく王族――王太子の役割である。
「また部隊長殿の件ですが、私が勝ったというのは単にその演習での結果でごさいます。特に罪に問われるべき事柄ではないかと存じます」
リオナスは奥歯を噛みしめた。部隊長は彼の剣の指南役でもあった。
『王太子の指南役よりもアルテミアの剣技の腕が上回った』
たった一度の演習結果であったとしても、その事実は、彼を師と仰ぐリオナス自身まで威厳を汚されたと思わせるには充分だった。
「ならば、ミユーリ男爵令嬢の件。これについてはどうだ! 貴様は先月、彼女に求婚しようとした紳士を侮辱しその尊厳を傷つけたと言うではないか!そればかりか己の性別を詐称して彼女に求婚しようとしたことまで伝え聞いているぞ!」
アルテミアは、首を傾げるとわずかに目を細めた。
「どこでその様な話になったのか……。説明をさせて頂きますと、私は彼女に求婚などしておりません。ただ、『強引な方法で迫られ困惑している』との相談されましたので、相手方との話し合いの場を設けたにだけに過ぎません」
「話し合いだと?相手は骨を折る大怪我をしたと訴えているのだぞ!」
「それは話し合いもそこそこに、先方がこちらに突進されてきたのです」
ミユーリ男爵令嬢は爵位こそ低いものの「シルヴィヌの妖精」と賞賛される美貌の持ち主であり、アルテミアの友人でもあった。そんな彼女に求婚する者は多く、その中の一人が件の紳士だった。
侯爵家の次男である事を傘にするその男は、他の求婚者やミユーリ家に不当な圧力を掛け結婚の承諾を迫ってきた。そんなやり口に恐怖を覚えた彼女が頼ったのもまたアルテミアだった。
まずは男と話し合いをしようと場を設けたのだが、当日やって来た男はなぜか、「やられる前にやってやる!」と真っ赤な顔で咆哮するとアルテミアに飛び掛って来て――。
「咄嗟に避けたところ、その勢いのまま転倒されたのでございます。まさかそれで骨を折られるとは……。席に着くこともなくお帰りになられたので、どうしたのかとは思っておりましたが、そういう事でしたか。お気の毒と言えばよいのかなんというか」
「――――!!貴様はああ言えばこう言うと!もうへらず口は沢山だ!」
アルテミアが冷静に論破すればするほどリオナスは地団駄を踏んで逆上する。そして遂には大きく手を振り払うと、声高らかに宣言をした。
「今、国王陛下は諸国へ外交に赴き不在である。しかしこの数々の問題を巻き起こし秩序を乱す者には裁きを与えなければならない。そこでこの私が国王代理として、ここに裁きを宣言する!」
リオナスは手に持った書状を力強く頭上に掲げた。
「アルテミア・ジンクール! 貴様を不敬罪と秩序撹乱罪により、本日をもって国外追放とする!」
――論理が破綻している。
王太子の所業に周囲はざわめき、固唾を呑んだ。
アルテミアは父に連れられ幼い頃より王宮に出入りしており、リオナスとは幼馴染であることは周知の事実だ。しかしいつの頃からか、彼は事あるごとにアルテミアを攻撃する様になっていた。
「承知いたしました、リオナス殿下。国外追放の刑、謹んでお受けいたします」
アルテミアが深緑色の瞳をリオナスに向けると、あちこちからは悲鳴が上がる。
「宣言したからには、二度とこのシルヴィヌ王国の地に足を踏み入れることを許さない。よいな!」
「勿論です。それでは私は、本日中にでも国境を越えましょう。殿下がこの先心穏やかにお過ごしになられることを、遠い異国の地でお祈り申し上げます」
アルテミアは深く一礼をする。そして艶やかに微笑むと、一切の未練を見せることなく、颯爽と広間を後にしていった。
◆◆◆
屋敷に戻るが否やアルテミアは、寝室に籠って旅支度をし始めた。数着の着替えに、本を数冊。路銀の足しになるように、宝石の一つも持って行こうか。目についた物を適当に詰め込むと、小さなバッグはあっという間に一杯になる。
「こんなものかな?」
最後に相棒でもある細剣に手を伸ばすと、寝室の扉が勢い良く開かれた。
「アルテミア様!どうか早まらないでください!!」
彼女の侍女であるリイネが、大きな琥珀色の瞳に涙を浮かべて飛び込んできたのだ。
「旦那様がこの知らせを聞いたらどんなに嘆かれることか!今早馬を飛ばしますのでどうか早まった事だけはお辞めください!」
「いいんだよ、リイネ。もう決めた事なんだ」
「ですが!」
「それにこれは私にとって、好機でもあるんだよ」
アルテミシアは手に取った細剣を、荷物をまとめた鞄の傍らに静かに置いた。
「え?」
思いがけない主人の言葉にリイネは目を丸くする。
「この国は、私にとって少し窮屈だと感じていたからね。他の国で自由に暮らすのも悪くはないかなって思ったんだ」
「ですが、旦那様もお寂しがられますよ?屋敷の皆だって……」
「父上には騎士団の皆がいるから大丈夫さ。それにきっと私の気持ちを分かってくださる。屋敷の皆だってそうだ」
「ですが、アルテミア様は働いたことがないではありませんか。知らない土地……しかも他の国で暮らすにはお金が必要ですよ?」
「それはまあ、どうにかなるさ。とにかく私はこの国ではないどこかに行って見たいのだよ」
確かにアルテミアの表情は、今迄見たことのないほどに晴れやかに輝いている。これ以上何を言っても彼女の決意は変わらないのだろう。
「わかりました」
リイネは大きくため息をつくと、アルテミアの鞄の横に、勢いよく自分の小さな鞄を置いた。
「でしたら私も、ついて参ります!」
「何だって?!だめだ。リイネを巻き込むわけにはいかないよ」
アルテミアの言葉を遮るように、リイネが早口で捲し立てる。
「私の生きがいは仕事です。そして私の仕事はアルテミシア様のお世話をすることです。それを取り上げようとなさるのですか?!お優しいアルテミア様ならそんなことはなさいませんよね?それともアルテミア様は私の生きがいを奪うというおつもりなんですか?!」
今迄に見たことのないリイネの剣幕に、アルテミアは一瞬言葉を失った。けれど彼女の強い決意と忠誠心を目の当たりにして、アルテミシアは「……全く。仕方がないな」と苦笑した。
「そこまで言うのなら、良いだろう。ただし、異国で苦労しても、もはや故国へ帰ることは許されないのだよ?」
「勿論!それは覚悟の上です」
満面の笑みで力こぶを作る年若い侍女は、新天地での生活にきっと彩りを添えてくれるだろう。
こうして夜更け過ぎ、書き置きをしたアルテミアはリイネを伴ってジンクールの屋敷を静かに後にした。
「ところでアルテミア様。行く当てはあるのですか?」
「そうだな……。オルテガ皇国はどうだろう?」
夜明けすぐに乗り込んだ辻馬車の中、リイネに訪ねられたアルテミアが答える。隣国オルテガ皇国はシルヴィヌ王国の周辺国のなかでもひときわ繁栄していると評判だ。
「オルテガ皇国なら、きっと女二人でも生活に困らずに暮らせる仕事がきっとあるはずさ」
多少の苦労はあるかもしれない。けれどこれからは自由が待っている。アルテミアの胸には、これから始まる新しく人生への期待が膨らんでいた。
◆◆◆
辻馬車に揺られること丸三日目。隣国オルテガ皇国の王都についたアルテミア達は、街の様子に目を見開いていた。シルヴィヌ王国も活気に満ちてはいたが、オルテガ皇国の王都の規模はそれ以上だ。様々な商店が建ち並び、あちこちから威勢の良い売り子の声と、食欲をそそる香りが漂ってくる。
「はぁぁ。これは噂以上の賑やかさですね」
リイネが感嘆のため息を漏らすと同時に、お腹の虫がグゥと鳴る。
「よし、それではまずは腹ごしらえでもしようか」
近くの食堂に入り、取りあえず手頃な値段の品を注文すると辺りを見回す。繁盛店らしく、席はほぼ満席で騒がしい。暫くして香ばしい湯気が立ちのぼる肉野菜炒めが席に届いたので、二人は早速頬張った。
「んー!これはたまりませんね!!」
「本当だ。初めて食べたが、これは美味しいな」
異国のスパイスが効いた肉は噛むほどに旨味が飛び出し、脂を纏った青菜はシャクシャクと歯触りが良い。どこか粗っぽさもあるがそれもまた味わい。ジンクールの屋敷はおろか、シルヴィヌ王国では食べることの無かった料理に舌鼓を打っていると、陶器が割れる音と男達の怒声が店内に響いた。
「何だと?!やんのかコラァ!!」
床に落ちた料理と砕けた皿、そして取っ組み合う男達。あまりの剣幕に店主は無ずすべもなくオロオロしている。
「うわ、昼間から酔っ払いの喧嘩でしょうか。アルテミア様。目を合わせてはいけませんよ」
眉を潜めたリイネが囁くのと、アルテミアが立ち上がったのは、ほぼ同時の事だった。
「君達は何を揉めているんだ?」
アルテミアは騒動の元に近づくと声をかけた。突然現れた見知らぬ若者に男達は一緒ギョッとした顔をしたが、すぐに声を荒げてテーブルの上に残っていた食器を床に投げつけた。
「うるせえな腐れ若造め!優男は引っ込んでろ!!」
「そうはいかない。店の皆に迷惑だ。喧嘩をするなら他所でやってくれないか」
「何だと?!」
飛び掛かる男達をひらりと躱すと、アルテミアは素早く後ろに回ってその首筋に手刀を振り下ろす。すると男達は「ぐえっ」とおかしな声を上げそのまま床に膝から崩れ落ちた。
「悪いが我々も食事を楽しみたいからね。暫く静かにしていてくれないか」
店主から借りたロープで手際良く気を失った男達を柱に縛り付けていると、騒ぎを聞きつけたのか帯刀した騎士と思しき人々が店に集まってきた。
「店で暴れている者がいると聞いたが……これは君がやったのか?」
「すまない。余りにうるさいものだから、つい手が出てしまった。……何か私も罰を与えられるだろうか?」
「いやいやとんでもない!この男達には元々手配書が出ていたんだ。捕まえてもらって、むしろ感謝状ものだよ!」
その中で、赤みを帯びた金髪の人懐こい顔立ちの男が明るい笑顔でアルテミアに近づいてきた。
「それにしても見事な腕前だ! もしかして君、明日の騎士団入団試験を受けに来たのかい?」
アルテミアは首を傾げた。
「入団試験?」
「あれ、違うのかい?オルテガ皇国騎士団は、国籍問わず才能ある者を積極的に受け入れる為、年に一回入団試験を行っているんだ。君のその腕前なら、合格すること間違いないと思ったんだけどな」
(騎士団……。合格すれば、仕事を探す必要もないな)
「アルテミア様いけません!右も左も分からない異国で騎士団など、危険すぎますわ!」
リイネが小声でアルテミアの袖を掴む。
しかしアルテミアはリーネを制し、金髪の男に向き直った。
「試験の話を詳しく教えてくれないか?私の名はアルテミ……いや、アルテだ。そしてこっちは妹のリー」
「いいね!そうこなくっちゃ。よろしくお二人さん。俺の名前はローレンだ」
アレンの話を聞いて早速アルテミアは騎士団への試験に応募することにした。騎士団に属することができれば給金は勿論、住居も借り上げてもらうことができる。しかも騎士団員になることはシルヴィヌ王国では叶えることはできなかった夢でもある。これから生活基盤を整えていかなければならないアルテミア達にとっては、何もかもが有り難い条件だった。
「それにしてもローレン様に偽名は使うわ『妹だ』なんて紹介するわ……私は肝を冷やしましたよ」
宿の部屋でため息をつくリイネを、アルテミアは面白そうに眺めている。
「新規一転、名前も変えてみたくてね。それに女が伴も連れずに二人きりでいるんだ。姉妹としておいたほうが余計な詮索されなくていいだろう?それとも私と姉妹になるのは嫌かい?」
「そ、そんなことはございません!けれど、何だか恐れ多くて」
「ならいいじゃないか。明日は試験だ。必ず合格してみせるから、リイネはどこに住むか考えておきなさい」
アルテミアは早々と布団の中に潜り込んだ。リイネはそんな主人の様子を呆れたように見つめた後、そっと蝋燭の火吹き消した。
◆◆◆
その一週間後、試験に見事合格したアルテミア――アルテは騎士団の服に身を包んでいた。試験結果は歴代最高、満場一致での合格だった。
早速今日から街の見廻りを担当することになったアルテミアは、鍛錬場でペアとなる人物の到着を待っていた。
「やあアルテ!待たせたな」
現れたのはあの日騎士団について教えてくれたローレンだ。
「どうだい?新しい生活は。家はもう決まったんだっけ?」
「ああ。お陰様で住みやすい家が見つかったよ。妹も喜んでいる」
「それは良かった」
シルヴィヌ王国では単身者は寮に入るが、ここオルテガ皇国では各自が希望した住居が与えられる。その点だけでも故国とは大きく異なる点だった。それにここは人種だけでなく性別にも差別がない。寛容さも持ち合わせているからこそ活気も生まれるのだろう。アルテミアは一人納得しながらも、それにしては女性の騎士団員の姿が見つからないことが気になった。
「ところで、女性騎士団員はとこにいるんだ?」
「え?何を言っているんだ?騎士団員は男だけだろう?」
「え?」
アルテミアは身体がぴしりと固まった。
「女性団員は、いないのか?」
「ああ」
「……どうしてだ?」
「まあ、規則でそうなっているからな。それに女性はか弱いだろう?力仕事の騎士は難しいだろう」
「では、私は?」
「アルテ?アルテはだって男だろう?まあ男の割には華奢だけど、その分剣の腕はピカイチだからな。……あ、もしかして女に間違えられそうになったのか?」
ローレンが心配そうな顔でアルテミアを覗き込む。
「あ、いや、大丈夫。間違えられたりは、していない。しかし今後女性団員を入団させる予定はないのか?」
「どうだろう?規則が変われば話はまた違ってくるだろうけど、なんせ議会を通して決定することだから中々難しいんじゃないのかな。」
「そうか……」
ポツリと呟いたアルテミアは考えていた。
そう言えば試験の際に、性別を問われることはなかった。女性団員は認められていないが、アルテミアは何の疑いもなく団員として入団することができた。それは即ちどういうことが言うと……
(男性だと思われているなら、それでもいいか)
アルテミアが出した結論は、酷く単純なものだった。生活基盤も整えたばかりし、別に女性として扱われたい訳でもない。ならば暫くは問題もないだろう。
しかしこの判断が、これから大きな騒動になっていく事を彼女はまだ知る由もないのだった。
王太子主催の舞踏会が開催されていた大広間で、一人の麗人――アルテミア・ジンクールへの糾弾が始まったのだ。
公爵家の令嬢であるアルテミアは騎士団長でもある父の鍛錬に付き合い、幼い頃より剣術や武術を嗜み成長してきた。長身で、動きやすいパンツスタイルを好む彼女は細い身体で舞うように剣を振う。優雅な動きで相手を倒すその姿は、まるで神話に登場する戦いの女神そのもの。そんな彼女は周囲から「麗しの騎士令嬢」と称賛されていた。
今夜の彼女の装いは、襟元にアクアマリンのビーズを施したシンプルながら美しいシルエットのジャケットとスラックスといった組み合わせ。ドレスコードの王太子の瞳の色となる、青を基調としたものだった。銀の長い髪も青のリボンで一つにまとめている。
質実剛健、華美な場所を好まないアルテミアはめったに夜会には出席しない。しかし、今夜この場所に身を置いたのには理由があった。父が国王らの諸国外遊に帯同した為、不在だったのだ。本来であればジンクール家は欠席すると伝えれば良いだけだ。しかし今回だけは様子が違った。招待状に『必ず屋敷から一名は出席せよ』との文が添えられていたのだ。
ジンクール家は父一人子一人。
仕方なくアルテミアは父の代理として出席していたのだが、夜会には珍しく、また美しい彼女の存在は人々の注目を浴びてしまう。一目彼女の姿を見ようと周囲は早速人集りが出来ていた。
しかし壇上の玉座に座る王太子のリオナスだけは異なった。彼女を視界に認めると、目を吊り上げて立ち上がったのだ。
「アルテミア! 貴様、その格好はどういうつもりだ!」
彼のその剣幕に、華やかな空気が一転する。
「珍しく舞踏会に出席したかと思えばこの有様。令嬢が男装で出席するとは何事か!これは王族……私に対する不敬の現れであるぞ!」
アルテミアが着ている服は、王都一番と謳われる職人が仕立てた最高級品である。しかし舞踏会に関わらず殆どの令嬢は、ドレスを着用するのが慣例だ。
彼女は王太子の視線を受け止めると、恭しく頭を垂れた。
「殿下、私に不敬の意図などございません」
アルテミアの凛とした声が、静まり返った大広間に響く。
「舞踏会の案内にはドレスコードが『青を基調とする装い』とありましたが、『ドレスを着用すべし』という文言はございませんでした。ですので私もこの通り青をあしらった装いにて登城させて頂いたのです」
襟元を指でなぞると、アクアマリンの淡い青がゆらゆら光を反射する。その所作の美しさに周囲からは賛辞のため息が漏れるが、それがますますリオナスを逆上させる。
「黙れ! 言葉遊びをするな!いつもいつもそんな真似ばかりする、貴様のその態度が問題だと言うのだ!」
リオナスは近くに控えていた従者に合図すると、分厚い書類を受け取った。
「いい機会だ。ここで今迄貴様が何をしてきたのかを教えてやろう」
書類の束を叩くと、顔を歪めて口角を上げる。
「まず貴様は先日、女人禁制にも関わらず騎士団の訓練に参加し、部隊長を打ち負かしたと聞いている。これは騎士団の秩序を著しく乱す行為である!」
アルテミアは肩をすくめた。
「女性が在籍していないだけで、そもそも騎士団に女人禁制という規則はございません。それに父――騎士団長にきちんと確認を取った上で参加をしておりました。騎士団に所属しておらずとも、護身術の一環として剣技を磨くことは推奨されるべきだと思いますので」
アルテミアは何度か騎士団の入団試験を受けている。しかし試験を順調に進んでも、最終審査で「騎士としての適性にそぐわず」という内容でいつも落とされていた。因みにその合否を下すのは騎士団長ではなく王族――王太子の役割である。
「また部隊長殿の件ですが、私が勝ったというのは単にその演習での結果でごさいます。特に罪に問われるべき事柄ではないかと存じます」
リオナスは奥歯を噛みしめた。部隊長は彼の剣の指南役でもあった。
『王太子の指南役よりもアルテミアの剣技の腕が上回った』
たった一度の演習結果であったとしても、その事実は、彼を師と仰ぐリオナス自身まで威厳を汚されたと思わせるには充分だった。
「ならば、ミユーリ男爵令嬢の件。これについてはどうだ! 貴様は先月、彼女に求婚しようとした紳士を侮辱しその尊厳を傷つけたと言うではないか!そればかりか己の性別を詐称して彼女に求婚しようとしたことまで伝え聞いているぞ!」
アルテミアは、首を傾げるとわずかに目を細めた。
「どこでその様な話になったのか……。説明をさせて頂きますと、私は彼女に求婚などしておりません。ただ、『強引な方法で迫られ困惑している』との相談されましたので、相手方との話し合いの場を設けたにだけに過ぎません」
「話し合いだと?相手は骨を折る大怪我をしたと訴えているのだぞ!」
「それは話し合いもそこそこに、先方がこちらに突進されてきたのです」
ミユーリ男爵令嬢は爵位こそ低いものの「シルヴィヌの妖精」と賞賛される美貌の持ち主であり、アルテミアの友人でもあった。そんな彼女に求婚する者は多く、その中の一人が件の紳士だった。
侯爵家の次男である事を傘にするその男は、他の求婚者やミユーリ家に不当な圧力を掛け結婚の承諾を迫ってきた。そんなやり口に恐怖を覚えた彼女が頼ったのもまたアルテミアだった。
まずは男と話し合いをしようと場を設けたのだが、当日やって来た男はなぜか、「やられる前にやってやる!」と真っ赤な顔で咆哮するとアルテミアに飛び掛って来て――。
「咄嗟に避けたところ、その勢いのまま転倒されたのでございます。まさかそれで骨を折られるとは……。席に着くこともなくお帰りになられたので、どうしたのかとは思っておりましたが、そういう事でしたか。お気の毒と言えばよいのかなんというか」
「――――!!貴様はああ言えばこう言うと!もうへらず口は沢山だ!」
アルテミアが冷静に論破すればするほどリオナスは地団駄を踏んで逆上する。そして遂には大きく手を振り払うと、声高らかに宣言をした。
「今、国王陛下は諸国へ外交に赴き不在である。しかしこの数々の問題を巻き起こし秩序を乱す者には裁きを与えなければならない。そこでこの私が国王代理として、ここに裁きを宣言する!」
リオナスは手に持った書状を力強く頭上に掲げた。
「アルテミア・ジンクール! 貴様を不敬罪と秩序撹乱罪により、本日をもって国外追放とする!」
――論理が破綻している。
王太子の所業に周囲はざわめき、固唾を呑んだ。
アルテミアは父に連れられ幼い頃より王宮に出入りしており、リオナスとは幼馴染であることは周知の事実だ。しかしいつの頃からか、彼は事あるごとにアルテミアを攻撃する様になっていた。
「承知いたしました、リオナス殿下。国外追放の刑、謹んでお受けいたします」
アルテミアが深緑色の瞳をリオナスに向けると、あちこちからは悲鳴が上がる。
「宣言したからには、二度とこのシルヴィヌ王国の地に足を踏み入れることを許さない。よいな!」
「勿論です。それでは私は、本日中にでも国境を越えましょう。殿下がこの先心穏やかにお過ごしになられることを、遠い異国の地でお祈り申し上げます」
アルテミアは深く一礼をする。そして艶やかに微笑むと、一切の未練を見せることなく、颯爽と広間を後にしていった。
◆◆◆
屋敷に戻るが否やアルテミアは、寝室に籠って旅支度をし始めた。数着の着替えに、本を数冊。路銀の足しになるように、宝石の一つも持って行こうか。目についた物を適当に詰め込むと、小さなバッグはあっという間に一杯になる。
「こんなものかな?」
最後に相棒でもある細剣に手を伸ばすと、寝室の扉が勢い良く開かれた。
「アルテミア様!どうか早まらないでください!!」
彼女の侍女であるリイネが、大きな琥珀色の瞳に涙を浮かべて飛び込んできたのだ。
「旦那様がこの知らせを聞いたらどんなに嘆かれることか!今早馬を飛ばしますのでどうか早まった事だけはお辞めください!」
「いいんだよ、リイネ。もう決めた事なんだ」
「ですが!」
「それにこれは私にとって、好機でもあるんだよ」
アルテミシアは手に取った細剣を、荷物をまとめた鞄の傍らに静かに置いた。
「え?」
思いがけない主人の言葉にリイネは目を丸くする。
「この国は、私にとって少し窮屈だと感じていたからね。他の国で自由に暮らすのも悪くはないかなって思ったんだ」
「ですが、旦那様もお寂しがられますよ?屋敷の皆だって……」
「父上には騎士団の皆がいるから大丈夫さ。それにきっと私の気持ちを分かってくださる。屋敷の皆だってそうだ」
「ですが、アルテミア様は働いたことがないではありませんか。知らない土地……しかも他の国で暮らすにはお金が必要ですよ?」
「それはまあ、どうにかなるさ。とにかく私はこの国ではないどこかに行って見たいのだよ」
確かにアルテミアの表情は、今迄見たことのないほどに晴れやかに輝いている。これ以上何を言っても彼女の決意は変わらないのだろう。
「わかりました」
リイネは大きくため息をつくと、アルテミアの鞄の横に、勢いよく自分の小さな鞄を置いた。
「でしたら私も、ついて参ります!」
「何だって?!だめだ。リイネを巻き込むわけにはいかないよ」
アルテミアの言葉を遮るように、リイネが早口で捲し立てる。
「私の生きがいは仕事です。そして私の仕事はアルテミシア様のお世話をすることです。それを取り上げようとなさるのですか?!お優しいアルテミア様ならそんなことはなさいませんよね?それともアルテミア様は私の生きがいを奪うというおつもりなんですか?!」
今迄に見たことのないリイネの剣幕に、アルテミアは一瞬言葉を失った。けれど彼女の強い決意と忠誠心を目の当たりにして、アルテミシアは「……全く。仕方がないな」と苦笑した。
「そこまで言うのなら、良いだろう。ただし、異国で苦労しても、もはや故国へ帰ることは許されないのだよ?」
「勿論!それは覚悟の上です」
満面の笑みで力こぶを作る年若い侍女は、新天地での生活にきっと彩りを添えてくれるだろう。
こうして夜更け過ぎ、書き置きをしたアルテミアはリイネを伴ってジンクールの屋敷を静かに後にした。
「ところでアルテミア様。行く当てはあるのですか?」
「そうだな……。オルテガ皇国はどうだろう?」
夜明けすぐに乗り込んだ辻馬車の中、リイネに訪ねられたアルテミアが答える。隣国オルテガ皇国はシルヴィヌ王国の周辺国のなかでもひときわ繁栄していると評判だ。
「オルテガ皇国なら、きっと女二人でも生活に困らずに暮らせる仕事がきっとあるはずさ」
多少の苦労はあるかもしれない。けれどこれからは自由が待っている。アルテミアの胸には、これから始まる新しく人生への期待が膨らんでいた。
◆◆◆
辻馬車に揺られること丸三日目。隣国オルテガ皇国の王都についたアルテミア達は、街の様子に目を見開いていた。シルヴィヌ王国も活気に満ちてはいたが、オルテガ皇国の王都の規模はそれ以上だ。様々な商店が建ち並び、あちこちから威勢の良い売り子の声と、食欲をそそる香りが漂ってくる。
「はぁぁ。これは噂以上の賑やかさですね」
リイネが感嘆のため息を漏らすと同時に、お腹の虫がグゥと鳴る。
「よし、それではまずは腹ごしらえでもしようか」
近くの食堂に入り、取りあえず手頃な値段の品を注文すると辺りを見回す。繁盛店らしく、席はほぼ満席で騒がしい。暫くして香ばしい湯気が立ちのぼる肉野菜炒めが席に届いたので、二人は早速頬張った。
「んー!これはたまりませんね!!」
「本当だ。初めて食べたが、これは美味しいな」
異国のスパイスが効いた肉は噛むほどに旨味が飛び出し、脂を纏った青菜はシャクシャクと歯触りが良い。どこか粗っぽさもあるがそれもまた味わい。ジンクールの屋敷はおろか、シルヴィヌ王国では食べることの無かった料理に舌鼓を打っていると、陶器が割れる音と男達の怒声が店内に響いた。
「何だと?!やんのかコラァ!!」
床に落ちた料理と砕けた皿、そして取っ組み合う男達。あまりの剣幕に店主は無ずすべもなくオロオロしている。
「うわ、昼間から酔っ払いの喧嘩でしょうか。アルテミア様。目を合わせてはいけませんよ」
眉を潜めたリイネが囁くのと、アルテミアが立ち上がったのは、ほぼ同時の事だった。
「君達は何を揉めているんだ?」
アルテミアは騒動の元に近づくと声をかけた。突然現れた見知らぬ若者に男達は一緒ギョッとした顔をしたが、すぐに声を荒げてテーブルの上に残っていた食器を床に投げつけた。
「うるせえな腐れ若造め!優男は引っ込んでろ!!」
「そうはいかない。店の皆に迷惑だ。喧嘩をするなら他所でやってくれないか」
「何だと?!」
飛び掛かる男達をひらりと躱すと、アルテミアは素早く後ろに回ってその首筋に手刀を振り下ろす。すると男達は「ぐえっ」とおかしな声を上げそのまま床に膝から崩れ落ちた。
「悪いが我々も食事を楽しみたいからね。暫く静かにしていてくれないか」
店主から借りたロープで手際良く気を失った男達を柱に縛り付けていると、騒ぎを聞きつけたのか帯刀した騎士と思しき人々が店に集まってきた。
「店で暴れている者がいると聞いたが……これは君がやったのか?」
「すまない。余りにうるさいものだから、つい手が出てしまった。……何か私も罰を与えられるだろうか?」
「いやいやとんでもない!この男達には元々手配書が出ていたんだ。捕まえてもらって、むしろ感謝状ものだよ!」
その中で、赤みを帯びた金髪の人懐こい顔立ちの男が明るい笑顔でアルテミアに近づいてきた。
「それにしても見事な腕前だ! もしかして君、明日の騎士団入団試験を受けに来たのかい?」
アルテミアは首を傾げた。
「入団試験?」
「あれ、違うのかい?オルテガ皇国騎士団は、国籍問わず才能ある者を積極的に受け入れる為、年に一回入団試験を行っているんだ。君のその腕前なら、合格すること間違いないと思ったんだけどな」
(騎士団……。合格すれば、仕事を探す必要もないな)
「アルテミア様いけません!右も左も分からない異国で騎士団など、危険すぎますわ!」
リイネが小声でアルテミアの袖を掴む。
しかしアルテミアはリーネを制し、金髪の男に向き直った。
「試験の話を詳しく教えてくれないか?私の名はアルテミ……いや、アルテだ。そしてこっちは妹のリー」
「いいね!そうこなくっちゃ。よろしくお二人さん。俺の名前はローレンだ」
アレンの話を聞いて早速アルテミアは騎士団への試験に応募することにした。騎士団に属することができれば給金は勿論、住居も借り上げてもらうことができる。しかも騎士団員になることはシルヴィヌ王国では叶えることはできなかった夢でもある。これから生活基盤を整えていかなければならないアルテミア達にとっては、何もかもが有り難い条件だった。
「それにしてもローレン様に偽名は使うわ『妹だ』なんて紹介するわ……私は肝を冷やしましたよ」
宿の部屋でため息をつくリイネを、アルテミアは面白そうに眺めている。
「新規一転、名前も変えてみたくてね。それに女が伴も連れずに二人きりでいるんだ。姉妹としておいたほうが余計な詮索されなくていいだろう?それとも私と姉妹になるのは嫌かい?」
「そ、そんなことはございません!けれど、何だか恐れ多くて」
「ならいいじゃないか。明日は試験だ。必ず合格してみせるから、リイネはどこに住むか考えておきなさい」
アルテミアは早々と布団の中に潜り込んだ。リイネはそんな主人の様子を呆れたように見つめた後、そっと蝋燭の火吹き消した。
◆◆◆
その一週間後、試験に見事合格したアルテミア――アルテは騎士団の服に身を包んでいた。試験結果は歴代最高、満場一致での合格だった。
早速今日から街の見廻りを担当することになったアルテミアは、鍛錬場でペアとなる人物の到着を待っていた。
「やあアルテ!待たせたな」
現れたのはあの日騎士団について教えてくれたローレンだ。
「どうだい?新しい生活は。家はもう決まったんだっけ?」
「ああ。お陰様で住みやすい家が見つかったよ。妹も喜んでいる」
「それは良かった」
シルヴィヌ王国では単身者は寮に入るが、ここオルテガ皇国では各自が希望した住居が与えられる。その点だけでも故国とは大きく異なる点だった。それにここは人種だけでなく性別にも差別がない。寛容さも持ち合わせているからこそ活気も生まれるのだろう。アルテミアは一人納得しながらも、それにしては女性の騎士団員の姿が見つからないことが気になった。
「ところで、女性騎士団員はとこにいるんだ?」
「え?何を言っているんだ?騎士団員は男だけだろう?」
「え?」
アルテミアは身体がぴしりと固まった。
「女性団員は、いないのか?」
「ああ」
「……どうしてだ?」
「まあ、規則でそうなっているからな。それに女性はか弱いだろう?力仕事の騎士は難しいだろう」
「では、私は?」
「アルテ?アルテはだって男だろう?まあ男の割には華奢だけど、その分剣の腕はピカイチだからな。……あ、もしかして女に間違えられそうになったのか?」
ローレンが心配そうな顔でアルテミアを覗き込む。
「あ、いや、大丈夫。間違えられたりは、していない。しかし今後女性団員を入団させる予定はないのか?」
「どうだろう?規則が変われば話はまた違ってくるだろうけど、なんせ議会を通して決定することだから中々難しいんじゃないのかな。」
「そうか……」
ポツリと呟いたアルテミアは考えていた。
そう言えば試験の際に、性別を問われることはなかった。女性団員は認められていないが、アルテミアは何の疑いもなく団員として入団することができた。それは即ちどういうことが言うと……
(男性だと思われているなら、それでもいいか)
アルテミアが出した結論は、酷く単純なものだった。生活基盤も整えたばかりし、別に女性として扱われたい訳でもない。ならば暫くは問題もないだろう。
しかしこの判断が、これから大きな騒動になっていく事を彼女はまだ知る由もないのだった。