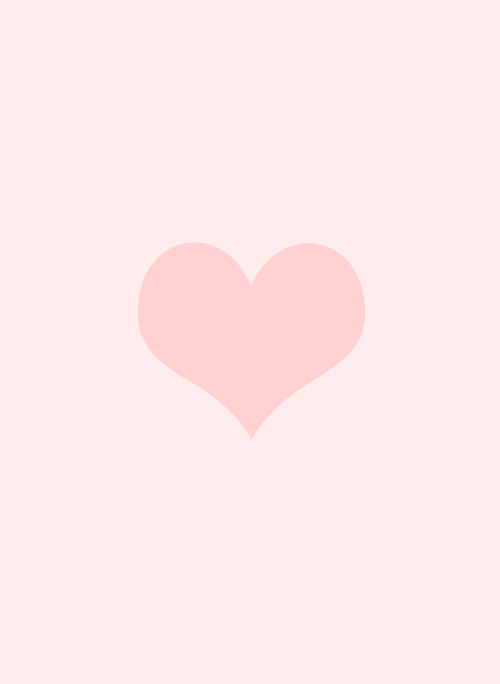蜜月と甘い嘘 〜忘れられた辣腕社長は記憶を無くした花嫁を離さない〜
◇◇◇
「うーん……こんな感じでいいのかなぁ?」
店舗の仕事を終え帰宅した私は、夕飯の準備もそこそこに三宅君から渡された紙にイラストを描いていた。ダイニングテーブルに広げた真っ白な紙に、ペンを次々に走らせていると、背後で扉が開く音がした。
「ただいま……っと、どうしたのこれ?」
夢中になって描いていたら、すっかり昴さんが帰宅する時間になっていたようだ。頭上からの声に慌てて紙を隠そうとすると、そのうちの一つに手を伸ばされた。
「big smile for you……?これ、久美が描いたの?」
「あ、えっと、それはそうなんだけど……」
彼がどんな顔をしているのか見たくなくて、思わずそっぽを向いてしまう。けれど、彼の口から漏れたのは失笑ではなく、感心した様な吐息だった。
「へぇ……。いいね、これ。すごくいい」
「え?」
「温かみがあるっていうのか……。描いた人の優しい気持ちが伝わってきて、癒される感じがするね」
思ってもみない絶賛に、戸惑いながら口を開く。
「……でも、幼稚じゃない?」
「幼稚っていうか…これは『味わい深い』って言うんじゃないの?」
彼は美術館の絵画でも鑑賞するように、顎に手を当ててじっくりと私の絵を眺めている。その柔らかな眼差しには、お世辞を言っているような気配は微塵もなかった。
「そ、そうかな……」
「うん。僕、この絵好きだな。……ねえ、これ一枚もらってもいい?」
まっすぐに褒められるのは、悪い気はしない。けれど、あまりに熱心に見つめられると、今度は羞恥心ともまた違う恥ずかしさが込み上げてくる。
「ええ、いいけど……。あ、もう、夕飯にしよう!」
私は咄嗟に話題を変えようと、テーブルの上を片付け始めるのだった。
「うーん……こんな感じでいいのかなぁ?」
店舗の仕事を終え帰宅した私は、夕飯の準備もそこそこに三宅君から渡された紙にイラストを描いていた。ダイニングテーブルに広げた真っ白な紙に、ペンを次々に走らせていると、背後で扉が開く音がした。
「ただいま……っと、どうしたのこれ?」
夢中になって描いていたら、すっかり昴さんが帰宅する時間になっていたようだ。頭上からの声に慌てて紙を隠そうとすると、そのうちの一つに手を伸ばされた。
「big smile for you……?これ、久美が描いたの?」
「あ、えっと、それはそうなんだけど……」
彼がどんな顔をしているのか見たくなくて、思わずそっぽを向いてしまう。けれど、彼の口から漏れたのは失笑ではなく、感心した様な吐息だった。
「へぇ……。いいね、これ。すごくいい」
「え?」
「温かみがあるっていうのか……。描いた人の優しい気持ちが伝わってきて、癒される感じがするね」
思ってもみない絶賛に、戸惑いながら口を開く。
「……でも、幼稚じゃない?」
「幼稚っていうか…これは『味わい深い』って言うんじゃないの?」
彼は美術館の絵画でも鑑賞するように、顎に手を当ててじっくりと私の絵を眺めている。その柔らかな眼差しには、お世辞を言っているような気配は微塵もなかった。
「そ、そうかな……」
「うん。僕、この絵好きだな。……ねえ、これ一枚もらってもいい?」
まっすぐに褒められるのは、悪い気はしない。けれど、あまりに熱心に見つめられると、今度は羞恥心ともまた違う恥ずかしさが込み上げてくる。
「ええ、いいけど……。あ、もう、夕飯にしよう!」
私は咄嗟に話題を変えようと、テーブルの上を片付け始めるのだった。